859氏による強制肥満化SS

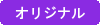
「おかわり!」
どんぶり茶碗を掲げ、幸せそうに宣言する妹の莉子。
その笑みは輝かんばかりで、見ているこちらまで無性に嬉しくなってくる。
これで手放しに喜ぶことができれば言うことはないのだが…。
「なぁ、これで何杯目か覚えているか?」
「4杯目だけど?」
事も無げに即答する莉子の姿に溜息を一つ。
炊飯器からおかわりのご飯を盛り付けている間も、莉子は休むことなくテーブル上のオカズを口に運んでいた。
莉子はいわゆる痩せの大食いだ。幼い頃から人一倍食べ、それでいて太ることは無く、今では男子から常に熱い視線を投げかけられるほどの美少女に成長した。
食べられる量に比例して、食べること自体も好きなようで、暇さえあれば何かを口にしている。
莉子がまだ子供の頃は、それほど極端ではなかったこともあり、綺麗に食事をたいらげるのをよく褒めていたものだ。
だが、食べる量が成長速度を大幅に超えてからは、不安が先走るようになった。
太らなければいいでしょ、と莉子は言うのだが、健康の方がその何十倍も大事だと思う。
むしろ、食べた分だけ太らないということ自体、常人ではありえないことなのだ。
幾度と無く食事量を控えるように言ってきたものの、それが受け入れられることは無かった。
家での食事担当は俺なので、こちらで出す量を減らすということも考えたが、そうなれば外で食べるようになることは容易に想像がついた。
莉子はとにかく味が濃いものを好む。好き勝手に食べるものを選ばせれば、ただでさえ崩れている栄養バランスが崩壊するのは間違いない。
できるだけ健康な食生活を保てるようにと、毎日の献立に試行錯誤を費やす日々。
しかし、どんな食事を作ろうが、絶対量が限度を超えていれば意味を成さず、何か劇的な方法はないかと俺は模索していた。
「で、私に協力を求めにきたわけだ」
「あぁ、こっち方面は専門だろ?」
自分の力だけではどうしようもないと悟った俺は、ある人物に相談を持ちかけた。
その人物こそ、今、俺の目の前にいる畑野明美だ。
白衣を身にまとい、すらりと伸びた足を組んでいる彼女は、近所でも評判の美人医であると同時に、俺の昔なじみでもあった。
「そういえば、彼女とは最近会ってなかったわね。よく食べる娘だったって記憶はあるけど、そんなにひどいの?」
「そう言うと思って、ほら、これが昨日の莉子の夕飯の内容だ」
明美にデジカメで撮った写真付きのプリントを渡す。
それを目にした瞬間、ピシリと音を立てるように明美が固まった。
予想していたリアクションとはいえ、少々複雑ではある。
「はぁ、これはこれは…… うん、まいったわね、こりゃ」
苦笑すら浮かべてお手上げポーズ。
「失礼だけど、妹さんの身長と体重、聞いてもいい?」
「確か、156cmの40kgぐらいだったかな。3サイズまでは把握していないが」
「いいお兄さんね、まったく。それはともかくとして、データ的には痩せすぎ一歩手前ってところかしら。この身体であの食事量なんて冗談だとしか思えないわ」
「やっぱり、このままじゃマズイよな」
「調査もせずに断言するのは医者として避けたいところだけど、好ましくないのは確実ね。特に塩分摂取量から考えると、最悪、30歳手前で糖尿病、なんてこともありえるわ」
「………」
室内を重苦しい空気が占領する。
「なんとか、ならないのか」
「とにかく摂取量を減らすこと。当たり前だけど、これが一番効果的ね。他にも手はあるけど、摂取量が多かったら焼け石に水だし」
「それはわかっているが……」
「妹さんに言っても聞いてくれない、でしょ? 安心して。アドバイスした以上は対応策まで用意するのが医者の仕事だから」
にっこりと微笑むと、机上の薬ビン棚から茶褐色のビンを取り出す。
「それは?」
「消化吸収補助剤。その名の通り、胃や腸の消化吸収を助ける薬よ。これは拒食症の人なんかが取れる量が少ない分、最大限の栄養を取るためのものであって、市販されているものより、効果はかなり高めだけどね」
「すまん、話がよく飲み込めない。それがどうして食事量を減らすことに繋がるんだ?」
「発想の逆転よ。そもそも、妹さんが摂取量を控えないのは『食べても太らない』からでしょ? なら、他の人と同じように、食べた分だけ太るようになったら?」
「そうか、自分から食事の量を減らすように……」
俺の呟きにコクリと首を縦に振る明美。
「出来れば、こんな手は使いたくないんだけどね。同じ女として、太るのがどんなに辛いことか理解しているだけに、ね」
憂いを帯びた表情の明美に、言い知れぬ不安が掻き立てられるが、それを誤魔化すように笑顔を作り、
「なーに、太るって言っても一時的にだろ? 莉子は陸上部に入っているし、食事の量さえ減らせばすぐ元通りになるさ」
「だと、いいんだけど」
こうして俺は、明美から消化吸収補助剤を処方してもらった。
莉子を少しひどい目にあわせることになるが、良薬は口に苦いものと決まっているのだ。
このときの俺は、希望を見出せた事に舞い上がるばかりに、この薬により引き起こされる事態を欠片も予測できないでいた。
家族水入らずの夕食。
相変わらず、莉子はテーブルの上を埋め尽くすほどの大量の料理を食べていた。
莉子の食べ方は早食いのそれのように見苦しい食べ方ではない。
口いっぱいに頬張ることも無いし、ちゃんとよく噛んでから飲み込む。
ただ、休むことなくひっきりなしに口に運んでいるため、気が付けば皿の上の料理が綺麗さっぱり消えているのだ。
「兄さん、おかわり」
いつものようにどんぶり茶碗を差し出す莉子。
だが、俺は顔を曇らせて受け取りを拒否する。
「兄さん?」
「なぁ、いい加減に食事の量を控えないか?」
「なんだ、またその話ですか?」
聞くのもウンザリと言わんばかりに顔をしかめられる。
「この前、明美のところに相談にいったんだ。そしたら、このままだと若いうちから糖尿病になるかもしれないって……」
「それぐらいの自己管理はちゃんとできています。なったらなったで、自己責任ですから兄さんには関係ありません」
「…………」
何度となく繰り返されてきたこのやり取りは、今日も平行線のままだった。
もしかしたら、今日こそは心変わりしてくれるかもしれないという、淡い期待を抱いていたのだが。
「……身体を壊す前に、そのままだと太るぞ」
「大丈夫です。食べても太らない体質ですから」
苦し紛れの皮肉と受け取ったのか、そっけない言葉を残して、自らおかわりを盛りにいく莉子。
――まさか、それが俺からの最後通告だったとは、夢にも思っていないに違いない。
莉子が自室のある2階に上ったのを確認してから、行動を開始する。
とは言っても、することといえば、明美から渡されたこの薬を、冷蔵庫の中にある開封済みのペットボトルコーラにいれるだけなのだが。
実のところ、明美にこの薬を渡されたその日から、俺はこの薬を服用していた。
明美を信用していなかったわけではないが、実際にどのくらい効果があるものなのか確かめておきたかったのだ。
約一週間飲み続けたその結果は、驚く無かれ、なんと――500g増。
なんと言うか、もはや誤差の域だが、そもそも太るための薬ではないのだ。
人並みの食事量しか取らない俺が服用しても、意味が無いのはある意味当然だったのかもしれない。
だが、本当に効果が薄いという可能性も捨てきれないので、指定された量よりも少し多めに入れておくことにする。
『ダメ元で』という思いが、その安易な行動を助長していた。
よく混ぜたあと、試しにほんの少し飲んでみる。
「うん、これなら飲んでも気づかれないな」
呟いてから、これが毒薬や睡眠薬だったら、まるっきり犯罪者の行動だなと苦笑する。実際、そう違いは無いのかもしれないが。
「兄さん?」
「!?」
背後からかかってきた予想外の声に、思わず身体をびくつかせる。
「暗いところで何をやっているんですか? と言うか、妹に声かけられただけでビビらないでください、情けないですから」
「あ、あぁ、莉子か。ちょっとな」
誤魔化しながら、薬の入っていた包み紙をくしゃくしゃに丸めて、ズボンのポケットにねじ込む。
「こんな夜中にコーラだなんて…… 太りますよ?」
「自分のコップを取り出しながら言う台詞じゃないと思うんだが」
「私はいいんです。そういう体質ですから」
誇らしげに胸を張りながら、薬入りのコーラをドボドボとコップに注ぐ莉子。
ばれない自信はあるのだが、どうしても気になり、チラチラとそちらに視線を向けてしまう。
「なんですか、何か言いたいことでも?」
「いや、なに」
コップの半ばまで飲み干されたコーラに、ホッと胸を撫で下ろしながら、俺は呟く。
「確かに、気をつけような。――お互い様に」
目に見えた効果が現れ始めたのは、意外にもその次の日の朝だった。
カリカリに焼いたベーコンと目玉焼き、ポテトサラダ、フルーツの盛り合わせetc...
早起きして作り上げたそれらは、おおよそ、一般家庭の五人前に相当する。
まだ、重く閉じようとするまぶたをゴシゴシと擦る。夕食の残りでも出せたら少しは楽になるのだろうが、
幸か不幸か、我が家では出された料理が次の食事まで残っていることはまず無いのだ。
調理者としては、残らず食べてくれるのは嬉しくもあるのだが、やはり胸中は複雑である。
そんなこんなで、この朝食もスムーズに莉子のお腹の中へと消え去るものだと思っていたのだが。
「…………」
莉子の箸が止まっていた。
すでにおかずの大半はたいらげていたので、これがもし他の人だったら気にすることは無かっただろうが、この程度の量で食事のペースを落とす莉子でないことは俺が一番よく知っている。
「どうしたんだ、莉子?」
「べ、別になんでもありません…!」
つっぱねる莉子であったが、どこか腑に落ちなさげな表情で、しきりにお腹をさすっていた。
これはもしや、という思いが胸の中で沸き起こる。
あの薬は消化吸収を補助するものだと聞いていたが、副次効果でいつもよりも早く満腹と感じるようになったのではないか。
素人考えもいいところだが、事実、莉子の様子がその仮説を裏づけしている。
もしかしたら、太るよりも早く、自ら食事量を控えるようになるかもしれない。
考えうる限り最高の結末が垣間見え、それだけでだいぶ気が軽くなる。
「無理しなくていいんだぞ。残しておけば、夜にも食べられるんだし」
「……っ! なんとも無いって言ったはずです。私はこれでちょうどいいんですから!」
吐き捨てるように言葉を残して、再び食事に戻る莉子。
助け舟を出したつもりだったが、逆に莉子のプライドを傷つけてしまったようだ。
焦ることはない、と自分に言い聞かせる。
たとえ何日かかろうと、最終的に食生活が改善されれば問題ないのだ。
気を落ち着かせるため、俺はブラックのコーヒーをグイッと飲み干した。
************
何かがおかしい。
歯を磨きながら、私は言い知れぬ不安に襲われていた。
今朝、ベッドで目が覚めてからというもの、どうにも歯車がかみ合っていないような、不思議な感覚が身体に纏わりついているのだ。
熱っぽさは無いので風邪ではないだろうし、気分もいたって良好だ。
まったくもって正体不明の感覚だったが、朝食を取っているうちにあることに気が付いた。
無意識にお腹を撫でる。この中には今の今まで食べていた朝食が、たっぷりと詰まっているはずである。
だと言うのに――
普段なら感じるはずの充実した満腹感。それが欠片も感じられないのだ。
************
薬を盛ってから二日目の朝。
あくびをかみ殺しながら、一口サイズに切りそろえた色鮮やかな生野菜の数々を、大皿に盛り付けていく。
ここであらかじめ少量の塩を振っておくのがポイントだ。
味付けを莉子に任せてしまったら、それこそ見ているだけでウンザリするような、こってりとした一品に仕上がるのは目に見えている。
現時刻を確認して、ラストスパートに取り掛かろうとした、ちょうどそのとき、背後から声がかかってきた。
「おはようございます、兄さん」
「あぁ、おはよ…」
反射的に振り向きながらの挨拶は、しかし、半ばで止まる。
一瞬、目の前にいるのが誰だか分からなかったのだ。
それは一瞬のことで、すぐにそれが莉子だということに気づく。
外見に劇的な変化があったわけではない。
ただ、ほんの少しだけ、いつもよりも顔つきがふっくらとしていたのだ。
それは本当に些細な変化であったが、だからこそ、逆に強い違和感となって印象に残ってしまう。
「どうしたんですか、兄さん?」
不思議そうに小首をかしげる莉子。
「いや、なんでもない。もうすぐ出来上がるから、顔洗ってこいよ」
首を横に振って誤魔化す。
おそらく、まだ莉子は自分の変化に気づいていないはずだ。
自分の変化に気づいた時、莉子はどのような反応を示すのだろうか。
このときの俺は、自身の使命よりも好奇心の方が勝っていた。
************
「…………」
鏡との無言のにらめっこは、数十秒間にもおよんだ。
「なんですか、これは…」
口の中で呟いた言葉には、苦渋の色が濃く滲んでいる。
鏡に映る自身の姿。それは、昨日までの見慣れたものとは少し違っていた。
わずかばかり、ふっくらと横に膨らんだ顔。
言わなければ、その変化に気づかない人もたくさんいるだろう。
だが、私自身にとっては非常に由々しき問題であった。
昨日の生活パターンを脳裏に思い浮かべる。
特に変わった事は無かったはずだ。いつものように起きて、いつものように食べ、いつものように寝た。
ただひとつ、変わったことがあるとすれば――
「…………」
お腹をさする。結局、昨日は満腹を感じることが一回も無かった。
終始空腹というわけではない。食べれば、ちゃんと空腹感は消える。
ただ、いくら食べてもこれ以上入らないという気にならないのだ。まったくもって、不思議なことに。
「でも、これが原因と言うことはありえませんね」
私はいくら食べても太らない体質なのだから。
満腹感を感じようが感じまいが、食事が原因で太るなんてことは絶対にありえない。
「やっぱり寝不足でしょうか。最近、課題をこなすために徹夜も多かったですし」
顔のむくみとは印象が異なっているような気もするが、気のせいだと自分に言い聞かせる。
そうだ、兄さんにどう見えるのか聞いてみましょう。
自分と他人とでは受ける印象も変わってきますし。
そうと決まれば実行あるのみ。
タオルで顔を拭うと、私は洗面所を後にした。
************
「…………」
向かい合わせで座った朝食の席。
先ほどから何か言いたげに、莉子がちらちらとこちらへ視線を送ってくる。
だいたいの察しはつくのだが、下手に突っついて昨日の二の舞になるのは避けたいところ。
これは待ちの一手だなと、あえて無視して食事を勧める。
結局、莉子が話を切り出すころには、テーブルの上の食事はほとんど消え去っていた。
「あの…… 兄さん。どこか、変わったところは無いですか?」
「ん、俺は特にいつも通りだけど」
「いいえ、兄さんではなく私のことでして」
なんとも歯切れ悪く訊ねる莉子。その表情は隠し切れない不安で曇っている。
さて、どう答えるべきだろうか。
「言われてみれば…… そうだな。ちょっと膨らんでないか、顔」
「……っ!」
とりあえず、無難そうな反応をしてみると、みるみるうちに莉子の表情が険しくなる。
「や、やっぱり、兄さんもそう感じますか?」
「あぁ。だけど、言われなきゃ気にならない程度だぞ?」
「そ、そうですか……」
ホッと胸を撫で下ろす莉子。その表情が安堵で和らいでいく。
そんな予想通りの反応に、俺は内心でほくそ笑んでいた。
これくらいでダイエットを決意されても、喉元過ぎればなんとやら。
数日後には元の食事量に戻り、「あれは兄さんの勘違いだった」で片付けるのは目に見えている。
完全に改善されるためには、それこそトラウマになるくらいの荒療治が必要なのだ。
莉子自身が自分で自分を誤魔化しきれなくなるまで、せいぜい鈍感な兄を演じているとしよう。
************
ベッドに腰を掛け、現時刻を確認する。
午後九時十五分。
今日び、小学生でもこの時間帯に寝るのは少数派だろう。
あの後、四方八方手は尽くしたのだが、結局、顔のむくみが取れることは無かった。
学校でのことを思い出す。直接口にする人はいなかったものの、私を見てあからさまに表情を変えた人が何人かいた。
少なくとも、その倍程度は私の変化に気づいた人がいたはずだ。
考えるだけでも気が滅入ってくる。気が滅入ると言えば、昨日に引き続いて今日も満腹感を感じることが出来なかった。
何かにつけて食事制限を迫ってくる兄さんのことだから、こっそり気づかれない程度に食事を減らしているということも考えられるが、食べている量は減っていないという認識はあるのだ。
ただ、満腹感が感じられないおかげでその実感が全然沸かない。
実感が沸かないということは満足していないということだ。
最初は不思議に思う程度だったが、今ではすっかりストレスとなって私を苦しめている。
「どちらも、明日には治っているといいんですが」
誰にともなく祈り、ベッドに横たわる。
そのまま瞳を閉じれば、深い深い眠りに………
…………………
…………
「……眠れません」
まぁ、実際、眠くないのだから当然か。
すっかり夜型の生活が染み付いているのに加え、食欲が完全に満たされていないことがそれに拍車をかけていた。
考えること、しばし。
「仕方ありませんね」
溜息を漏らしながら、寝返りを打って身体を横に傾ける。
肩を数回揺らして姿勢を安定させると、そろそろと腕を下半身に伸ばしていく。
臍のあたりから、指をパジャマの表面に滑らせて下降させていき、太ももの間に潜り込ませる。
「……んっ」
ピクッと体が震え、鼻から空気が抜ける。
手のひらを太ももで挟んだまま、指の先で股間を引っかく。
パジャマ越しとはいえ、和らいだ感触がしっかりと奥まで届いてくる。
誰にも明け渡したことの無い秘密の場所。
だからこそ、そこへの刺激はひどく甘美なものだった。
決して早めることなく、幾度も指を前後に往復させる。
「んんぅ、ぁ……、んふぅ……」
気を抜けば声が出てしまいそうだ。
時計の針が時を刻む音以外、何も音を発しないこの部屋にそれはよく響くだろう。
下手をすれば、兄さんにも……。
「んんっ!」
想像した瞬間、一際大きい快感の波が身体を揺らした。
自分のことをはしたない娘だとは思いたくないが、時々、そちらの素質があるのではと勘ぐってしまう。
もちろん、それは単なる思考遊び。快感を高めるための媚薬のようなものだけれど。
「はっ、んぅっ……、んんぅ、ん……」
もどかしい快感に、もぞもぞと体全体を揺する。
この曖昧な感覚を長引かせるのが、私のいつもの楽しみ方なのだけれど、今回に限ってはそう悠長にしていられない。
パジャマのボタンを上から三つほど外し、生じた隙間からもう片方の手を差し込む。
年相応の膨らみをやんわりと揉んでから、その頂点にカリッと爪を立てる。
「……っ!」
緩急により何倍にも膨れ上がる快感。
それで満足せずにさらに乳首を弄っていく。
硬く尖っていく敏感なそこは、力を入れすぎれば痛くなるだけだ。
昂る精神を必死に押さえつけながら、うっすらと先に見えるゴールへ、体全体の感度を高めていく。
それは、予想していたよりも案外早く訪れた。
「…んんんっ!!」
叫びあがりそうになるのを、歯を食いしばって堪える。
全身を突き抜ける快感に意識が飛びそうになるが、それも時間にしてみれば数秒のこと。
波が過ぎ去った後に残るのは、心地よい疲労感だけだ。
「ふあぁぁ…」
人目が無いことをいいことに大あくび。
行儀は悪いけど、今は我慢する方が身体に悪い。
後始末もそこそこに、今度こそ私は深い眠りについた。
悪夢を見た。
内容ははっきりと覚えている。
親友の久美子と教室で昼食を食べているシーンから、その悪夢は始まった。
談笑に花を咲かせていると突然、久美子が銃を取り出し、私に向かって発砲してきたのだ。
撃たれても痛くは無く、外傷も無いのだが、そのかわり撃たれるたびに風船のように私の体は膨らんでいった。
服が内側から弾け飛んでもそれは止まらず、まるでホラー映画のように同級生達が押しつぶされては私の肉に溶け込んでいく。
やがて、私の身体は教室中を埋め尽くし…… そこで目が覚めた。
ひどく混沌とした、ある意味で夢らしい夢だったが、夢の中で私は確かな恐怖を感じていた。
そのせいか、パジャマのみならず、シーツまで寝汗でぐっしょりと濡れている。
肌に直に張り付いたパジャマが不快極まりない。
カーテンの隙間から差し込む日の光はあんなにまぶしいというのに、それに反して最悪の目覚めだ。
重い気持ちが身体まで引きずっているのか、起き上がるのすらひどく億劫だが、いつまでもこうしてはいられない。
「んんっ……!」
気合を入れて、一気に起き上がる。
そのままの動きで背を反らせて身体を伸ばし――
「……あれ?」
違和感が生まれた。いつもと同じ動作なのに、いつもとは少し違うような……。
違和感の正体を探るべく、恐る恐る身体を見下ろす。
「……なっ!?」
普段なら背を逸らしても肌を晒すことはないのに、私の見つめる先ではパジャマがお腹の半ばまでめくれ、おへそが完全に顔を出していた。
寝ている間にパジャマが小さくなった? いいや、そんなことあるはずがない。
背中に冷たいものが走り、寝ぼけていた思考が急速にクリアになっていく。
ここにいたって、私はようやくあの悪夢の要因となったあることを思い出した。
焦燥感に急かされるがまま足を速め、部屋の隅にある化粧台の前へと向かう。
「……嘘」
鏡にうつった私の顔は、昨日と変わらず、膨らんだままだった。
むしろ、悪化しているようにも見えるのは私の気のせいだろうか。
無意識に、パジャマがめくれあがって晒されたままのお腹を撫でる。
プニプニとした搗き立てのお餅の様な弾力が、私の手を押し返していた。
「むぅ……」
ケチャップとマヨネーズをたっぷりとかけたスクランブルエッグを頬張りながら、私は何故こうなってしまったかを考えていた。
昨日は単なる顔のむくみだと思い、睡眠時間をたっぷり取ったのだがそれは無駄に終わったらしい。
ボリュームアップしたお腹が、事が顔だけにとどまってはいなかったことを物語っている。
「………」
こっそりと兄さんの様子を伺う。
コーヒーを片手に新聞へと目を走らせており、私には微塵も注意を向けていない。
服をきちんと着たら、お腹の膨らみはほとんど目立たなくなったが、やはり他人からどう見えるのか気になるところ。
だが、迂闊に訊ねて、もし相手が気づいていなければ、それこそ自ら墓穴を掘るというものだろう。
考えたところで埒が明かないので、ひとまずそれは棚に上げる。
むくみではないとするならば、これはいったいなんなのだろうか。
考えられるものと言えば…… 病気? 単なる思い付きだったが、ひょっとしたらいい線をいっているかも知れない。
それまでと変わらぬ生活を送っているのに、急に体が膨らみ始めたなら原因は病気としか考えられないのではないか。
事実、おたふく風邪のような例もある。
体全体が膨らむ病気があってもおかしくはあるまい。
ただ、原因が病気だとしたら困ったことが出てくる。
対処法が分からない。つまり、これ以上の悪化を食い止める手段が無いのだ。
やはり、医者に見せるべきだろうか。そういえば先日、明美さんの名前を聞いたような……。
そんなことを考えなら、私は本日4杯目のおかわりを口に運んだ。
「起立!礼!」
学級委員の号令で全員が頭を下げる。
一瞬の間をおいて、途端に教室中が賑やかになりはじめた。
今日の授業はこれで終了。これからは魅惑の放課後タイムだ。
昼休み以上の喧騒があちらこちらで沸き起こる中、私は部活の準備をしていた。
私が所属しているのは陸上部だ。
自慢ではないが、県大会でも好成績を残せる程度には実力がある。
ナップサックからシューズを取り出し、続いてユニフォームを取り出そうと手を入れたところで、
「……っ」
ぴたりと動きが止まる。
制服ならまだ隠すことの出来たお腹の膨らみだけど、薄手のユニフォームに着替えたら……。
「莉子ちゃん、どうしたの?」
固まったままの私を不審に思ったのか、久美子が声をかけてきた。
久美子も陸上部に所属しており、その胸には私と同じユニフォームが抱かれている。
「う、ううん、なんでもない。ただ、その……」
一瞬、ナップサックの中身をチラリと見て、
「ユニフォーム、洗濯したまま忘れてきちゃって」
「へぇ、珍しいね。莉子ちゃんが忘れ物だなんて」
その言葉に、ドキリと鼓動が警鐘を鳴らしたが、どうやら他意は無かったようで、「先に行ってるね」と一言を残して、久美子はその場を去っていった。
私は安堵の溜息をつくと、親友を騙した罪悪感に少しだけ心を痛めながら、彼女の後を追った。
その日、私は体操着で部活をこなした。
一人だけ服装が違うことで、周囲からの視線が集まり、まるでそれら全てが私のお腹を注目しているような気がして、心休まる時は一時もなかった。
案の定、タイムは散々で、「いつもとは環境が違うから」と誤魔化したものの、実際は走るたびにたぷたぷと振動するお腹が気になってしょうがなかったからだ。
心なしかスタミナも落ちたような気がする。
これから、私はどうなってしまうのだろうか。