Naoki氏による強制肥満化SS
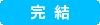
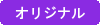
「姉ちゃん、また携帯いじってるの?」
あたしの5つ上のお姉ちゃんは、美人だ。
色白で目がぱっちりしてて、鼻筋が通ってて、細くて、実はちょっと貧乳。
性格もおっとりしてて優しくて気さくで頭もいい。
12歳のあたしが言うのもなんだけど、なかなかの逸材だ。
ただ、完壁な人間なんてどこにもいないもので、
姉ちゃんには一つ決定的にいやなとこがあった。
「えー、休みの日ぐらい良いじゃんかー。」
「って言って毎日何時間も触ってるよ!高校生なのに勉強とかしなくていいの?」
「母さんと同じこと言わないでよ、まるで回し者みたい。」
姉ちゃんはだらけ魔だった。
高校二年生の姉ちゃんは、帰宅部で、17時過ぎぐらいに帰ってくると、
速攻でスウェット上下に着替える。
それからリビングのテレビの前を、ブランケットにくるまりながら陣取って、
携帯を充電器につないだままスナックをつまみつつひたすら彼氏や友達とメールしてる。
自分の部屋でやればいいのに、リビングの方が暖かいからってわざわざここにやってくる。
それからずっとテレビの前で携帯といちゃいちゃしてるんだ。
飽きたらあたしのジャンプを読んだり、あたしの分のスナックまで食べたり、爆睡したり、
好き放題だ。
あたしが自分の部屋で宿題を終わらせてテレビを観に来た時も、
友達とバレーをやってから帰ってきた時も、
夕飯を食べ終わってからも、絶対にいる。
別にそれが悪いわけじゃないんだけど、
なんか見てて良い気分じゃないんだよなぁ。
ママもそれを見るたび、いつまでだらだらしてるの、
来年受験なのよ、とか言ってるんだけど、姉ちゃんには馬の耳に念仏だ。
あたしはいつだってこれはどうにかしなければならない問題だと思っていた。
「ハルナー!電話よ!」
あたしがうだうだやっていると、ママの声が聴こえた。
時計を見ると、11時29分。日曜日のこんな真昼間に電話してくるのはきっとあの人だ。あの人しかいない。
「もしもし?」
「ああ、ハルナか?おはよう、私だよ。カトリだよ。」
「うん、わかってたよ。」
彼は郁原カトリ。
年齢不詳、国籍不詳、職業不詳、もはや郁原カトリというのが本名かどうかすら怪しい。
解っているのは、彼はあたしの友達だということと、
金持ちだということと、めちゃめちゃ天才だということ、天才過ぎて非常識極まりないこと、
動物と話せるということ、それからいつだってなんだか怪しげなものを作っていること。
「私の3時間の努力が報われそうなんだ、早く来てくれ!」
「たった3時間ならあたしがその瞬間を見届けてやる必要もないんじゃない?」
「いいからはやく!」
やれやれ、解ったよと電話を切りながら、あたしは内心わくわくしながら外出用の上着にそでを通した。
「人間の行動を何かのスイッチにできるリモコン?」
なんだそりゃ、とあたしは出された四ッ谷サイダー梅味を堪能しながら、
梯子の上で作業するカトリを見上げた。
埃っぽいだだっ広い研究所。カトリは今3mの洗濯バサミを遊び心で作っていた。
誰得なのかはあたしにもわからなかった。
「ああ、例えば今君がサイダーを飲んでいるだろう、ハルナ。その“行動”を“梯子”のスイッチにしてみよう。」
カトリは白衣のポケットから何やら銀色の薄い箱のようなものを取り出した。
Ipodみたいだ、と思った。
カトリはそれをあたしに向けてカチッとやった。
なんだか赤い光が見えた。
「さぁ、一口飲んでみな。」
あたしは言われたとおりにした。すると、
ウィイイイン
「お、おおお!」
梯子が下がった、というより縮んだと言った方が的確かもしれない。
梯子はあたしがサイダーでのどを鳴らした瞬間ガクンと地面に着いた。
「驚いたろう、雨に濡れた自転車が錆びているのを見て思いついたんだ。まぁ、これはそんな物理的法則に縛られず、何にだって使えるんだがね。」
カトリが梯子の上からドヤ顔で降りてきた。
「頭の中で想像しながら、対象に向けてスイッチをカチリとやるだけでいいんだ。授業中、ノートに消しゴムをかけるたび、嫌いな先生の髪の毛を100本消してやるとか、CDを一回聴くごとに視力がよくなるだとか。」
「なんか縛られてなさ過ぎていろいろ不安になるけど大丈夫なの?」
「ああ、犯罪になるようなことはできないしな。だから親父がたばこを一本吸うごとに心臓の血管が一本詰まる、とかはいくらスイッチを押してもリモコンに自動ロックがかかる。だがね……」
カトリは意味深に言葉を切った。
「なにせプログラムに1時間ぐらいしかかけてないもんだから、微妙なラインのは出来ちまったりするんだ。じーさんがキャバクラに一回行くごとに身長が1ミリ縮むとかさ。」
「そんなじーさんいないでしょー。」
「かはっ、ちがいない。」
カトリは豪快に笑った。
だけど、あたしはそのじーさんのたとえを聞いて、すごいことを思いついてしまった。
「ねぇ、カトリ、これはどのぐらい効果が持続するの?」
「ん、ああ、操作主の気が済むまでだ。」
確かにあたしがサイダーを飲んでももう梯子はぴくりともしなかった。
「ねぇ、これあたしに1日貸してくれない?」
「ああ、構わんが、あんまわけのわからんことするんじゃないぞ。」
「解ってる!」
あたしは今、とんでもない顔をしてるんじゃないかと思う。
「ただいまぁ。」
「遅かったのね。もう16時まわってるよ、ハルナの好きなアニメ始まるんじゃない?」
もう16時をまわっていても、姉ちゃんはまだだらだらしていた。
「あー!またあたしのうすしおポテチを!」
「あ、ごめんごめん、つい…。」
「ついじゃないよ、もー!」
「まぁまぁ、同じ奴3つ買ってあげるからさー」
「1つで良いったら!!」
そんな姉ちゃんの過失は、あたしのトンデモな企みに拍車をかけるに十分だった。
女の子にとって一番やなことだけど、姉ちゃんのためを思ってやることだから、許してね……!
あたしは姉ちゃんに見えないように、そっとリモコンのボタンを押した。
「姉ちゃん、また携帯いじってるの?」
あたしの5つ上のお姉ちゃんは、美人だ。
色白で目がぱっちりしてて、鼻筋が通ってて、性格もおっとりしてて優しくて気さくで頭もいい。
ただ、完壁な人間なんてどこにもいないもので、
容姿になんの欠点もないかと言われればそうでもなかった。
「えー、休みの日ぐらい良いじゃんかー。」
「って言って毎日何時間も触ってるよ!まだ高校生なのにそんな体でいいの?」
「母さんと同じこと言わないでよ、良いのよ成長期だから。」
姉ちゃんはデブになった。
むっちむちの豊満ボディ。
3週間前までスレンダーで鳩胸だったくせに今じゃスイカを2つと、おばけカボチャを1つ、
それぞれ胸と腹にくっつけてるみたいだ。たぶん乗ったら気持ちいい。
スウェットは本来ゆったりしてるはずなんだけど、
ぱっつんぱっつんに張りつめて、姉ちゃんの白い肌をちらちらと隠せずにいる。
たぷんたぷんの足はおそらく以前の姉ちゃんのウエストよりも大きい。
丸い背中が邪魔で、テレビが見えないのには困ったものだが、
姉ちゃんの綺麗な顔にふわっとついた脂肪は、女性らしさを引き立て妙に色っぽい。
姉ちゃんが不細工じゃなくてよかったと心から思った。
急にこんなに太っても、誰にも何も悪く言われないのは姉ちゃんの人望の見せる技だろうか。
学校じゃあ、包容力が体に出てグッドだとか何とか言われてるらしい。
「姉ちゃん…、成長期は結構だけどさ…、制服とかきつくないの?糖尿とかこじらせないでよね……。」
「何いってんの、姉ちゃんは無敵だよ!」
死にゃあしないよ、と、にかっと笑う。
「だけど、歩きにくいからちょっとは運動しようかな…。」
「それがいいよ」
あたしの気が、済んだ。
「ハルナ、君、やってくれたな。」
次の週末、カトリのところへ行くと、彼はにやにやしていた。
「ん?なんのこと?」
あたしはすっとボケてみせた。
「私が昨日公園を散歩してたら、君の姉貴がユサユサ走っているのが見えたよ。
私の記憶じゃ、彼女はあんな巨体じゃあなかったはずだ。おかげで少しよく見ないと解らなかった。あれは君がなにかやらかしたんだろう。」
「その通りだよ。言わずもがなカトリのリモコンを使ったんだ!
あんまり姉ちゃんがだらだらするもんだから、
“姉ちゃんが3時間連続でだらける”ごとに、
“姉ちゃんの脂肪細胞が1kg増える”ようにしたんだ!」
「それで3週間で倍の体格にねえ……」
「40kg近くは増えたと思うよ!でもあたしの気はもう済んだんだ!」
だから姉ちゃんはもう太らないはずさ、
これに懲りてだらだら癖を止めてくれたらあたしの勝ちだ、と続けると、
カトリがにんまりした。
「ハルナ、君、私の気は済んでいないんだ。」
「え?」
「ハルナ、私はね、人が肥えていくのを見ると興奮するんだ、私はさっき、やらかしてくれたね、ではなく、やってくれたね、と言ったろう。本当に興奮したさ、君の姉貴が通学しているのを毎日見かける度に、彼女がいかに日々膨れているか、しっかりわかったからね。」
あたしはカトリが何の話をしているのか読めなかった
「本当によくやってくれた、でかしたよハルナ…だけど君の気が済んだというのは本当に残念だ―」
カトリがあたしにリモコンを向けた。
「代わりに君が、私の性欲処理機になってくれ。」
カチッ
プクッ、ムクムクムクムクッ……!!
「え、ちょっ、なにこれっ!!!」
服がきつい…!急速に内側から体が膨れていくのがわかる。
「あつ、あつい…!」
膨大なエネルギーが体の中を駆け巡っていくような感覚。
「ちょ…っと!なに、したの…!!!」
口周りが膨れて上手く喋れない。
バリッ、ビリビリビリビリ…!!
ついにシャツが破けた。
あたしの成長しきってない胸と、まだくびれのないお腹がぼよんと飛び出る。
「君をスイッチにしたよ、ハルナ。どの行動が引き金になっているかは秘密さ。」
体が膨れて思うように動けないあたしをカトリがそっと抱きこんだ。
「私の気が済むまで、君はずっとこのままさ。」
カトリが、妖艶に笑った。