415氏その2
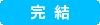

#ドラゴンクエスト3,ドラクエ3,Dragon Quest Ⅲ,DQⅢ
・プロローグ
「おいィ!あたいの怒りが有頂天になった!メガトンパンチ!」
「うぎゃああ!?や、やりやがったな!」
端的に言って、勇・武・魔・僧のパーティバランスは最高だった。
その中でも特に、武道家の活躍は特筆ものである。
「な…なめるなぁーッ!!!!」
研ぎ澄まされた格闘技術は彼女の拳を的確に急所へと導き、剣にも勝る凶器たらしめる。
「ほう?」
「そこにいたのにいなかった!?」
さらに、持ち前の素早さで攻撃をいなし、その守備力は重武装で固めた戦士に匹敵する。
結果、魔法使いと僧侶は勇者のバックアップに全力を注ぐ事ができるため、勇者もそのポテンシャルを遺憾なく発揮する事ができた。
「ハイスラァ!」
「追撃のグランドヴァイパ!みろ、見事なカウンターで返した!」
「ウボァー」
戦闘開始からここまで、実に2ターン。
この日の戦闘も、極めて効率的にこなす事ができた。
はずだった。
「さすが武道家は格が違いましたね。」
「すごいなー憧れちゃうなー」
「や、やだな…あたい照れちゃうよ。ていうか、それほどでもないって!…えへへ」
差し迫った脅威を退け、緊張を解いた一行は気付かない。
物かげから彼らを見つめる小さな影が一つ。
小型の魔物だ。
「クク…キヒヒヒヒ…」
その魔物の名を鬼面道士と言う。
本来ならば、現在彼女達の居るアッサラーム地方には出没するはずの無い強力なモンスターである。
「っ!?」
サッとおぞ気が走るような感覚に、武道家が身構える。
しかし、振り向いた先には、ただ岩があるだけだった。
「やはりMVPだった!しかも謙虚にもそれほどでもないと言った!」
「…気のせい?」
なおも武道家を褒めちぎる勇者たち一行。
彼女達の誰ひとりとして、今しがた自分達の被った致命的な被害に気づいてはいない。
遠ざかって行く談笑を聞きながら、岩に変化した鬼面道士は、勝利の確信にほくそ笑んでいた。
・一章
鍛錬を兼ねた金策を終え、勇者一行はアッサラームの町を訪れていた。
「ようこそトモダチ、ご注文おきまりデスカー?」
「あー、お腹すいた!」
「おいちゃん!ドネルケバブ8人前くださいな!」
ここに逗留しておよそ一週間、来たばかりの時は恐ろしく強く感じられた魔物とも、余裕を持って渡り合えるようになって来ている。
やたらと高い物価のせいで消耗品の補給にもう少しかかりそうだが、旅立ちの準備は整いつつあった。
「は…はち…?パードゥン?」
「あー、はい。8人前です、聞き間違いではなく。」
「はやくwはやくwあたいもうお腹すいて死にそうだよッ!」
武道家の利点として、金がかからない事があげられる。
軽くて動きやすい、言い換えれば材料費の少ない武具を用いて闘う武道家は、装備代が安く済むのだ。
「いただきまーす。はふ、はぐっ!むぐむぐむぐ…ごきゅん」
「相変わらずよく食べるわね。」
強いて言うならば、食費が他者の5割増しなのが問題だったが、そこはご愛敬。
ぶっちゃけパーティで一番活躍しているのは武道家なので、リーダーの勇者も食事代が少しばかり高くつく程度の事では文句を言いづらいのだ。
「むぐむぐ…うまい!もう一杯!」
「ほ、ほんとによく食べるわね…」
とはいえ、ここ数日、武道家の食事量は目に余るペースで増えていた。
当然、仲間たちも資金の減り具合などから、その事に気づいてはいたものの、この時は別段不信は抱かなかった。
普段の運動量を考えれば、彼女が良く食べるのはむしろ当然と思えたのである。
「まだまだ!後3人前は行けるわよー」
「ってまだ食べるんかい!?いくらなんでも太る…事も…無いか、うん。」
「平気でしょう。普段あれだけ激しく動いているのですから。」
「そーそー、一杯食べなきゃ大きくなれないよー」
宣言通り、追加注文分までペロリと平らげた彼女に、半ばあきれ、半ば感心する仲間たち。
しかし、予算より少なくなった軍資金で薬草を買い込んだあと、あろうことか武道家がもう一軒回りたいと言い出した時には、さすがに止めに入った。
「いいじゃんかよぅ…あたい頑張ったからお腹すいたんだよぅ…」
「うっさい、私らも頑張ったわ!」
彼女達にとってはちょっとした日常の一コマである。
この楽観が後の悲劇を招くとも知らず、ただ和やかな空気だけが流れていた。
・二章
「ふぅ…ふぅ…お、終わった?」
「…」
連日もりもりと大めしを喰らう彼女の動きは、急激に鈍って行った。
戦闘の効率も目に見えて落ち、2日で済むはずだった金策に既に5日もかかっている。
「あのさ…こんなこと言いたくないんだけど…」
「ふぅ…な、なにかな?」
言いよどむ勇者に、眉をしかめる余裕さえ無い。
一目でわかるほど丸くなった顔を振ると、脂汗が飛び散った。
仲間たちの顔にさっと嫌悪が走る。
「う…あ、あの…ちょっと…」
「ここのところ不節制がすぎるんじゃないかなー…なんてー…」
「っ!?あ、あたいが自己管理できてないっての!?」
つい声を荒げてしまった、武道家にも自覚は有るのだ。
しかし、どうしようもなかった。
なぜか、食べても食べても空腹が満たされないのである。
「だって、あなた最近おかしいじゃない!食費が一気に倍になるなんて異常だよ!」
「そうですよ。最初は厳しい戦いでお腹がすいているのかと思いましたけれど…」
「明らかに、動きが悪くなってるもんねー」
一斉に仲間たちが武道家をたしなめる。
しかし、原因が分からない以上、本人にもどうしようもないのだ。
不安が彼女を一層苛立たせ、ここ数日の彼女は精神不安定に陥っていた。
「に、2倍食べたなら2倍動けばいいんだよ!怒鳴ってる暇があったら早く戦いに行こうよッ!」
あまりにも無理のある主張に、場の空気が白けて行く。
とはいえ、彼女のこれまでの貢献を知る勇者たちは、武道家を強く咎め立てする気にはなれなかった。
「そうだね…わかったよ。」
「勇者様!でも…」
「いいんだ。確かにそうした方が建設的かもしれない。」
勇者の一声でその場は収まり、再び非効率な狩りが始まる。
何かが狂い始めていた。
・三章
出立の予定を2週間過ぎた頃、とうとう致命的な破局が訪れた。
勇者の堪忍袋の緒が切れたのである。
「ちょっと!いい加減にしなさいよ、このデブ!」
「んあぁ?」
今日も今日とて、一人で10人前の食事をとる武道家。
構えも取れないほどブヨブヨに膨れ上がった体を揺すり、のたのた勇者に詰め寄る姿に、もはやかつての凛々しさなど微塵も残っていない。
「ちょ、ちょっと勇者さまー…」
「はぁ、ふぅぅ…い、今…あたいのこと…な、なんて…」
「デブっていったのよ!このデブ!」
あわてて魔法使いが取り成そうとするが、一度噴出した言葉は止まらなかった。
長らく我慢し続けてきた鬱憤もあるのだろう、勇者の口撃には容赦が無い。
「何が2倍動けば良いよ!?黙って見てればバクバクムシャムシャ無駄飯ばっかり食べて!全然働いてないじゃない!」
「く、この…!」
鼻白んで拳を振り上げる武道家。
しかし、その動きは悲しいほど遅く、後ろに回った僧侶に簡単に抑え込まれてしまう。
「落ち着いて!勇者様の言う事にも一理あります!最近戦闘の度に私の魔法力が空になっている事はご存知でしょう?ホイミを使う頻度が跳ね上がっているんです!」
「そ、それは…あんたがヘボなだけだよ!あたいのせいじゃない!」
「な…私が悪いって言うんですかッ!?」
「あんたのせいに決まってるでしょデブ!いつまでも調子に乗ってるんじゃないわよ!」
「う、うるさいうるさい!誰のおかげでここまでこれたと思ってるのさ!?」
誰も負い目に感じていた事が、よりによって最も口にするべきではない本人の口から発せられる。
これが止めだった。
「なによそれ…自分だけで戦ってたつもり?やっぱり、あんた最低!」
「さすがに、その言葉は聞き捨てなりません…!」
「あたしもーあんたのそういう所は良くないと思うよー」
激しい口論を繰り広げながらも、武道家をのぞく三人の心は急激に冷めて行った。
贅肉をブルブルと揺らして喚き散らす彼女のあまりの醜さに、怒りよりも幻滅が先に立ったのである。
「うがああああああッ!なによぉっ!?文句あるなら…か、かかっ…は…はが…」
時間にして数分足らず。
戦闘ならば2ターンにも満たない時間で、武道家は息を切らせ、そのまま倒れた。
あまりの凋落ぶりに、沸騰していたはずの怒りもどこかに消え失せてしまう。
後には、空虚な失望だけが残った。
「…行こう」
翌朝、武道家が目を覚ました時には、仲間たちは置手紙を残して消えていた。
・四章
それからは悲惨の一言だった。
肉団子と化した体では、雑魚の相手すらままならず、無為に傷ついては町に逃げ帰る事を繰り返す。
キメラの翼でアリアハンに帰ろうと思い立った時には、すでに遅かった。
手紙と共に残されていたゴールドは、たったの1日でそっくり食費に化けていたのだ。
「お嬢さん?こんな所で眠っていたら風をひくぜ。」
「…なによ。」
ついに宿代すらなくなり、道端に蹲っていた彼女に、町民であろう青年が声をかけて来た。
砂漠の夜は、分厚い脂肪ごしにもなお厳しい。
肩におかれた手のぬくもりが、今はずいぶん懐かしく思える。
「はっ、あんたも…あたいをバカにしに来たっての?」
絞り出した声は、自分でも驚くほど情けなかった。
しかし、青年はそんな彼女に呆れるでもなく、語りかける。
「ま、こんな土地柄だからね。いろいろ事情の有る奴もいるさ。」
「事情…はは、事情か…」
不思議と、警戒心を抱かせない青年だった。
思い出すのも恥ずかしい話であるのに、彼女は促されるままに、ここ数日の出来事を話してしまう。
突然、食欲が異常に増した事。
自分でも抑えられない、強迫観念のような空腹感。
いつしか心までも荒み、仲間と争って全てを失った夜。
楽しかった仲間との旅が、遥か昔の事のように思えた。
「ふぅん…そんなことがなぁ…」
「うぅ…それで、ね…あたい…あ、あんな事言うつもりじゃ…」
口に出し、思い出すたびに、情けなさに嗚咽が漏れる。
涙で声が詰まるタイミングを見計らったように、青年が手を叩いた。
「よし、事情は分かった。」
「っ…あんたに、あたいの何が…!」
「これからの上手い身の振り方さ。宿代も無いんだろ?じゃ、こっから仕事の話だ。」
「…仕事って?」
「おっと、きれい事は無しだぜ。こんな土地柄だしな。」
二ッと笑って話し始めた内容を信じるなら、なんの事はない、青年は地元のポン引きなのだという。
提示された条件は衣食住の保証、求められた対価は彼女の体だ。
「あ、あたいに体売れって言うのかい!?」
「おうともさ。その体なら良い値がつくぜ。ほら、あのおっさんの目を見てみろよ。」
「目って…ひぇ!?」
うつむいている時には気づかなかったが、道行く男たちの誰もが、彼女にギラついた視線を送っている。
過酷な砂漠と言う環境だからだろう。
この地に生きる生き物にとっては、ふくよかさこそが至高のセックスアピールなのである。
もう戦えない、重荷でしかないはずの体に思いもよらなかった価値を見出され、彼女は戸惑った。
「ふ、ふふ…」
しかし、それ以上に嬉しかった。
見限られ、捨てられた女にとって、自らの価値を認められることほどの喜びはない。
月明かりと物欲しげな視線に照らされて、武道家の顔が艶然と輝いた。
「あはははははっ!面白い!その話乗ってやろうじゃん!」
「お、威勢がいいねぇ!よしきた、善は急げだ。」
まるで子供がはしゃぐように、青年と武道家は連れ立って駆けだした。
青年の放ったキメラの翼が燃え上がり、二人をダーマ神殿に運ぶ。
その晩、この世から一人の武道家が消え去った。
・五章
「はぁ…はぁ…はひぃん…」
色布で覆われたランプが、粗末な部屋を淡く照らす。
決して広くはない部屋の中央で、巨大な白い塊がくねくねと揺れていた。
「へへ…見事なもんだぜ。」
「えへへ、ありがとうございますぅ。」
肉塊の正体は女だ、それも飛びきり肥えている。
肌色の梨とでも表現するべきだろう、丸々と太った巨体が、薄暗い部屋の中に浮かび上がっている。
女は金環をはめた両手を後頭部で組み、性器を見せびらかすかのように、ガニ股で腰を揺すっていた。
「なあ、もっとこっちに来てくれよ…」
「はぁい、お客様ぁ」
どこか称賛さえ感じられる要求に、女は甘ったるい声で答えた。
媚びる事に慣れきった、娼婦の声だ。
男の股間に這いつくばり、ただでさえ巨大な乳房に肉をかき集める。
色街でも一二を争う彼女の商売道具は、客の男に対して予定通りの効果を及ぼした。
「うふ、あたいの体、いかがですか?」
「おおおおおおッ」
肉に包んだ男の分身に口づけ、そのまま乳房を上下にすり合わせ始める。
絶対的に胸のボリュームが足りない細身の女では不可能な芸当だ。
かつて、みずからの肉体を武器とした感覚を取り戻した気がして、彼女は知らずほほ笑んだ。
「ぴちゃ…んむ…ぷぁ、はい、ここまでですぅ」
僅かの間、部屋に荒い息遣いと水の滴るような音が響き、そして唐突に止んだ。
「お、おい!待っ…」
「あん、ダメですよぅお客様。ちゃんと、あたいの中に来るまで我慢してくださいな。」
脂汗を浮かべながら、女の体が起き上がる。
男の方も現金なもので、再び目の前にそこが現れると、あっさり視線をくぎ付けにされてしまった。
いったい何人と寝ればこうなるのか、体同様にむっちりと肉付きの良い陰唇から、ドス黒いヒダがはみ出している。
湿り気を帯び、綻んだそれを、男の指がなぞった。
「(あ、そろそろ)」
男の目つきでわかる。
100や200では済まない経験から、女にはこの後の流れが手に取るように予想できた。
「た、た、た、たまらねぇっ!」
まったく予想通りのタイミングで、女の体が押し倒される。
寝具の上に組み敷かれ、高々と抱えあげられた両足の付け根に、男の体が繰り返し叩きつけられた。
倦み飽きるほど慣れきった展開。
にもかかわらず、女は客の男以上に交わりを楽しみ、何度も絶頂を貪った。
・六章
「よう、調子はどうだい?」
「きゃっ、御主人様ぁ、お洋服着てる時に入ってきちゃだめ!」
後始末を終えて一服していた女が慌てて服を脱ぎ捨てる。
場違いに軽い調子で部屋を訪れたのは、いつか武道家に声をかけたあの青年だった。
服と言っても、着ていないのと大差ない、ハムに巻かれたタコ糸も同然の布切れだが、この予期せぬ来訪者を迎えるにはふさわしくないらしい。
「細かい事気にすんなよ、俺たちの中だろ。」
「やだぁ…あたい、ご主人様の前では、いつでも抱ける女でいたいんですよぅ…」
あの夜、この青年に連れられて、武道家はダーマ神殿を訪れた。
通常は入る事の出来ない地下深くで行われていたのは、決して表沙汰になる事の無い非合法の転職である。
一度関われば、もう二度と堅気には戻れない。
闇の契約に署名して彼女は新たな職業…娼婦として生きる道を選んだ。
「だって、あたい御主人様の雌奴隷ですもん!」
得意満面に、かつて武道家だった女はポーズを決めた。
胸を張り、カボチャのような乳房を突きだす。
両腕の間に、今や誇りと呼べるまでに愛着の湧いた脂を挟み、命令一つで開けるよう、陰部に指をかけた。
青年が仕込んだ、全てを差し出す絶対服従のポーズである。
「よし、いいぞ。開いてみな。」
「は、はぁい…御主人様ぁ…おまんこ開かせていただきますぅ…」
女は、待ちきれないと言わんばかりに目いっぱい入口を広げた。
はみ出たヒダと同様、奥の奥まで真っ黒に染まった膣が無防備に晒される。
湯気を立てて愛撫をねだるそこに、青年の指が突きこまれ、定期の検分が始まった。
「あぅっ…あぅぅ~…気持ちいぃよぉ…」
「クク…大分レベルが上がってきたな。」
腹の中まで肉付きが良い、期待以上の仕上がりに青年がほくそ笑む。
歓喜に体を仰け反らせた女からは、邪悪に笑う青年の表情は見えなかった。
勇者パーティーの分断には予定通り成功、しかも、この展開は期待以上だ。
罠にかけた相手がこうまで成長し、しかも自分に懐いているとなれば、欲も出ようと言うものである。
「なあ、実は折り入って頼みがあるんだ。」
「た、頼み?あぁ、ありがとうございます!あたいを頼って下さって嬉しいです!」
先程までの媚びるような口調ではない。
パッと花が咲いたように、まん丸の顔に笑顔が浮かぶ。
この青年の役に立てる事が、打算抜きで嬉しいのだ。
彼女の堕落ぶりを満足げに確認しながら、青年はなおも言葉を続けた。
「なぁに、そう難しい事じゃないさ。」
いつの間にか握っていた杖を一振りすると、粗末なドアがピタリと固定され、硬く閉ざされた。
そして、期待に目を輝かせる女の前で、青年の背がみるみる縮み、その顔に皺が現れる。
「え…あ…あれ…?」
「キヒヒヒヒ…怖がる事はない。少しばかり仕事を頼みたいのじゃよ。勇者どもを叩きのめす悪魔を産み落とすと言う大仕事をなぁ!」
数秒後、部屋中に狂ったような女の叫び声が響き渡った。
張り巡らされたマホトーンの術によって表に漏れる事はなかったものの、仮に誰かがこの声を聞いていたとしても、安女郎がよくやる大げさな演技として片づけられていたであろう。
「ぐあああああーッ、ご、御主人様あああぁ!いい!いいのォ―――ッ!!!」
目の前の人間が突然魔物に変じたと言うのに、彼女の声色には一片の拒絶もなかった。
それどころか、想い人の新たな一面を発見したとばかりに大喜びで体を開き、誘い込む。
「クヒッ!キヒヒヒヒヒ、そうかそうか!そんなにええかこの淫売めが!」
「はぃぃ、イイです!最高ですぅ!一生ついていきます!」
ヒィヒィとよがりながら、女は自ら丸太のような足を掴み、覆いかぶさる魔物に向かって腰を押しつけた。
自身の最奥、子宮を捧げるために。
「さぁて、そろそろ…」
「…ぁあああああ!し、死ぬまでお仕えしますぅッ!」
「くれてやろうかの!」
ビュクンと、彼女の体内で肉棒が跳ねた。
「ぶヒ…ッ!?」
ピクピクと、弛んだ腹が痙攣を起こした。
客の男に出される時とは明らかに違う感覚、今まさに取り返しのつかない事が起こったと本能が告げる。
なおも胎内を責め立てる鬼面道士を愛しげに抱きしめながら、彼女は自分の体が完全に、この小さな主に征服された事を悟った。
・エピローグ
今日もアッサラームの裏通りで、武道家だった女が体を売る。
薄絹一枚を身にまとい、とろける様な肥満体を堂々と誇示している。
強いて、これまでと違う点を挙げるなら、彼女が声をかける相手だろう。
「ねぇねぇ、お兄さん。私と一発ヤっていかない?」
「ぐが?なんじゃい姉ちゃん、客引きか?」
彼女が腕をとり、惜しげもなく体をこすりつけている相手は魔物である。
彼女の客だけではない、最後の希望であった勇者が潰えた今、アッサラームを含む世界中の町を、魔物が闊歩しているのだ。
「ふむふむ…おう、ええ体しとるのう!」
「あん、どうかしら…?」
ムチムチとした体を、魔物の無遠慮な腕が鷲掴む。
幸せ太りと言ったところか。
鬼面道士の仔を産まされてて以来、彼女の体はますます太りつつも、一向に張りを失わなかった。
体の各所が魔物にちょうど良いサイズまで肥育された姿は、マニア向けの淫魔といった風情だ。
「おし、気に入った!いっちょワシが相手したるわ!」
「えへへ、やったね。一名様ご案内ぁい!」
どうやら、魔物の手にすら余るサイズの巨尻がお眼鏡にかなったらしい。
嬉々として魔物の手をとり、部屋に連れ込む姿は、心底楽しそうに見える。
実際、彼女は娼婦を天職とすら思っていた。
勇者を打ち取った英雄の母である彼女は、本来ならば最下層の娼婦奴隷などとっくに卒業して然るべき立場にある。
にもかかわらず、本人たっての希望で、世界征服後も変わらず客をとり続けているのだから、まさに筋金入りである。
「あーずるいー」
そんな彼女に、隣の部屋の娼婦がうらやましげな視線を向ける。
とんがり帽子だけを身に付けた全裸で道行く魔物を誘っているが、どうにも食い付がも悪いらしい。
元が派手好きなのか、太り過ぎて着られる服が無くなった今でも、局部をピアスで飾り、チリチリと鳴らして遊んでいる。
「い、いかがですか?どなたか…私と添い寝して下さる方…」
そのさらに隣は、我関せずと言った態度でマイペースに媚を売っている。
他の二人に比べれば大人しい、ふっくらとした体で、控えめに声をかけるものの、あちこちに施された下品な刺青が、その初心な素振りをことごとく台無しにしていた。
「あー、分かった。なんでお客の入りが悪いのか。」
「…そう言う事ですか。」
人通りが少ない理由は、単純明快だった。
裏通りまで聞こえてくる大通りの喧騒、あちらでは、勇者の公開処刑がクライマックスを迎えているのだ。
「ぶふ、はぐっ…んっ、もう…もう食べさせないで…誰か止めてぇ…」
タネを明かせば下らない。
微弱なメダパニの呪文で満腹中枢を麻痺させるだけの、ごく単純な手品である。
あとは、暴走した食欲に食べ物をぶら下げてやるだけ。
たったこれだけの単純な手口で、武道家を皮切りに、魔法使いと僧侶も無力化され、闇に落とされてきた。
そして、一人残された勇者もまた、彼女達の後を追わされようとしている。
「うぐ、むぐぐ…醜く…デ、デブになりたくないよぉぉ…」
「へへへ、勇者なんて言うからどんな生意気女かと思ったらよ…」
「こりゃ解禁が楽しみだぜぇ」
操られるように食べ物をかき集めながら、女は羞恥にむせび泣く。
あえて奪われずに残っている衣服が動きに合わせてビリビリ破れ、見るも無残な5段腹が衆目の前にこぼれ落ちた。
「ぎゃはははは!こりゃすげぇや、ブタでもこうはならんぜ!」
「(あぁ…みんな私を見てる…)」
かつて勇者と呼ばれたそれは、自分でも気づかない内に、崩れた体を火照らせ始めていた。
(完)