415氏その4
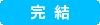

#ドラゴンクエスト5,ドラクエ5,Dragon Quest Ⅴ,DQⅤ
・プロローグ
グランバニア…先王パパスの出奔に始まり、何かと王族関係のトラブルには事欠かない国である。
そして、一時世界を席巻した光の教団と、魔王がミルなんとかさんが倒れた今でも、その体質は健在らしい。
苦い顔の家臣達を尻目に、それは悠然と廊下を練り歩いていた。
「はぁん…あふぁぁ…」
遠目に見れば仲睦まじい男女、寄って見れば湿気の塊。
しかし、実状を知っている人間から見れば、それらを形容する言葉は一つしか存在しない。
「あぁぁ…レックス…レックスぅ…」
「なんだい、タバサ?」
すなわち、バカップル。
それも、このグランバニアの次期国家元首と来ては、家臣の表情も暗くなろうと言う物である。
寄り添って歩く男女の正体は、共にこの国唯一の王子レックスと、王女タバサだ。
「わ…わたし…もうダメです…」
「何がダメなんだい?教えて欲しいな。」
切なげに眉根を寄せてむずがるタバサ。
滝のような汗と、湿った服に浮き出た二つのポッチが、この光景を更に異様たらしめていた。
おまけに、犬のような首輪まで付けられ、赤いリードを引かれている。
「一体、どうした?ハッキリ言ってくれないと分からないな。」
「うぅぅ…!い、意地悪しないでぇ…」
対するレックスは嗜虐的な笑みを浮かべつつも、決して彼女の体に触れようとはせず、手に握った紐を介して、タバサの動きだけを支配している。
偶然通りかかったリュカ王は顔を覆って天を仰いだ。
「ひぅ…だ、だから…その…もう我慢できないからぁ…あうぅ…だ、抱いて…ください…」
泣き出しそうな、それでいて恍惚とした声を漏らし、タバサが服の裾をたくしあげる。
そこで初めて、レックスの手が彼女に伸び、彼女のスカートを押さえた。
ちなみに衆人環視の真っただ中である。
「よく言えました。でもダメだよ。」
「そんなぁ!?し、シたいのっ!今すぐレックスとシたいのぉっ!」
泣き喚きながら性交をねだる娘の姿に、とうとうリュカ王が膝から崩れ落ちる。
グランバニアではよくある事なので、家臣達は気にしなかった。
「タバサ。」
蕩け切った甘え声を切り裂くように冷たい声が響く。
ビクリと体を震わせるタバサ。
グランバ二アではよくあることなので、家臣達はそそくさと仕事に戻った。
「それは何だ?」
「えっ…?」
「そこに開いてる穴は誰の物だ?」
「は、はい…これはレックスの…あっ…」
今度こそ涙を流しながら、タバサは顔を上げた。
まるで血に媚薬でも混じっているのではないかと言うような淫靡な表情だ。
しつこいようだが、グランバ二アではよくあることなので、家臣達は無視して通り過ぎた。
「お兄ちゃんの…モノです…」
「だったら、それは僕以外に見せちゃだめだろう?」
咎めるように、レックスの指がなめらかな二の腕に食い込むと、分厚い脂身が歓喜に震えた。
体重にして100kgは下らぬであろう肥満体は、強国の王女たる彼女がいまだに嫁ぎ先を決められずにいる大きな原因だ。
「ごめんなさい。」
「分かればいい。我慢できるね?」
「うん…辛いけど、ベッドまで我慢する…」
唇を食いしばり、一大決心のように呟く。
レックスは満足げに頷きながら、彼女の腰に手を回した。
「よしよし、タバサはいい子だね…御褒美だよ。」
「ひぐっ…!?」
そして、そのまま巨大な尻タブを突き抜けて、下着を着けていない秘所を抉った。
暴発寸前の性感を必死に抑え込んだ矢先の不意打ちに、たちまちタバサの情欲が沸騰する。
「うあぁああぁぁああーーーッ!お゛っ、おにいいぃぃぢゃああああああん!!!!」
ヘコヘコと腰を揺する妹を抱き上げて、レックスは手近な部屋の扉を蹴り開けた。
いわゆるお姫様だっこの体制で扉の向こうに消える彼の顔はこれ以上ないほどに得意満面だったが、グランバ二アではよくあることなので、家臣達はよくあんなの持てるなぁとしか思わなかった。
・第一章
幼少期の体験は人格形成に大きな影響を与えるという。
では、本来親と共にあるべき時間をまるごと奪われ、お互いをたった一人の肉親として過ごした兄妹はどうなるのか?
「妹が可愛すぎて生きるのが辛い。」
「や、やだぁ…何言ってるの…?」
王族用の豪華な寝室で見つめ合う男女が一組。
脳の湧いたセリフを口走りながら細い紐を手繰るのは、レックス王子。
その先の首輪ごと引き倒されて熱い吐息をもらすのは、タバサ王女。
困ったことに二人は血を分けた実の兄妹である。
「今日もタバサは一段と可愛いなぁ。真っ白で、すべすべして、まるでシルクみたいだよ。」
「はぅ…レ、レックスも…素敵だよぅ…」
さらに困ったことに、デキてんじゃないかと言う市井の下世話な想像は大正解だった。
黙っていれば美男美女、愛らしくたおやかなタバサ王女、すらりと凛々しいレックス王子は共に国民のあこがれの的なのだが、今の二人を見れば百年の恋も冷めるだろう。
なにしろ、タバサは犬用の首輪をはめて床に這いつくばり、レックスに至ってはそんな彼女を見下ろしてデレデレと二ヤけているのだから。
「ねえ、タバサはどうしてそんなに綺麗なんだい?」
クイ、と頬に添えた手を持ち上げる。
鷲掴みにされた顎が反りあがると、濡れた瞳が媚びるように揺れた。
「き、きれッ…恥ずかしい事言わないで…」
「ごまかすなよ。そんなに綺麗になってどうする?あちこちで男を誘惑してるのか?」
全く意味の無い質問。
気分を盛り上げるための準備のようなものなのだ。
レックスの膝に引き寄せられながら、タバサは婉然とほほ笑み、何十度と繰り返してきた答えを口にした。
「それは…お兄ちゃんのため…」
「僕のため?」
「そうだよ…お兄ちゃんを誘惑したくて…わたし、すごく頑張ったんだよ…」
夢見るような声で答えるタバサ。
幼い勇気を振り絞った、決して実らぬはずの求愛の結果が、何をどう間違えたのかコレである。
親の顔も知らぬ子供達はたちまち互いに夢中になり、齢16を迎えた今となっては、恋人と経験するべき事のおおよそ全てを二人で分かち合っていた。
「なるほどね、僕はまんまとタバサの毒牙にかかったわけだ。」
「えぇ、わたしのせいなの?」
「タバサのせいさ。その証拠に、ほら。」
レックスは紐を引く手を緩め、足を開いた。
戒めから解放されたタバサは、さらに顔を寄せ、兄の股間に顔をうずめる。
他ならぬ彼女の愛液に焼けた肉棒が、吐息を感じてむくむくと鎌首をもたげた。
「一緒に居るだけでこんなになるんだ。動きづらくて仕方ないよ。責任とってほしいね。」
「もう、しょうがないなぁ。」
他ならぬ彼女自身の愛液で黒ずんだ先端を咥え、喉奥に飲み込んでいくタバサ。
なぜか妙に勝ち誇ったような顔だ。
やがて、背を撫でていた手が振り上がり、突き出された下半身に振り下ろされる。
太鼓のように鳴り響く尻の下では、すでに水たまりが形成されていた。
・第二章
「え、縁談ッ!?」
「ひっく…う…うえぇぇ…ど、どうしよぉぉ…」
国民の間ではもはや公然の秘密と化している二人の仲だが、事が事である。
いまだ、子供たちと過ごせなかった時間の方が長いグランバニア王夫婦は、彼らの爛れた関係に気付かずにいた。
そんな折に持ちあがったのが、タバサ王女の遠国ラインハットへの輿入れ話だ。
「冗談じゃない!僕のタバサに色目使ってやがるのは一体どこの馬の骨だ!?」
「えぐ…うぅ…ラインハットの…」
「コリンズか!?あ、あのクソガキッ!国ごと滅ぼしてやろうか!?」
とはいえ、今回の件は父親同士が酒の席でかわした口約束である。
ぶっちゃけ言いだした当人すら本気にしてはいないのだが、道ならぬ恋に身を焦がす二人は気が気でない。
口角泡を飛ばすレックスの心中では、半ば物騒な決意が固まりつつあった。
「うぇ…やだ!やだぁ!わたしは、レックスと…ひっく…」
「大丈夫だ、タバサ。」
泣きじゃくる妹をひしと抱きしめながら、レックスが言い放つ。
決然と放たれた力強い言葉に、タバサもつられて顔を上げた。
その頃リュカ王は、「まあ、ゆっくり話す機会でも設けてみるか」などと考えていた。
「僕が何とかするよ…お前はだれにも渡さない!」
「ぐす…本当?」
「約束する!だからタバサ、笑っておくれ。お前は僕が守るから。」
悲壮感漂う表情も手伝い、そこだけ切り取れば、まるで劇のワンシーンである。
すっかり悲劇のヒロインと化したタバサは、されるがままに身をゆだね、うっとりと眼を閉じた。
そこから先は、大方の予想通り。
運悪く近くに居た人間が数名、げんなりした顔で耳をふさいだ他は、グランバニアは今日も平和だった。
・第三章
さて、大見栄を切ったものの、王子にとっても寝耳に水である。
策などあるはずも無く、早々に手詰まりとなった挙句、よりによって父直属のモンスター近衛隊に相談する始末。
恋は盲目とはよく言った物だ。
彼らの反応は一様に
「しらんがな(´・ω・`)」
「リア充爆発しろ。」
「ざまぁwww」
と、大顰蹙状態だった。
「そう言わずに頼む!この通りだ!皆の知恵を貸してくれ!」
恥も外聞も無く、手をついて床に頭を擦りつける王位継承権第一候補。
あまりの勢いに一瞬体が浮き上がる、伝説のジャンピング土下座の構えだ。
親が見たら間違いなく泣く光景だが、残念ながら元野生動物のモンスター連中に下座戦法は通じなかった。
「「「惚気話うぜえ…」」」
かつてないほどの団結力を発揮し、まさしく敵を見る目で冷やかに王子を睨みつける魔物達。
もはや万策尽きたか。
レックスの心が焦燥に押しつぶされかかった絶妙のタイミングで、救世主は舞い降りた。
「あら、それならいい手がありますわ。」
「何だって!?教えてくれ、頼む!」
つややかな肌、豊満な肉体、逆行を浴びて歩み出たのは、スライムべホマズンのべホズンだ。
余計な事言いやがってと顔をしかめる仲間達を無視して、萌黄色の巨体がしゃなりと揺れる。
「簡単な事ですわ。あたくしがキングス様と結ばれた時と同じように、姫様の魅力を知る人間が殿下お一人だけになってしまえば良いのです。そうすれば、自動的に姫様は貴方様の物…違いまして?」
「な、なるほど…一理ある!」
いや、その理屈はおかしい!と視線による総突っ込みが入るが、なにしろ衛生班のドンたるべホズンが相手だ。
結局権力かと、誰もが諦め顔で口をつぐむ中、彼女の独壇場は続く。
「殿下に一つ、ヒントを差し上げます。」
ブニョンとゼリー状の体表が盛り上がり、レックスの手に向かって伸びてゆく。
その中から一粒の木の実が現れ、掌に収まった。
「これは…」
「あたくしにできるのはここまで。あとは御自分で何とかなさって下さいまし…どうか、タバサ様をよろしくお願いいたします。」
器用に体をへこませて一礼し、さがるべホズン。
波が引くように持ち場に戻る魔物達を見送りながら、レックスは狐につままれたような表情で掌を見つめていた。
手渡された命の木の実をしばらく眺め、頭をひねる。
「…ッ!そうか!そういうことか!」
数瞬の後、天啓を得たりとばかりに弾んだ声を背に受け、べホズンは静かに頷いた。
・第四章
「タバサ!」
「な、なあに?お兄ちゃん。」
今日も今日とて、妹に夜這いをかけるレックス。
何時になく真剣な面持にドギマギしながら、タバサは顔を上げた。
目の前に差し出された兄の手には、畳んだ薬包紙が握られている。
「これを飲んでくれ。」
「飲むって…これ、お薬?なんの?」
怪訝な顔も無理はない。
夫(※タバサ談)の手ずからとはいえ、得体の知れぬものを口に入れることに抵抗が無い訳がないのだ。
レックスもそこは承知の様で、淀みなく誤魔化しの文句を口にする。
「今はまだ言えない。ただ、僕達がずっと一緒に居るために必要な物とだけ言っておくよ。」
「ず、ずっと!?はうぁ…」
実際何の説明にもなっていないのだが、そのフレーズだけで舞いあがってしまったタバサには、そんな事は些細な問題らしい。
途端に物欲しげな目で兄を見つめ始める。
あまりのチョロさに、やはり自分が守ってやらねばと決意を新たにするレックスだった。
「さあ、こっちにおいで。僕が飲ませてあげるよ。」
「う…うん…わかりました…」
フラフラと、吸い込まれるように擦り寄り、頭を差し出す。
顎を掴まれ、口を開かされると、たちまちタバサの表情がドロリと蕩けた。
支配欲と被支配欲が交差し、倒錯的な情愛が燃え上がる。
「口を開けて…これでお前は僕の…僕だけのモノになるんだよ…」
「はい…タバサは、お兄ちゃんだけのモノです…」
ハァハァと息を荒げ、レックスの兄の足に縋りつく。
膝をかかえ込み、控えめな乳房を押しつけるポーズは、さながら古代の神殿に飾られた彫像のようだ。
首輪を掴まれ、突き出した舌の上にさらさらと粉薬を乗せられる。
鈍い苦みがもたらす被虐の快楽に、タバサは早くも一度目の絶頂を迎えた。
・第五章
投薬開始から半年。
毎日欠かさず服用している薬は、目に見える形でタバサを蝕み始めていた。
「ぶふっ…ね、ねえ…お兄ちゃん…」
「ん?なんだいタバサ?」
もっとも顕著な影響は、ブクブクと全身にまとわりついた脂肪だ。
少しづつ、あくまでも自然に、肥満への道をたどる娘に、両親も遅まきながら心配そうな視線を向けるようになっていた。
しかし、もう手遅れだ。
今や、タバサにあこがれの視線を注いでいた民草の中にさえ、変わり果てた彼女の姿に嫌悪感を示す者が出始めていた。
「最近…はぁ…わたし…ふぅ…」
「おいおい、一体どうしたんだい?」
以前はどうという事も無かった運動量で息切れがおこる。
予想以上の効果に、レックスは自らの勝利を確信していた。
もっとも、その仮想敵は、まさか相手方の兄に恋のライバルと目されている事など知る由も無かったが。
「なんだか…はぁ、おかしいです。不摂生とか…してるわけじゃないのに…ふひっ…」
「うんうん。」
「体は重いし…みんな私を見てるし…ねえ、私どうしちゃったのかなぁ…?」
思い当たる節など一つしかないと言うのに、それでも彼女はレックスを疑おうとはしなかった。
恋は盲目とはよく言った物だ。
素知らぬ顔で通すレックスも、さすがに罪悪感を感じずには居られない。
「…大丈夫だよ、タバサ。周りの奴らなんて気にするな。タバサはこんなに綺麗なんだから。」
「あう…で、でもぉ…」
タバサの訴えを聞きながら、慣れた手つきで服を脱がせてゆく。
あらわになった体は、見事なまでに緩み切っていた。
ウェストの描く曲線はすっかり反転し、ツンと上を向いていた乳房は、重力に耐えられないほど実って垂れ落ちている。
一瞬もう十分ではないかと思いかけたが、この試みに失敗は許されないのだ。
レックスは心を鬼にして、薬包紙を取りだした。
「さあ、タバサ…今日の分だよ。」
「はい…お兄ちゃん…」
従順に弛緩する体を抱き起こし、唇をなぞる。
正体が分からぬよう、粉末状に擦り潰された命の木の長期服用は、怪しまれる事なくタバサを太らせるには最適の手段と言えた。
そう、誰に取られてもおかしくない立場なら、誰も手に入れようと思わない様にしてやればいいのだ。
タバサの魅力は自分一人が知っていればいい。
それが、べホズンの助言を受けてたどり着いた答えだった。
「口を開けて…そう、いい子だ。それじゃ、飲ませるよ?」
「ん…下さい…」
最愛の妹に群がる悪い虫を駆除するべく、レックスは粉末を含み、口づける。
タバサのかすかな不安を吹き飛ばすには十分すぎる誘惑だ。
薬物中毒者のような白痴面でピチャピチャと舌を鳴らすタバサの手首を掴み、そのまま手枷をかけた。
「んぁ…?」
「よし、いい飲みっぷりだ。さすが、僕の自慢の奥さんだよ。」
「ひゅい!?おおおお…奥さん!?」
呆け顔から一転、真っ赤になって顔を伏せるタバサ。
視界には悩みの種である三段腹が映っているはずだが、もうそれどころではないらしい。
目を白黒させる彼女に構わず、両足が全開にされ、足首とベッドが枷で連結されていく。
「さあ、準備ができたよ、タバサ。今日はどうしてほしい?」
「ふぇ?あ、あれ?あれぇっ!?」
気付いた時にはもう遅い。
いつの間にか自由を奪われていた体に戸惑う間もなく、覆いかぶさったレックスが愛撫を始めていた。
何かおかしい、はぐらかされていると感じつつも、急激に昂って行く体の要求に勝てるはずも無く、タバサの思考は急激に溶けて行く。
「今日は…」
「今日は?」
「め、目隠しがいい…です。」
「ふふっ、了解。」
リクエスト通り、レックスは机から愛用の目隠しを取りだし、巻きつけた。
磔になった体を改めて眺めてみると、なるほど確かに酷い有り様だ。
頭からつま先まで、どこを取っても膨れていない所が無い。
べっとりと汗にまみれた体をヒクつかせ、餅のような頬を期待に上気させている。
特にひどいのは、今しがた剝き出しにした股間だ。
「こりゃ酷い。一日中こんなにしてたのか?」
「ふわあぁっ!」
手を添えると、嬌声と共に腫れぼったい柔肉がグチュリと鳴った。
粘膜の感触はまだ無い。
タバサのそこが、軽い収縮だけで音を立てるほど発情しきっているのだ。
「こんなんじゃ前戯のし甲斐が無いなあ。さっさと入れちゃおうか?」
「やぁ、指もして欲しいです…」
当然、そんな乱暴な真似はしない。
半年前と比べると幾分厚くなった土手をいじり回しながら、レックスは、こんな所も太るのかと妙な感慨に襲われた。
いよいよ陰唇の動きが狂おしくなってきた頃合いを見計らい、少しづつ指先を沈めて行く。
「きゃうあああああ!?」
「え、ちょ、早ッ!」
予想外のタイミングだ。
入口をこじ開けただけで、タバサはあっさり気をやってしまった。
拘束された手足を支点に背を逸らし、唯一稼働する腰ががくがくと跳ね回る。
「あうっ!ああああああっ!やっ!あはぁぁぁぁッ!ひゃはああああああっ!」
跳ねるたびに指が食い込み、新たな刺激でさらに身をよじり、その拍子に異なる角度で膣壁が擦られる、永久機関のようなサイクルに巻き込まれて、タバサは悶え狂った。
一方、身の振り方に困るのはレックスである。
第一関節でこんな調子なのに、ここから指を動かしても大丈夫だろうか。
「まあ、普通に責めるんだけどね。」
「あうううううーーーッ!ああーーーッ!ああーーーーーーーッ!!!」
疲れ果てて動きが鈍った隙を突き、レックスは指を突きいれた。
人差し指を付け根まで、壁を感じるまで挿入し、少し引き抜いて臍側に方向転換、掻く。
1.2秒の早技の効き目は、グルリと裏返ったタバサの瞳が物語っている。
「ヒッ!?」
太った分だけ感覚が合わないかもしれないな、などと言う心配はどこ吹く風で、ぐったりしていたタバサの体が再び踊り始める。
暴れるたびにフルフルと変形する贅肉に、レックスもまた、言いようのない興奮を覚えていた。
「タバサ…そろそろ入るよ!」
「まぁ…ま…まだぁ…」
「わ、熱い!そうか、タバサは拘束好きなのか!今度から参考にするよ!」
待てと言われて止まれるほどの余裕はもうなかった。
言葉では平静を装いつつ、震える手でガチガチの肉棒を取りだす。
一刻も早く潜り込みたい衝動を抑え、かろうじて痛がらせないように挿入した時点で、レックスの理性も限界を迎えた。
「くは…ごめん、止まれない…かも…」
「ぁ…ぁ…?」
半ば吹き飛んだ意識のなか、タバサは回された手が、背中の皮を掴むのを感じた。
本能的に危険を察知し、口を押さえようとするが、両手は視界のはるか上でベッドの背に繋がれている。
慌てて手を引く間もなく、股間から打ちこまれた衝撃が脳内を荒れ狂った。
「あがががあああああぁぁひいいいいいいいいぃぃぃぃぃ!?!?」
「ああ、タバサ!好きだよ!愛してるッ!大好きだ!」
筋肉質の体が恐ろしい勢いで上下する。
跳ね上がる度に夥しい量の愛液がベッドに溢れ、叩きつける度に脂肪のクッションがブチュンと音を立てて波打った。
「ぴぎゃッ!?ひはッ…ひゅー、ひゅー…」
「なんて柔らかいんだ…さ、最高だよ!ああ僕のタバサぁッ!」
「ぎぁっ!?あっぎゃぁぁあぁあああーーーーーーーッ!!!!!!」
いよいよ気違いじみた声を張り上げ、二匹の獣は時を忘れてのたうちまわった。
その激しさたるや、百戦錬磨のグランバニア国民をも震えあがらせたと言うのだから相当な物である。
そのころリュカ王は「タバサには来月の飲みにでも顔を出させるかな」とか考えていた。
・第六章
「やあ、リュカ!久しぶりだなぁ!」
「ヘンリー!会いたかったよ!」
ガッシリと握手する二人の関係は、とても一国の王同士とは思えないほど気安い物だった。
本来、政治的に責任ある立場の人間が、このようにプライベートで親しくし過ぎると言うのは好ましくないのだが、そこはグランバニアである。
よくある事なので、今さら目くじらを立てる家臣もいない。
ともに市井出身の王妃たちも、茶飲み友達とのおしゃべりに飢えているらしく、やれリュカヘンだのヘンリュカだのと世間話に花を咲かせていた。
「そうそう、今回はな。ほら、約束通り息子をつれて来たぜ。」
「お久しぶりです。」
やや固さが見受けられるものの、ピシリと礼にのっとった挨拶だ。
前に有った時は、ヘンリーの生き映しかと思うほどのヤンチャ坊主だったはずだが。
「うん、息災で何よりだ。」
「は、はい…痛み入ります陛下。」
「ははは、おじさんでいいよ!最後に会ったのは2年前だったかな?いや、見違えたよ。」
なおも緊張した様子で礼を済ませるコリンズ王子を、リュカは感慨深げに見つめた。
背後で、リュカコリ…そういうのもあるのか!などと聞えたが、全力で無視した。
「で、だ。お前さんの子供達は今日は来るのかい?うちの息子の…なんだ、嫁さん候補は!」
恥ずかしまぎれに笑いながら、ヘンリーが尋ねる。
酒の席の戯言とはいえ、一応は公人同士の約束だ、触れないわけにもいくまい。
あわよくば挨拶がてらの冗談にかこつけて有耶無耶にしてしまおうと目論んでいたのだが、答えるリュカの口元はなぜか引きつっている。
「ああ、うん。その事なんだが…」
冷や汗を流しながらしどろもどろになるリュカ。
訝しんだヘンリーが口を開こうとした瞬間、狙ったようなタイミングで足音が聞えた。
しかし、様子がおかしい。
ドスンドスンと地響きのような、これではまるでトロルの足音ではないか。
「ふぅ、ふぅ…お、遅くなりました。お久しぶりです、ヘンリーおじさま、コリンズ王子。」
「「誰!?」」
奇しくも同時に、全く同じ疑問が発せられた。
それも無理はない。
ラインハット親子の記憶によれば、タバサ王女は、小柄で華奢な少女だったはずだ。
よもや身長168㎝、体重105㎏の怪物が現れようなどとは、全く想定していなかった。
「あら、忘れちゃいました?リュカの娘のタバサです。」
「え、ああ…うん。お、覚えてるよ?その、タバサ…ちゃん?」
「くぁwせdrftgyふじこlp!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?」
コリンズは混乱している。
数ヶ月の肥育を経たタバサ王女の姿は、淡い幻想を打ち砕くには十分すぎる破壊力を持っていたらしい。
哀れ、少年の初恋は、変態兄妹の前に潰え去った。
「その…なんだ…見違えたよ…うん。女の子は変わるって言うし…」
「pぉきじゅhygtfrですぁq・・・・・・・・・・・・・・・・・・」
「なんか、ごめん…うん。どうしてこうなった。」
必死に言葉を探しているのだろう、途切れ途切れに言葉を発するヘンリー王。
コリンズ王子は依然として真っ白にフリーズしている。
意気消沈した当事者の前で縁談など切り出せるはずも無く、この話はこれきり立ち消えになったのだった。
・エピローグ
「あのときは驚きました。まさかお兄ちゃんのお薬が原因だったなんて。」
「えっ!?気付いてなかったの!?」
ひとしきり盛り上がった後のピロートークは、決まってこの話だ。
よくよく考えれば、太る薬などという危険物を無断で投与されていたタバサは怒り狂ってもおかしくはない。
最悪、極大呪文フルコースも覚悟して白状したレックスを待っていたお咎めは、以外にも「これからはベッドの外でもサービスする事」という条件だけだった。
そのサービスとやらが、主に周囲への精神的苦痛が甚大な公開羞恥プレイと言うのだから、理不尽の極みである。
「気付く訳ないでしょう!わたしがお兄ちゃんの事疑うはずないんだからっ!」
「うぐっ…す、すいませんでした…」
さも当然と言わんばかりに主張するタバサに、レックスはただ平伏することしかできなかった。
その反応に気をよくして、タバサはわざとらしくため息をつく。
「あーあ、お兄ちゃんのせいで体が重い。」
「ぐぎぎ…」
「これじゃロクに動く事も出来ないですねー」
「ど、どうしろと!?」
「別にぃ?ただぁ、せっかくエッチしてるのに、私だけ気持ちよく動けないって不公平じゃないかなーって?」
(チラッと擬音がつきそうな態度で兄を見やりながら、タバサは大袈裟に手足を広げた。
つまりは、満足させろという事だ。
ぶっちゃけ、第二ラウンド開始の合図みたいなものである。
「オーケー、分かったよ。そんなに言うなら誠心誠意ご奉仕しますよ。覚悟は良いな?」
言うが早いか、目にもとまらぬスピードでレックスの腕が閃くと、見る見るうちに、贅肉のクッションに縄が食い込んで行く。
開いた両足は閉じられないように、掲げた両手は下ろせないように、一体どこで練習したのかと問い詰めたくなる手際で、タバサの自由はまたたく間に奪われてしまった。
「あれ?」
ようやく口を開いた時には、もう結び目が引き絞られていた。
クロスした縄の間からはみ出した腹をグニャリと掴まれると、たちまちタバサの肌が紅潮し、瞳が潤み始める。
「ほらほら、僕がつけてやった贅肉は気持ちいいだろう?」
「ふわ…あぁん…」
「今日はどうしてほしい?鞭?それとも張り型?」
「おほぉ…き、今日はぁ…」
翌日、タバサ王女はなぜが長袖襟高の服を着込み、しきりに尻を気にしながら、妙に内股で歩いていたが、グランバニアではよくあることなので、リュカ王以外は誰も気にしなかった。