415氏その5
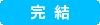

#ドラゴンクエスト6,ドラクエ6,Dragon Quest Ⅵ,DQⅥ
・プロローグ
石造りの部屋に、人影が二つ。
一つは巨大な金色の魔物、もう一つはすらりとした修道服の女性だ。
金色の魔物は恭しく女性の手を取ると、そっと口づけた。
「アクバー、一体何を企んでいるのですか…?」
すらりとした女性、シスターアンナは、拍子抜けしたような顔で魔物に問いかける。
ここは牢獄の町。
大魔王デスタムーアの領地である狭間の世界に存在する、町とは名ばかりの収容所だ。
ここでは、絶望の町と欲望の町の誘惑に耐えた強者たちの心を折るべく、日夜人々が虐げられている。
「言っただろう?お前を俺の妻にすると。ならば親愛の情を示すのは当然ではないか。」
彼女と向かい合う金色の魔物が、ここの支配者だ。
名をアクバー。
人間の希望を打ち砕くことを使命とする彼にとって、心を鼓舞する神秘の声を持つシスターアンナは邪魔以外の何者でもないはず。
だからこそ、彼女を貶しめるための悪趣味な異種間結婚が企画され、今日はその下準備として悪魔の魂を植えつけると聞かされていたのだが、どうにも様子がおかしい。
「…ふむ」
「何がおかしいの!?私を辱めるのでは無かったのですか!?」
世にも恐ろしい悪鬼の相貌が、信じがたい事に穏やかに綻んでいた。
言葉にできぬほどの責め苦を覚悟していただけに、このような態度は全くの予想外だ。
不安を表情に出すまいと、シスターアンナは密かに持ち込んだ真鍮の十字架を握りしめた。
「辱める?なにを言っているのだ。愛する妻に恥をかかせて喜ぶ夫など居るものか。」
「なッ!?」
ドクンと心臓が跳ね上がった。
神に仕える身の彼女は、異性から愛を囁かれた経験など無に等しい。
降って湧いた新鮮な感覚に、白い頬が見る見るうちに赤みを帯びて行く。
「あ、愛ですって!?冗談も大概になさい!」
「冗談ではないさ。俺はお前のそういう毅然とした所が大好きだ。」
巨大な手が、いたわるように華奢な肩を包み込んだ。
接点に感じる異常に高い体温にも、不思議と嫌悪感を覚えない。
それどころか、伝わった熱が安らぎに変わり、血流に乗って広がって行くようにさえ感じられる。
「なにを馬鹿なッ!あなた達は人間を憎んでいるのでは無かったのですか!?」
「もちろん、人間など好かんさ。だが、お前だけは特別だ。」
思考が追い付かない。
原因不明の激しい動悸に、シスターアンナはひたすらに戸惑った。
魔物に、それも憎むべき大敵に言い寄られていると言う理解不能の状況が、アンナの冷静さを奪っていく。
「時にアンナよ、今度は君の体に触れたいのだが…構わんか?」
「え………」
あくまでも静かに、アクバーの巨体が迫って来る。
常ならば跳ね除けていたであろうそれを、彼女はただ、眼を白黒させて見つめていた。
・一章
「はぁ…」
人間達が閉じ込められている居住区の唯一の広場、禍々しいギロチンを戴く処刑台の前に、シスターアンナは座り込んでいた。
溜息とともに、口づけを受けた左手の甲を眺める。
理解不能の感情が鮮明に思い出され、彼女は知らず赤面した。
「なぜ、こんな気持ちになるのでしょう…?」
「…ター!シスターアンナ!一体どうなすったんで?」
ハッと顔を上げると、マスクを被った荒くれ男が心配そうに覗き込んでいた。
この町に居る誰もが、一度はシスターアンナの神秘の声に救われている。
傷ついた恩人を慰めようと、彼なりに必死なのだ。
「い、いえ!何でもありませんわ…」
「なんてこった、シスター!やっぱりアクバーの野郎に…!」
痛ましい様子で荒くれ男が目を伏せた。
シスターアンナの憂鬱は、アクバーに乱暴されたためと考えたのだろう。
しかし、それは誤解だった。
アクバーはアンナを抱きしめただけで、あとは何もせずに彼女を解放したのだ。
だからこそ、彼女はこれほど戸惑っている。
「おいたわしい、さぞ辛かったでしょうに…」
「なっ…ちがいます!あの日は、その…あの…」
気がつけば、数人の町人が集まってきている。
恥ずかしげに弁明するシスターアンナ。
鎮めようとすればするほど鼓動は早まり、白い肌が桜色に染まっていく。
「私も辱めは覚悟していました…ですが、彼は…決して無理矢理には…」
「ああ、なんて可哀想なシスターアンナ…よりによって汚らわしい魔物とだなんて…」
無意識に十字架を掴みながら、しどろもどろに無事を告げるも、町人達には心配をかけまいとする嘘としか聞こえなかった。
彼女自身も、そして彼女を崇拝する人々も、いつの間にか弁明がアクバーを庇う内容になっている事には気付かないままだ。
「アクバー様、シスターアンナに手を付けなかったと言うのは本当でございますかな?」
「ああ、まだ抱いてはおらんぞ。」
所変わってアクバーの執務室。
アクバーのとった不可解な行動を、側近の妖術師ドグマが怪訝な顔で問いただす。
「一体どのような風の吹きまわしで?人間どもの心を折るのでは?」
「フッ、知りたいか?」
ニヤリと笑ってアクバーが語り出す。
「ただ力づくで奪ったのでは、奴らを真に屈服させる事は出来ん。むしろ怒りが更なる力を与えるだけよ。」
「はぁ、確かに一理ございますが…正攻法がダメとなると、如何にしてあの強情っぱりをモノにするおつもりで?」
ますます訳が分からないと頭をひねるドグマに対し、アクバーは愉快でたまらないといった表情だ。
アクバーはトントンと自分の胸を叩き、魔族とは思えない言葉を吐いた。
「ココロだよ。」
・二章
悪魔の魂を植えつけられてから一週間たった。
と言っても、シスターアンナにしてみれば、一体いつそんな物を植えつけられたのか分からない。
変わった事と言えば、毎日アクバーの部屋に招かれて食卓を共にしている事くらいだ。
「魔族の食事には慣れたかな?できるだけ人の食べ物に近い材料で作らせたつもりなのだが。」
「慣れる事など、できるはずが無いでしょう…」
口では反発しつつも、彼女は内心舌を巻いていた。
初日こそ、とても食べられたものではなかった料理は、日に日に改善されている。
材料は不明だが、味付けを工夫しているのか、今では質素な教会の食事よりも美味なのではないかと思えるほどだ。
「ふむ、まだ改善の余地があるか。」
「ええ…い、いえ!結構です!おかまいなくっ!」
「ハハハ、そう遠慮するな。確か、葉物野菜が食べたいと言う事だったな?ようやく調達の目途がついたそうだ。」
何より不思議なのは、こうしてアクバーが彼女の望みを聞き、叶えようとしている事だった。
魔物とはただ暴力を頼み、相手の意思をねじ伏せてでも欲望を満たす存在。
そう身構えていた彼女にとっては、却ってやり辛い相手だ。
「ふむ…」
「…何でしょう?」
いっそ完全に心を閉ざせれば悩む事など無かったのかもしれない。
しかし、あの日からシスターアンナは、妙にアクバーの事を意識してしまっていた。
話しかけられれば返事をし、見つめられれば律儀に何か用かと尋ねてしまう。
どれも人並の男性経験があれば気の迷いで片付けられる事柄にすぎないのだが、残念ながらそんな物は持ち合わせていなかった。
「いやなに、こうして改めてみると…やはりお前は美しいと思ってな。」
「んグッ!?は、はあ…それは…どうも…」
まただ。
最近のアクバーは、二言目には彼女を褒め、愛おしげな視線を送るようになっていた。
努めて平静を装いつつも、火照る体を鎮める術を知らないシスターアンナは、ただ俯くばかりだ。
誤魔化すようにせかせかと料理をかき込む彼女を眺めながら、アクバーは口角をつり上げた。
・三章
一ヶ月もすると、シスターアンナも町人達も、表向き以前の調子を取り戻した。
あくまでも表向きは。
彼女の心中は依然荒れ模様だ。
「シスターアンナ、ちょっと良いですかい?」
「え…?あら、ごめんなさい。考え事をしていました。」
こうして居住区に足を運び、耳を傾けはするものの、彼女はいつしか、町人達の言葉に共感できなくなっていた。
また魔物関係の愚痴か。
内心うんざりしつつ、居住まいを正す。
「全く、アクバーの野郎血も涙もありませんぜ!この間もうちの弟を…」
「はい…はい…」
憎々しげに吐露される心情にも、まるで気持ちが動かない。
せめて義務感だけでも取り戻そうと、十字架を掲げてみたものの、彼女の心は冷え切ったままだ。
「いつだってそうでさ!奴ら、自分が有利になったと見るや、どんな無茶なことも平気で言いやがる!」
彼女の眼にはむしろ、目の前の荒くれ男よりもアクバーの方が好ましく映っていた。
いつだったか、この男が懺悔したような乱暴を、アクバーは働かない。
本性がどうであれ、少なくとも自分の前では伸士であろうと律しているらしい彼の努力を、シスターアンナは高く評価していた。
「…ええ、そうですね。」
気の無い相槌にも、神秘の力は宿る。
こうして声高にアクバーを非難できるのも、シスターアンナの声によって喚起された勇気の賜物だ。
それが煩わしかった。
「ったく、親の顔が見てみたいぜ!」
「はぁ…アク……ッ!」
思わずアクバーの名を呟きそうになって、慌てて口をつぐむ。
慣れとは恐ろしいもので、一月もたてばアクバーと過ごす日常にも何の気負いも無くなっていた。
この居心地の悪い空間から離れたいと言うシスターアンナの思いは、いまやアクバーに会いたいと望む事と同義なのだ。
「以上が、巡回の牢獄兵の報告です。」
「おう、御苦労だったな。」
兵士長ゾゾゲルは、一月前から始まった、この奇妙な任務に困惑していた。
人間達を閉じ込めている居住区の見回りに加え、シスターアンナ個人の様子を事細かに報告するよう命じられたのだ。
「お言葉ですが、アクバー様。それほど気にかかるのであれば、お手元に置かれては…」
「フッフッフ、まあ見ていろ兵士長。今に面白い事になる。」
不敵に笑うアクバーの言葉は、まもなく証明されることとなる。
・四章
「フンッ、なによみんなして…」
「何を怒っている?せっかくの美人が台無しだ。」
いつもの歯の浮くようなセリフも、この日ばかりは効きが悪い。
眉根に皺をよせてヤケ食いするシスターアンナは、よくぞ聞いてくれたとばかりに顔を上げた。
「だって!みんな酷いんですよ!?」
「なんだ、なんだ?人間同士の内輪もめか?」
顔を寄せてシスターアンナの話に食い付いて見せる。
狙い通りの展開に指を鳴らしたくなる衝動をこらえ、あくまでも呆れ顔を装って話の続きを促した。
「毎日毎日毎日毎日、暇さえあれば他人の悪口ばかり私に吐き出して!私はゴミ箱じゃないんですよ!?」
「そうは言っても、仕方あるまい。お前しか話せる相手が居ないのだ。」
「だからって!」
人間達を励ましている時とはまるで違う、どこか幼さを感じさせる声に、部屋の前を通りがかった魔物は一様に目を丸くした。
大魔王も一目置いたシスターアンナの神通力が、彼女自身によってかなぐり捨てられようとしているのだ。
「一体何を言われたのだ?俺でよかったら聞いてやるぞ。」
プンプンと鼻息荒く主張するシスターアンナを宥めながら、アクバーは水を向けた。
溜めこまれたストレスがはけ口を提示され、溢れだす。
「そう、聞いて下さいアクバー!確かに魔物の側に非があるケースが多いのは事実です。けれど、みんなそれを良い事に自分の失敗や関係の無い事まで全部あなたのせいにして!」
「ほう?」
「何も知らないくせに!一面だけをあげつらって、乱暴者だの…悪魔だの…一体どういう神経してるのかしら!」
「ふむ、つまるところ…」
ここで呆れ顔を崩し、あからさまに喜色を浮かべて見せる。
シミュレーションどおりの結果は出るや否や。
「君は俺のために怒ってくれているのか?」
「あなたのためって………あッ!!」
指摘されて初めて気付いたのか、シスターアンナの顔がポッと紅潮する。
アクバーは、してやったりと目を細めた。
「それは…私だってあなたは嫌いです!あ、当たり前でしょう?」
「おお、妻よ。そう悲しい事を言ってくれるな。」
湯気を噴いて縮こまるシスターアンナに料理を薦めるアクバー。
しばらくは顔を伏せて呻いていたが、やがて観念したのか、彼女は俯いたまま、ばつが悪そうに食事を再開した。
肉は野菜は見た事もない物ばかりだが、もう口にする事に何の抵抗も無い。
その味付けが一週間も前から、初日と同じ魔物向けに戻っている事にも、おそらく気づいてはいないのだろう。
「アンナ。」
「…はい、なんでしょう?」
「そろそろ式を挙げようか。」
時は満ちた。
そう判断したアクバーは、いよいよ王手をかけた。
・五章
居住区は朝から大騒ぎだ。
いよいよシスターアンナとアクバーの結婚式が行われるとの通達がなされ、囚われの人間達を総動員して、会場の準備が進められている。
「くそっ、なんで俺たちがこんなことを…」
「シスターアンナを苦しめる片棒を担ぐなんて…!」
口惜しそうに吐き捨てつつ、町人達は数人がかりでギロチンを処刑台から運び下ろした。
人の背よりも大きい木と鉄の塊は、持ちあげるだけでも重労働だ。
また、処刑台から入口までの通路には赤い絨毯が敷かれている。
わざわざ人間の流儀を真似た結婚式を見せつけることで、彼らの郷愁をも嘲笑おうと言う訳だ。
そんな企みを手伝わされている町人達の胸中は、式が始まる前から暗澹としていた。
「よし、もう良いだろう。ドグマ、出番だぞ。」
「ヒヒッ、お任せあれ。」
ゾゾゲル兵士長が作業終了の号令をかける。
神父役のドグマが、空になった処刑台によじ登り、懐から聖書を取りだした。
シスターアンナの持っていた物だ。
「あーテステス…ごほん!では、新郎新婦、前へ。」
人々が遠巻きに見つめる中、城と居住区を隔てる大きな扉が開かれ、アクバーとシスターアンナが入場する。
望まぬ結婚を強いられた彼女を元気づけようと、制止する牢獄兵を押しのけながら、町人達が駆け寄った。
「ああ、シスターアンナ!お気を確かに!」
「負けちゃいけねえ!心を強く持って下せぇ!」
せめて一声と叫ぶ町人たちを尻目に、シスターアンナは静かに歩みを進めて行くる。
なおも悲痛な声は鳴りやまないが、ガチガチに緊張した彼女はそれどころではなかった。
「…緊張しているのか?」
「そそそそんな事は!ぜぜぜ、ぜぜん!」
やれやれ、初心な女とは思っていたが、ここまでとは。
アクバーは内心、少し困っていた。
引き攣った顔に涙まで浮かべ、繋いだ手を握り締めて来る。
「ほほう、では喜びで舞い上がっているのかな?」
「よ、よよよ喜んで!?」
いない、と言いきれない事が、彼女の心変わりを何より雄弁に物語っているのだが、二人を憎々しげに睨みつける町人達にはそれが分からないらしい。
ならばとアクバーは手を解き、シスターアンナの腰に回した。
「くっ…ああ、何てこと…薄汚い魔物なんかの手が…」
「あんのスケベ野郎が!」
「…!」
歯ぎしりしながら悔しがる崇拝者の声に、シスターアンナの眉がピクリと跳ねる。
不安と興奮にざわめいた心が急速に凪いで行くようだ。
代わりに湧きあがったのは、心ない野次に対する怒りだった。
「…なによ、アクバーはそんな人じゃないわ。」
周囲に聞えないように声を漏らし、彼女は自分でも信じられないほど大胆な行動に出た。
アクバーの体に身を預け、見せつけるようにもたれかかったのだ。
変われば変わる物だと感心しながら、アクバーは残りの道程をアンナと寄り添って歩む。
やがて二人は、血に染まった即席の祭壇に上がり、ドグマ扮する神父の前にたどり着いた。
「汝アクバー、病める時も健やかなる時も、この女アンナを妻とし、生涯愛することを誓いますかな?」
「ああ、名誉にかけて誓おう。」
さも当然と言わんばかりにアクバーが答える。
いよいよ、シスターアンナの番だ。
目前に迫った苦難に思いをはせ、修道服に忍ばせた十字架をぎゅっと握る。
「汝アンナ、病める時も健やかなる時も、この男アクバーを夫とし、生涯愛することを誓いますかな?」
「…ち、誓い…」
声を震わせながらチラリと視線を泳がせた。
泣き出しそうな彼女の眼を、鋭く力強い魔物の眼光が射抜く。
修道女シスターアンナが最後に縋った相手は、彼女が支えてきた人間達ではなく、黄金色の巨体を持つ魔物だった。
「誓います…っ!」
神々しさなど微塵も無い、絞り出すような声で、誓いの言葉が紡がれる。
人々の希望は、一人の女として、悪魔との結婚を受け入れてしまったのだ。
ドグマはニタリといやらしい笑みを浮かべ、プログラム進めた。
「よろしい、では指輪の交換を。」
精根尽き果てた表情で左手を差し出すアンナ。
同じく差し出されたアクバーの手に自分の手が添えられ、大きな指輪をはめて行く様を、彼女は他人事のように眺めていた。
しかし次の瞬間、他人事では済まない衝撃が彼女の全身を走る。
「ふわあああああああッ!?」
背筋を駆け抜ける得体のしれない感覚に、アンナは飛び上がった。
左手の薬指から、ドス黒い何かが洪水のように流れ込んで来る。
むずがゆいような、痺れるようなそれは、しかし決して苦痛ではなかった。
「うぁ、ぁぁぁぁー?あはああああああん!!!」
「ど、どうしたの!?」
「アクバーッ!シスターに何しやがったァ!」
たまらずアクバーにしがみつくアンナの体内では、劇的な変化が起ころうとしていた。
数か月もの間、魔族と同じ食事だけを摂っていた彼女の血肉は、既に隅々まで呪われた邪悪な滋養に満たされているのだ。
そこに、指輪を通して流れ込むアクバーの魔力が混ざればどうなるか。
「怖がる事はない。俺が付いている。」
「なぁ…なにをぉ…うげッ!?」
震える背中を抱きすくめながら、アクバーが囁いた。
直後、アンナの体が爆発するように膨れ上がる。
ゆったりとしていた修道服が一瞬でボロ布に変わり、破れ目から柔肌が覗いた。
肉に食い込んだ指輪が妖しく輝き、アンナの手の中に溶けて行く。
「あぶッ!がッ!あ゛ッ!あぁぁぁぁ!!!」
「ああ、そんな…」
「ちくしょう…何て奴らだ…」
人々が絶望的な表情で見守る中、アンナの体は2度3度と爆発を繰り返した。
まず目立ったのはウェストだ。
緩やかな曲線を描く砂時計が、早回しのようにデップリと肥えて垂れ下がる。
それに引きずられるように乳房が盛り上がり、あっという間に頭よりも大きく実った。
「ひがぁ…なぁにぃぃ!?なにこれぇぇぇ!?」
仰け反った首に継ぎ目が生じ、ブクリと二重あごが盛り上がる。
続いて肩が、腕が、だらしない堕肉に包まれた時、ついにアンナの腰がミシリと悲鳴を上げた。
しかし、それも束の間、肉の滝がなだれ落ちるように腰が膨れ、尻が膨れ、それらを支える足が巨木のように太っていく。
最後にその付け根、慎ましい秘裂が下腹の弛みに埋没した時、彼女の体から魔肉に覆われていない部位は消滅した。
「なんれぇッ!?キヒッ、気持ぢよしゅぎるううううう!?やああぁーんッ!!」
心なしか背まで伸びて行くようだ。
小柄ではないが、それでも160㎝程度だった身長が恐ろしい勢いで増大する。
僅かに引っかかった衣服の切れ端を吹き飛ばしながら、彼女の頭は3m近いアクバーのそれと突き合わせられる程に押し上げられて行った。
「よく頑張ったな、アンナ。」
「ぶぇ…あ、アクバーぁぁどこですかぁ…?こわい…たすけてぇ…」
もう野次馬の声など意識の範疇に無い。
荒い息をつきながら、アンナは必死にアクバーを探した。
いまだ焦点の合わない視界の中に金色を見出すと、彼女の心を安堵が満たして行く。
「キーッヒッヒッヒ!新婦の癇癪は収まりましたかな?では誓いの口づけを。」
「うむ。さあアンナ、顔を上げてくれ。」
いつかと同じように、穏やかに微笑みながらアクバーが近づいて来る。
もはやアンナの脳裏には、拒絶するという選択肢すら存在しなかった。
溺れた人間が藁に縋るように、目の前の首をかき抱いて、深いキスを交わす。
脳髄が痺れるような多幸感に、アンナの目から涙がこぼれた。
「んむ…はあぁ、すごい…どうして、こんなに幸せなの?」
「それはな、アンナ。俺たちが愛し合っているからだ。」
実を言えば、彼女は初めてのキスで、既に致命的なダメージを受けていた。
左手の甲に押された不可視の刻印がじわじわと肉体を侵食し、彼女の心身は無意識の内にアクバーの魔力に馴染んでいたのだ。
そして今日、結婚指輪と言う起爆装置は、十分すぎる威力を以てアンナの魂を破壊した。
今や彼女の存在は、巧妙に仕込まれた悪魔の魂によって成り立っている状態だ。
「ああ、何か…来ます…!いやぁ、怖いよぉ…」
「大丈夫だ、すぐに済む。ちっぽけな人の皮など脱ぎ捨てろ。俺の妻に生まれ変わるのだ!」
粘膜から直に魔力を流し込まれた魔肉が、とうとう人の形を捨て始めた。
赤く色づいた皮膚は完全に元の肌色を失い、オレンジを経て黄色に。
脂を帯びて輝く様は、まるで黄金だ。
背中から垂れた肉がひとりでに伸び上がり、もう一対の腕のように張り出して行く。
「うがぁ!?」
「ひええっ!あれは何だッ!?」
「きゃああああああ!」
アンナの体が跳ねた。
今しがた生まれたニ対目の腕から、骨のような突起が突き出したのだ。
やがて、骨に沿って皮膜が張られ、腕は翼に変わっていく。
「アンナ、俺の眼を見ろ。最後の止めを刺してやる。」
「ふぎぃ…はい…ああ、あああ!あああアナタぁぁぁーーーッ!!!!」
あくまでも従順に従うアンナ。
アクバーはその頭を掴むと、不安に濡れた瞳を覗きこんだ。
膨満した肉が極限まで興奮し、比喩では無く湯気を噴き上げる。
真っ白な湿気のヴェールが、花嫁の姿を覆い隠した。
「何と!あの尼がこれ程の魔力を発するとは!」
「ヒッヒッヒ、なるほど。これは確かに、無理やり植えつけるよりも深く効果があるようですなぁ!」
訳知り顔の側近二人に対し、参列させられた人間は、うろたえるばかりだ。
ただ、敬愛するシスターアンナが惨い仕打ちを受けているという事実だけを理解し、唇を噛んで成り行きを見守っている。
やがて、湯気は徐々に薄まり、その中に人影が浮かび上がった。
「金色の…肌…あああ…」
「ウソだッ!シスターが…俺たちのシスターアンナがぁ…」
視界が晴れた時、もうそこにシスターアンナの姿は無かった。
同じ大きさ、同じ肌、同じ翼。
濛々とした白煙の中から現れたモノは、アクバーそっくりのモンスターだったのだ。
・六章
カラン
乾いた金属音が、打ちひしがれた沈黙を破る。
アンナが式の始めから握りしめていた十字架を取り落としたのだ。
原型が分からないほどにひしゃげた残骸は、そのまま台の下まで転げて落ちた。
「気分はどうだ?」
アクバーが尋ねる。
アンナはアクバーに視線を固定したまま、夢見るような口調で答えた。
「とても素敵ですわ、アナタ。」
パタパタと、生えたばかりの羽根がはためく。
おそらく、彼女なりの喜びの表現なのだろう。
再びキスを求めて唇を尖らせるアンナを、アクバーが制する。
「まあまて、初夜の前に招待客にあいさつくらいしなさい。」
「えぇー、面倒くさいです。」
アンナはむくんだ頬をさらに膨らませて不満を表した。
親身になって人間たちを励ましていた頃の面影は、もはや微塵もない。
それでも、愛するアクバーのためならばと気を取り直し、彼女は言葉を失った町人達を振り返った。
「アンナです。シスターやめました。この方の妻になりました。」
言うべき事は言ったとばかりに、さっさと身をひるがえすアンナ。
あまりにも気持ちのこもらない声に、アクバーも苦笑いだ。
「まったく…なんだそれは。」
「むー、そんな事よりキスしましょうよ、キスー」
もはや周りなど眼中にないとばかりに、アンナは目一杯アクバーに甘えた。
アクバーは肩をすくめると、神父役のドグマに目配せして下がらせる。
そのまま、遮る物の無くなった処刑台の真ん中で、アクバーは妻の肢体を見せびらかすように羽交い絞めにした。
「きゃんっ!?あ、アナタ!いきなり何をなさるの!?」
「そんな、ぞんざいな挨拶があるか!仕様の無い奴め!俺に嫁ぐと言う事がどう言う事か、本当に分かっているのか?」
二つの巨体がイチャイチャと揉み合う。
今度は見上げる町人達からも、アンナの変わり果てた体がハッキリと見えた。
「うぷ…」
「こりゃあ、ひでぇ…」
何人かは露骨に目を背けた。
無理もないだろう。
身長実に260㎝、体重に至っては一体何百㎏あるのか想像もつかない。
人間ではありえない黄土色の肌が、脂汗で金属のように輝いている。
「さあ妻よ、生まれ変わった体についておさらいだ。お前はコレで何をする?」
「くぁ、あぁん…」
鉤爪が無造作にアンナの胸を掴む。
人の頭どころか、その倍は有りそうな脂肪塊を果たして乳房と呼んでいいものか。
「はふ…ええと、赤ちゃんに乳をやります。」
「それだけではないだろう?」
アクバーはニヤニヤと好色な笑いを浮かべて、アンナを向き直らせた。
そのまま頭を抑えつけ、跪かせる。
容赦のない荷重に、木製の台がメリメリと軋んだ。
「さあ、もう一度言ってみろ。その無様な脂身は何に使う物だ?」
腰帯を外し、努帳を突きつける。
大きな体に見合った棍棒のような逸物に、アンナは暫し見惚れた。
いかに無垢と言えど、ここまでされればアクバーの意図に気付くのはたやすい。
おずおずと乳肉を掴み、肉槍を挟みこむ。
「こ、こうやって…アナタに喜んでもらうために、使います…?」
タプタプと魔肉を揺すり、アンナは懸命にアクバーの分身をしごいた。
脂が潤滑剤の役目を果たし、半勃ちだった逸物が硬く大きくそそり立つ。
人外の爆乳を更に突き抜けて現れたパートナーの頼もしさに、アンナはどこか誇らしげな笑みを浮かべた。
「そうだ。気持ちがいいぞ。さすがは俺の選んだ女だ。」
「うふふっ…もう、アナタったら…」
普通の人間は魔物同士の性交を目にする機会など無い。
まして、これほどの醜悪さともなれば、いかに狭間の世界に耐え抜いた牢獄の町の住人と言えど、許容できる物ではないだろう。
とうとう、顔を覆ってすすり泣いていた女性が一人、口を押さえて呻き始めた。
「ぐず、ぶぇ…うげえぇぇっ!」
一人決壊すれば、後はあっという間だ。
釣られた人間達が次々と顔を背け、嘔吐する。
ハッキリと目に見える形で苦しむ人間達の姿に、魔物たちが手を叩いて笑い転げた。
そんな阿鼻叫喚の光景には目もくれず、壇上の二人はさらに淫らな行いを続ける。
「次は下だ、アンナ。そのだらしない腹肉も使って見せろ。」
「お腹!?ええと、お腹のお肉は…こ、こうかしら?」
今度は迷い無く、デップリと垂れ落ちた腹肉を抱え上げ、アクバーの肉棒をくるむように腰を上げた。
肉をかき集めてできたヒダが、まるで膣のようにカリ首を絡め取る。
「ぬはぁ…こ、これはッ!」
必死に羽ばたいてみても、やはり半端な姿勢は苦しいのか、中腰の膝を開閉する度に、アンナの体が汗ばんで行く。
脂汗でヌメる肉ヒダの挿入感は、まさに濡れた性器その物だ。
「ど、どうですか、アナタぁ?アンナの腹ズリ、気持ちいいですか?」
「どこでそんな言葉を覚えて来た!?この淫乱め!!!」
もう限界だ。
アクバーはいかにも名残惜しそうに、肉のオナホールから分身を引き抜き、アンナを床に突き飛ばした。
間違いなくトン単位に達したであろう衝撃に、バキッと致命的な音が鳴る。
ただ一人、アンナの最後を見届けようと歯を食いしばっていた荒くれ男が、飛び散った木片に打たれて気を失った。
「はあ、はあッ!アンナ!分かっているな?自分が今から何をされるのか、お前は理解しているな!?」
伸士の仮面をかなぐり捨て、血走った眼で肥えた女体をまさぐるアクバー。
隠し続けた剥き出しの獣性は、羽ばたきの風とともに受け入れられた。
「はい…私は…アンナは今からアナタのモノにされます…!」
ズシンと地響きが起きた。
アンナが自ら身を横たえた音だ。
誘うように太ももの魔肉を撫でまわしながら、アンナは高らかに自らの死刑宣告を読み上げた。
「アナタに純潔を散らされて…アナタに種を仕込まれて…アンナは、アナタの子を産みますぅッ!」
「~~~~~ッ!!!ぐおおおおおおッ!行くぞぉ!」
2つの巨影が一つに重なる。
空気が震えるほどの衝突音と、不快な水音。
そして
「ぐはあ゛あ゛あ゛ーーッ!ぶがががッががあああーーーッ!」
惨めに堕ち切った雌豚の鳴き声で、アンナは絶頂を告げた。
トチ狂ったように床でのたうつ両翼が、心からの悦びを表現している。
そして同時に、それがベッド代わりの処刑台への止めとなった。
板木と金具の砕け散る音を伴奏に淫らな咆哮が響き、その場にいた人間すべての希望を打ち砕いて行く。
その様はまるで、彼女の声にかつてと正反対の力が宿ったかのようだった。
・エピローグ
流れる月日の中、シスターアンナを失った人間達は、急速に気力を萎えさせていった。
何をするでもなく日々を過ごし、気まぐれに訪れる魔物に虐げられる日常。
この日も一人、虚ろな目の女が標的にされた。
「へへっ、お姉ちゃんも大分デブったね。」
「ぅぅ…ぁー…」
アクバーよりは大分小柄な金色の魔物が、素っ裸でへたり込む女性に声をかける。
やや小太りの女体がビクンと震えた。
しかし、魔物は女性のおびえなど意にも介さず、口淫を強要する。
「お、上手になったじゃん!これならいい肉便器になれるよ。」
「んっ…くちゅっ…ぶじゅ…じゅっ…」
小柄と言っても、それはあくまでアクバーに比べての話だ。
太く長い肉棒を無遠慮に挿し込まれ、女性の額に脂汗がにじむ。
5分ほどそうしていただろうか、突然ピタリと注送が止まった。
「くぅぅ、気持ち良いー!やっぱり一発目は口に限るね。」
「うぶっ…ううぅぅ…あ、あふんぅぅ…」
満足げに息を突く魔物をよそに、今度は女性の方が悶え始める。
幾度となく魔のエキスを注がれ続けた肉体が、精液に含まれる魔力を吸って、また少し肥大した。
「よしよし、膨れたねー。んじゃ、このまま下にも種付けしてあげようか。」
「やぁ…魔物は…アンナはいピギッ!?ブヒッヒィーッ!?!?」
四つん這いのまま逃げ出す尻目がけて、一突き。
口で何と言おうと、ガバガバに開発された女陰はとっくにその気になっているのだ。
激しいピストンの度に尻タブが波打ち、常人なら腰骨が砕けるほどの衝撃を受け止める。
女の体は既に、反吐が出るほど嫌ったはずの魔物との交尾に適応し切っていた。
「ふふ、頑張ってるわね、ボウヤ。」
もう一つ、大きく変わった事がある。
結婚式の日に、一つしかない処刑台が粉砕されたため、ギロチンを用いた住民の処刑が不可能になったのだ。
代わりに反乱分子の粛正に当たっているのが、今しがた居住区に入って来た、アクバーの新たな側近である。
「それじゃあ、私も仕事を始めましょうか。」
「うう…し、シス…」
「その名で呼ぶのはやめなさい!」
大の字に拘束された荒くれ男に、女悪魔の脚が容赦なく突き刺さる。
人間の倍近い長身から繰り出されるトーキックの威力は、肉を打ち抜き、骨を震わせる程だ。
哀れな犠牲者は、たまらず悲鳴を上げた。
「うぎゃあああああッ!!!!!」
「まあ、情けない声。そのあらくれマスクは飾りなのかしら?」
蹴りの動作に合わせて、裸の胸がブルンブルン揺れる。
真っ黒に塗りつぶされた先端で、真鍮のピアスも楽しげに舞い踊った。
鋳潰され、魔王軍の紋章へと生まれ変わった信仰の証が示す意思は、魔族への絶対服従に他ならない。
「反逆者がどうなるか、当然知っていますね?」
「げほっ、目を…覚まして下せぇ…し、シスター…」
「同じ事を何度言わせるのッ!?物覚えの悪いやつね!!」
女悪魔が再度荒くれ男を蹴りつける。
そのまま、無駄話は終わりとばかりに憮然と男のマスクを剥ぎ取った。
自らも主人とそろいの腰帯を脱ぎ捨て、熱く濡れた処刑器具を露わにする。
「お前を、反逆未遂の罪で圧迫刑に処します。私の中で逝けることを光栄にお思いなさいな。」
「こ、こんな…こんな破廉恥な真似をして、あんた恥ずかしくないんですかい!?えぇ!?シスターアンナ!?」
それが荒くれ男の最後の言葉だった。
勢いよく女悪魔の腰が下ろされ、男の鼻と口が汚れた女陰に飲み込まれる。
ズッポリと嵌り込んだ顔面に向かって大量の愛液が分泌され、受刑者は呼吸器を魔物の体液に埋め尽くされて絶命すると言う仕組みだ。
「ふふ、なかなか良いですよ?このまま殺すのが惜しいくらい。」
かすかな官能を貪るべく、女悪魔はキュッと足を閉じ、腰をくねらせ始めた。
石臼ならぬ肉臼として恐れられている、牢獄の町の新たな名物だ。
胎内に反響する苦悶の声に、女悪魔の興奮が加速する。
「はっは…ぁ、そろそろぉ…い、イックゥゥーーッ!!!」
女悪魔の手が、眼下で揺らめく太鼓腹を抱き締めた。
正視に耐えない贅肉の正体は、催淫の魔力でできた巨大な性感帯の塊だ。
巨木のような脚が、小山のような尻が、脆い人間の頭を咥えたまま痙攣する。
グ シ ャ ッ
…あとは気が済むまで楽しんだ後、膣穴から残骸をひり出して、今日の仕事は上がりだ。
「昼間からお盛んだな、我が妻よ。仕事にかこつけて、俺の居ぬ間に男遊びか?」
「あーっ、ひどいわアナタ!」
と思ったが、今日はどうやら、もう一仕事あるようだ。
視察に来たのは、彼女の主にして夫であるアクバー。
楽しそうな妻子の様子に、腰帯の上から分かるほど股間をいきり立たせている。
色狂いの女悪魔が、そんな物を見せつけられて黙っているはずもなかった。
今しがた処刑した男を尻に敷いている事も忘れ、血みどろの股間を突きだしておねだりポーズをとる。
「ほらぁ!ちゃんとご覧になって!アンナの卑しい堕落マンコは、いつだってアナタのチンポが食べたくて、ヨダレまみれですっ!」
「ハッ、なら好きなだけ食らうがいい。」
まずは少し入口をなぶってから、等と組み立てていた流れは一瞬でご破算。
いつも通り、アクバーの逸物は、あてがうと同時に最奥まで引きずり込まれて行った。
「んほおおおおーーッ!!あ、アナタぁぁ!!最高ぉぉぉーーーッ!!!」
「ぐぬぬ…いつもながら、何と言う吸い付きだ…!全く、お前は俺に犯されるために生まれて来たような女だな!アンナッ!」
バサバサと羽音を立てて、金色の肉塊が亡骸の上をのた打ちまわる。
数百㎏+数百㎏×数百往復。
かつて仲間であったモノを粉々に擦り潰しながら、女悪魔はいつまでも肉の悦びを貪り続けた。
一方その頃、完全に忘れ去られた地下の独房で、髭面の男が男泣きに泣いていた。
何故神はこのような所業を許すのか、この世に救いは無いのか、と。
「よもや、本気ムドーに勝てずに10年も積みゲーとは…ッ!この大賢者クリムトの目をもってしても見抜けなんだわ…!」
とりあえず、救いは無いらしい。
(完)