877氏その2
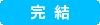
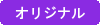
私の住む王国は、他の国とは少し違う。
統治しているのは王ではなく、女王なのだ。
その名も高きアメリア女王。
御姿は形容しがたいほど美しく、圧倒的な求心力で以って国の戦士たちは負け知らず。
私もかつて一目見たものだが、赤いドレスに長身痩躯を包んだお姿は、いっそ悪魔的ですらあった。
そして、アメリア女王には度胸もある。
西の賢人プルーフ様の遊説を受け、即採用なさり、
東の狂戦神テスカトリポカさえ、軍に加えなさった。
東の狂戦士といえば戦場と見れば突っ込み、暴れるしか脳のない無法者と聞いていたのだが、
どうやらそれは彼をどこかの国に登用させまいとする罠だったらしい。
女王はそれさえ見抜き、彼を雇ったのだ。
最後に、これがもっとも変わった点。彼女の耳は、少々とがっている。
これがもし秘密のことであるなら、私は今すぐ穴を掘って叫ばなくてはいけないが、
幸い女王はエルフ――即ち異種族であることを隠していない。
そのおかげで、この国は人とエルフの共存する都市になっている。
なんだかんだいって、これがこの国のもっとも変わっている点だろう。
なにせ、私たちエルフは魔法が使えるのに対し、
人間は使えない。それを向こうが妬むのは至極もっともだ。
そんな女王のもっともお傍に仕えるのが、侍女と呼ばれる人々だ。
毎年国で大々的にオーディションを行い、合格したものを自らの侍女にしている。
それ故、王女は男嫌いなのではないか、という噂まであった。
さて、ここでやっと本題に入る。
なんと、この私セルフィアは、このオーディションによって侍女に選ばれたのだ!
審査の瞬間の緊張と、決まったときの嬉しさったらこの世に類を見ないほどだった。
というわけで、今日から宮仕えである。
私は天高くそびえる城のエントランスから、玉座の間へ案内された。
「貴女が、セルフィアね。私がアメリア。楽にしてください」
目の前には女王。私は頭を垂れ、女王の脇には憲兵二人。正直、楽にできる状況ではない。
「はい」
ただ、女王の命令だ。私は頭を上げて立ち上がり、直立不動の姿勢をとる。
それを見て、女王は少しクスリと笑った。
「そうね……まずは、食事にしましょうか」
言うと、女王はついてくるよう身振りで示し、移動を始める。
向かった先は言葉の通り――ダイニングだ。
既に料理は用意されており、幅二メートル、長さ五メートルほどの大きなテーブルの上には、
ところ狭しと料理が並んでいた。
私はその光景に圧倒されていて、何も言えない。
給仕が何人か――全員女である――居るが、テーブルに着くのは私と女王二人きり。
とても、二人で食べれる量ではない。
中央にそびえるケーキだけでも、小食の私と痩せ身のアメリア様では到底歯が立たないだろう。
「では、いただきましょうか」
しかし、当然のように女王が食べ始める。
食事は皿にとって、給仕が持ってきてくれる。
私も女王の食事を残すわけにはいかぬと思い、食べ始めた。
ところがこれが、おいしい。
流石は女王といったところなのだろうか。
肉、野菜、穀物、どれをとっても一級品だ。
(ここにいろんな料理のおいしい描写)
気づくと私は、満腹をとうに超えて食べていた。
明らかに食べすぎである。
それなりに余裕のあるはずの服の、ウエスト部分がきつい。
これ以上は食べれないと思ってテーブルを見ると、私の側にはまだ多くの料理が残っている。
もったいないが、食べきれない。
ついでにその向こう、ケーキをはさんで女王のほうのテーブルを見る
なんと、ほとんどの料理が消えていた。
よく見ると、間のケーキさえその高さを半分ほど減らしている。
「あら、貴女も終わったようね? いいでしょう」
上品に口をナプキンで拭いて、女王が口を開く。
あれほどの量を(恐らく)毎日食べてあの痩身とは……恐ろしい。
「では、貴女がこれからどうすごすか、説明します」
お腹いっぱいで眠くなりそうだった意識が、一気に冴えた。
女王の口元を注視し、耳を研ぎ澄ませる。
「とりあえず、これからの一年、貴女は見習いです。先輩方の指示をしっかり受けて働くように」
「はい」
ゲップをこらえながら、なんとかそれだけ返事をした。
「よろしい。では、明日からお願いします。
詳しいことは、部屋に冊子が置いてあるはずです。
よく読みこんでおくように」
「はい……ゲフ」
こらえきれずに、すこし出てしまう。
顔を真っ赤にしてうつむく私を、女王は笑顔で見ていたのだった。
二ヵ月後
「ご馳走様でした」
私はそういって、食器を置いた。
「ご馳走様」
ほぼ同時に、正面の女王も食べ終わったようだ。
時刻は夕食時。
あれからほとんど毎日毎食、私はアメリア様ともに食事を取っていた。
あれほどの量をお食べになるのに、その美貌に陰りの色は一切見えない。
それどころか、ますます美しくなった様ですらある。
かく言う私は、最初あれだけ残していた食事を、結構な量食べれるようになっていた。
それでも、見かけ上は、変わっていない。
「では、下がっていいです。ご苦労様でした」
「はい。では、失礼します」
そうして、部屋に戻り、私は服を脱ぐ。
ゆったりとした寝巻きに着替えてから――
『魅了(チャーム)』の魔法を解いた。
瞬間、さっきまで余裕があった寝巻きが、内側から押されパツパツになってしまう。
もともと小さくは無かった胸はほんの少し、気持ち程度に膨らんでいた。
だが、ウエストの砂時計は崩れ去り、寝巻きから生地を奪う一番の要因になっている。
お尻もただでは済まず、ただでさえ足りていない丈を下から押し上げる。
ふとももは、その太さのために寝巻きに動きを制限されて、動かし辛い。
そう、私は太っていた。
「はあ……」
息を吐きながら、お腹の肉をつまむ。
それほどの努力も要らず、かなりの量がつかめてしまう。
「少しは、痩せないとなあ」
要因は分かりきっている。アメリア様との食事だ。
あれほどおいしいものをお腹いっぱい、一日三食六十日詰め込んだのだ。太らないわけが無い。
しかも、断る事もできない。
運動をしようにも、昼間はずっと侍女としての訓練に当てられている。
夜になれば、ごらんの通り人前に出られる姿ではない。
「はあ……」
体重ばかりでなく、ため息も重くなる毎日である。
六ヵ月後
「ご馳走様でした」
「ご馳走様」
私とアメリア様は、ほとんど同時に夕食を食べ終わった。
それも、テーブルの上の食事、ほとんど全てを。
アメリア様が、以前は私に合わせて食べてくれていたのがよく分かる。
私の食べるスピードが上がると、アメリア様も合わせて速くなっていっくのだ。
「最近、どうかしら。仕事の方は?」
「やっと、基本は頭に入りました。でも、まだミスばっかりで……」
「そう。最初は仕方ないわね」
おかげで、こういった雑談の時間もできた。
「ああ、あと……」
「はい、なんでしょう?」
「必要かと思って、届けさせておいたわ」
何を? と聞くような無礼なことはできない。
「分かりました……? ありがとうございます」
「いえいえ。女王としては当然よ。じゃあ、下がっていいわ」
何を届けていただいたのだろうか?
すこし楽しみにしながら、私は部屋に戻る。
服を着たまま、部屋のベッドの上に置かれている包みを開いた。
中から出てきたのは、緑色の布。それも、かなり大きい。
「――まさか」
冷や汗をたらしながら、急いで服を脱ぎ、魔法を解く。
身体が膨らんだ。
胸はもう、自重で形を保てないほど大きい。
お腹は、そんな胸が乗っかるように前に突き出ている。
全部脂肪。もはやつまめるというレベルじゃない。
ぐにぐにと、揉むとどこまでも柔らかい。
ついでにお尻もすごいことになっている。
背中にも肉の段ができているし、あごもとうに二重だ。
そして、太ももはもはやちょっとした丸太並。
まっすぐ立っていてもぴったりくっついてしまう。
当然、入る服など無いので、ここ最近は裸で寝ていた。
……のだが、女王の贈り物。
これは――特大の、肌着だった。
上はシンプルなビキニタイプ
下はそれに、少々シルクの布がついた感じだ。
着てみる。……私のサイズにぴったりだった。
……何故太ってしまったことがばれたのか?
とまあ、一瞬疑問に思ったが、アメリア様ほどのエルフなら、いろいろと手段があるのだろう。
私は残念ながら『魅了』の魔法しか使えない。
とりあえず、久しぶりのこの状態でも着れる肌着に満足して、私は眠りについた。
約)一年後
「ご馳走様でした」
「ご馳走様」
一年繰り返されたこの食事も、今日で最後だ。
多すぎたこの食事も、今では普通と感じるようになってきた。
時たま城下に行ったときなど、お腹が満たせず苦労したものだ。
「セルフィア」
「はい」
「この一年、どうでしたか?」
少し考えて、応える
「多種多様な事柄を、存分に身につけられた一年でした」
いろんな意味で。
「では、明日からは私付きの侍女として、存分に働いてください」
その言葉に、私はただ礼を以って返す。
「では、今日は下がっていいでしょう。また、明日」
「はい。では、失礼します」
部屋に戻り、鍵を閉める。
そして、魔法を解いた
身体が、一気に膨れあがる。
なんとか踏ん張って、しりもちをつくのだけは避けられた。
そして、アメリア様にいただいた下着を着る。
なんとこの下着、既に三回はサイズを更新している。
それでも、今の私には少しきつい。
胸はもはやよく分からない肉の塊になってお腹のうえに鎮座している。
サイズが合わず、どうしても乳頭が浮き出てしまう。
丸出しのお腹はもっとひどい。
なんとか入ったパンツの上に乗っかり、これでもかと存在を主張する。
今の私が寝転がったら、ちょっとした山みたいに見えるだろう。
さっき魔法を解いたばかりなのに、身体は汗で光っている。
ついでに、腕にもたっぷり脂肪がついて、使うたびにぶるぶると震える。
足は太い。そこいらの木には負ける気がしないほど太い。
靴下のゴムの部分が食い込んでいる。
「……勝ってどうする」
あまりにもむなしいので、自分で突っ込んでみた。
「それにしても、これは……」
口元に手をやる。右手は大きくなった胸の上に。
「太りすぎ、だよねぇ……」
鏡を見ながら、そう呟いた。
ただ、これだけ太ってしまっても、ひとついいことがあるのだ。
ちょっと前まで魔法といえば『魅了』しか使えなかった私だが、
なんと、『靴下を履く魔法』が使えるようになったのだ。
……必要に、迫られて
「ああ、痩せたい……」
そういいながら、手はお菓子をさぐり当ててしまったのだった。
蛇足
「フフフ……」
暗い部屋の中心で、私は笑った。
私の瞼の裏には、『監察(ウォッチング)』によって捕らえたセルフィアの夜の姿が映し出されている。
「また一人、落としてしまった……」
そういいながら、自分の身体を探る。
もう魔法なしには動けないほど肥満した身体。
お腹は直立しても地面につくほどで、腕は『魅了』状態のウエストより太い。
首なんてとうの昔に消え、今合う服は特注で作らせた下着だけ。
色は赤。デザインは、あの子と色違いだ。
「……フゥ」
座っているはずなのに息が切れて、紛らわすためにそばに置いておいたジュースを流し込む。
ついでにクッキーを二、三枚鷲づかみ、口に放り込む。
「……痩せてるのがいけないんだわ。……痩せてるのが」
そういえば、もう次のオーディションの時期だ。
王女である私が、侍女を選ぶ時期。
「次は、どんな子にしようかしら」
……魔法が使えるからって、種族差別はよくないわよね。