バッドエンド
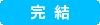
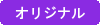
私は中学校でいじめられている。
殴られたり、ノートを引き裂かれたり、クラス中から無視されている。
けれども、そんなどうしようもない毎日でもなんとか生きてこられた理由は、
2つ年上のお姉ちゃんが私を励ましてくれたから。
私が泣いて家に帰ってくると、お姉ちゃんはいつも「あなたは悪くないわ」と言って、
私の細い体をぎゅっと抱きしめてくれた。
去年の4月にお姉ちゃんが高校に入学してから、お姉ちゃんは私を避けるようになった――
気がする。
私は部活には入っていないので毎日夕方5時くらいには家に帰っているけれど、
お姉ちゃんは陸上部の練習で大抵夜8時すぎに家に帰ってくる。
お姉ちゃんが帰ってくると私は玄関でお出迎えをして、なぐさめてもらおうとするのだけれど、
「今日は部活の練習で疲れてるから勘弁してね」と微笑まれて軽く頭を触られるだけ。
私は相変わらずいじめられているのに。
本当はお姉ちゃん、駄目な私の相手をするのが嫌になったのかもしれない。
そう考えると、自分が途方もなくみじめなゴミみたいな存在になった気がして。
学校に通う気力もでなくなって。
私は家に引きこもるようになった。
太陽が登りきった自室で布団に包まりながら、お姉ちゃんは今頃高校で
楽しく過ごしているんだろうなと思う。
お姉ちゃんがいつも家にいて私と一緒にいてくれるならどれほどいいだろう。
***
その日も私は布団の中でうとうととしながら、夢とも現実ともつかない時間を過ごしていた。
うららかな午後の日差しが部屋に差し込む。
突然、私の名前を呼ぶ声がした。
「……誰?」
声がした方向を向くと、部屋の隅に陰気な顔の痩せた男が立っていた。
背丈は私の胸ほどしかない。真っ黒なスーツを着て真っ黒な山高帽を被っている。
「はじめまして」小男は静かにお辞儀をした。
「そんなにおびえた顔をしなくても大丈夫ですよ。私はあなたの願いをかなえる存在なのです」
「願いを叶える……?」
「はい」と言って、小男はこちらに近づいてきた。
「あなたはどうやら相当の不満を抱え込んでいるようだ。根暗でいじめられっ子でかわいそうな私。
でも、お姉さんは相手にしてくれない。違いますかな?」
「そうよ」
目の前の小男に不満を吐き出すように、私はぽつりとつぶやいた。
「……お姉ちゃんがずっといてくれればいいのに」
すると、小男はにやりと片方の口の端を釣り上げた。
「その願い、私が叶えましょう」
「叶えるって、どうやって?」
「いたってシンプルです。その方法とは」小男の骨ばった指が私に向けられた。
「お姉さんが学校に行けなくなればいいのです。
そうすれば彼女はずっとあなたのそばにいてくれるでしょう」
「……」
「私にお任せください。明日、あなたは驚くはずですよ」
私が何か言う前に、小男は壁に溶け込むように消えていった。
***
「どうしよう……」
小男が消えた後、私は後悔していた。
勢いでつい言ってしまったが、正体不明の人間(?)に
「お姉ちゃんがずっとそばにいてほしい」とお願いをしてしまった。
もし、これが物語だと、小男の正体は悪魔で、願いをかなえてもらった結果は
大抵ろくでもない結末になるのが定石だ。
お姉ちゃんはどうなってしまうのだろう。
もしかしてとんでもない過ちを犯してしまったのかもしれない。
不安が心の縁から溢れ出そうになる。
私は罪悪感から逃げるように布団にもぐりこみ目をつむった。
***
目が覚めると、辺りは真っ暗になっていた。時計の針は午後8時すぎを指していた。
一時だけ眠るつもりが、どうやら寝過ぎてしまったようだ。
寝ぼけ眼で階段を降りていると、玄関の扉がゆっくりと開いた。
けれど、扉は半開きのまま止まり、その影から呻くような声が聞こえた。
「……誰か助けて……」
お姉ちゃんの声だ。
走り寄って扉を開け放つと――そこにはぶくぶくに太ったお姉ちゃんが入口に詰まっていた。
「……香織、助けて……無理に体をねじ込んだら動けなくなっちゃったの……」
膨れた頬を上気させ額に汗を浮かべながら身動きするお姉ちゃん。
私はそのむちむちとした太い手をつかんで引っ張ったが、
満月のように丸々としたお腹がつっかえてしまって、びくともしなかった。
「い、痛い……」
駄目だ、びくともしない。体力がない私の息はすでは上がってきていた。
「そうだ。お姉ちゃん、ちょっと待って」
私は廊下を走り、庭に面した居間から外に出て玄関に回った。
扉に詰まっているお姉ちゃんの後ろ姿が見える。
二つの桃をつけたような巨大なお尻に、紺の制服のスカートがぴっちりとひっついて、
お姉ちゃんのボディラインが目立つ。私はその迫力のある巨尻を押した。
「やだ、 どこ触ってるの!?」
引いてダメなら押してみろ。人間の構造上、引くよりも押す方が強い力が出るはずだ。
分厚い脂肪の感触を手に感じながら精いっぱい押した。
「……お姉ちゃん、頑張って……」
「ん、んっ……」
わずかにお姉ちゃんの巨体が前進していき、ついにが入口から外れた。
家中を振動させて、お姉ちゃんは前のめりに倒れた。
「あ、ありがと。助かったわ」
お姉ちゃんは何とか起き上がると、雪だるまのような体でぎこちなく回れ右をした。
首に肉がつきすぎて顔だけこちらに振り向かせるということができないのだろう。
「どうしてそんな体に……?」
私は答えを予想しながら、廊下の床に座っているお姉ちゃんに聞いた。
「これは……」と、恥ずかしそうにためらった後、
「学校で急に、体が膨れ出したの」と言った。
おそらく、さっきの小男の仕業だろう。
どんな力を使ったのか分からないが、あいつはお姉ちゃんを太らせ、
動くことが困難な体にしてしまったのだ。
申し訳なさで胸が張り裂けそうになった。
目の端が熱く感じたと思ったら、涙が頬を伝っていた。
「ごめん……なさい」
「どうして香織が謝るのよ? あなたは悪くないわ」
そう言って、お姉ちゃんは肉厚の手で私の頭をなでてくれた。
温もりが伝わってくる、とても優しい仕草だった。
「うぐっ、ぐすっ、ごめんなさい、ごめんなさい……」
「あらあら、私のことは心配しないで。太ったくらいでくじけるようなやわな精神はしてないわ」
そう言って、お姉ちゃんは突き出たお腹を叩いた。
ぽんっ、ととても良い音がした。
「あはっ」
思わず笑みがこぼれた。
そうだ、お姉ちゃんはこれほどまでに私のことを気にかけてくれていたんだ。
数時間前まで自分の殻にこもってうじうじしていた自分が嫌になった。
「うふふ、元気になったみたいね」お姉ちゃんも笑った。
私はその満開の笑みを見て、これからはお姉ちゃんに心配をかけないように強くなろうと決めた。
***
それから私は学校に再び通い始めた。
相変わらずいじめは続いたけれど、それをはねのけるように勉強に打ち込み、
運動部(お姉ちゃんと同じ、陸上部だ)に入って体を鍛えた。
細かった体に筋肉がついていくにつれて、いじめっ子達も私に一目置くようになり、
私は学校生活に馴染んでいった。
そして1年後。
お姉ちゃんが通う高校の入学式。
私はお姉ちゃんと、おそろいの制服を着て学び舎に向かう桜並木を歩いていた。
「今日から香織は私の後輩ね」
お姉ちゃんは相変わらず太ったままで、大きな体を揺するようにして歩いている。
並んで歩いているとかなり目立つ体形だ。
陸上部では太りすぎが原因で選手からマネージャーに転身していた。
その豊満な体とおだやかな性格もあって、
お姉ちゃんは部員達のムードメーカー的存在になっているらしい。
私は今でもお姉ちゃんをこんな状態にしてしまったことを後悔している。
高校では中学校の時のように陸上部に入部し、お姉ちゃんの分まで活躍するつもりだ。
「うん、よろしくね、先輩! それにしても……お姉ちゃん、また太った?」
にやりと笑う私の顔をお姉ちゃんは恥ずかしそうに小突いた。
「も、もう、気にしているのに。それは言わない約束でしょ」
マネージャーになってから体形に気を使わなくなったことで気が緩んだお姉ちゃんは、
好きな時に好きなお菓子を食べるようになった。
おかげで太ってからも体重は増え続き、先日120kgを突破した。
最近は膝が痛くて歩くのが辛くなってきたようだ。
それでも私の優しいお姉ちゃんに変わりはない。
ずっと、ずっと優しいお姉ちゃんに変わりはない。
「ところで、あの小男は一体何者だったんだろ……?」