334氏その16

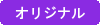
午前6時。学び舎には生徒達は登校してきていない。
広々とした校庭には雀が鳴いていた。
そこに表れた2つの影。
「『聖マリア女学園』。私立のお嬢様学校だ。ここに妖怪の気配がするね」
「それでは、今度の潜入先はこの高校だな」
ひとりは150cm足らずの小柄な少女。
もうひとりは2m近くある筋骨隆々の大男である。
「大里、今度は妖怪との戦闘に夢中になるあまり、建物を壊しちゃだめだぞ」
少女が大男を窘める。すると、大男は眉を顰め、少々罰が悪そうに反論した。
「仕方がないだろう、リリー。この間戦った妖怪は手加減して勝てる相手ではなかった。
油断していたらこちらが殺されていた」
「やれやれ、あの事件の後、僕が関係者の記憶を消したから妖怪の存在はばれなかったものの、
もっと優雅さが欲しいものだね」
少女が肩口で切り揃えた灰色の髪をかき上げると、朝日を受けて毛束がきらりと輝いた。
「100年に一人の天才魔術師である、僕のように」
「分かった、分かった。お前の術にはいつも感謝している」
大里はグローブのような手でリリーの頭を撫でると、朝靄の中に聳え立つレンガ造りの校舎に向き直った。
「それで、今度の妖はどんな奴だ?」
少女は両手の平を校舎に向けると、呪文を唱え、妖気を探った。
「一言でいうと…『乙女の敵』だな」
「どういうことだ?」
大里の問いかけに答えず、リリーは校舎の中に入って行った。
犬塚いつきが教室の扉を開けると、汗臭さと熱気が頬を撫でた。
生徒達から放たれる大量の汗と熱量のせいだ。
饐えた臭いに軽くえずいていると、中からでっぷりと肥えた女生徒が巨体を揺すりながらのしのしと歩いてきた。
「体調でも悪いのかしら?」
「あ…え、江頭さん。おはよう」
江頭さんの顔はてかてかと汗で光っている。
ブレザーのボタンは今にもはじけ飛びそうだ。一番大きいXLサイズの制服のはずなのに。
たった1週間前まで雑誌モデルとして活躍していたのが信じられないくらいの太りっぷりだ。
「もっと栄養を取って太らないとだめよ。あなただけそんなに痩せていて」
そう言って、購買部で買い求めたであろう揚げパンを手渡された。
汗まみれの手にずっと握られていたためか、パンを包んでいる油紙はしっとりと濡れていた。
「さすが、学級委員長! 優しいわ〜」
クラスメートが口ぐちに賛美の声を上げる。
彼女達は、程度の差こそあれ、ブクブクに太りきっている(江頭さんに比べれば、小熊サイズだけれども)。
皆、先週までは痩せていたはずなのに。
まるで自分が元から太っていたかのように振舞っている。
「さあ、朝礼が始まりますわよ。早く席にお着きになって」
あまり気が進まない。私は教室内の悪臭を嗅がないように口で息をしながら、席に着いた。
「うう、嫌だな…こんな学校。つい最近までは格式ある名門校だったのに、どうしてこんなことに」
「それは妖怪の仕業だよ」
「え?」
気が付くと隣に見知らぬ女の子が立っていた。
灰色の髪の小柄な子だ。ハーフだろうか。
「あなたは…誰?」
「おっと、自己紹介がまだだったね。僕の名前はリリー。今日からこの学校に転校してきたんだ」
リリーがほっそりとした手を差し出す。
「私は犬塚。よろしくね」
私たちは握手を交わした。
「しかし、この学校の女生徒は、キミ以外皆丸々と肥えているね」
「元は痩せていたんだよ。でも、ある日を境に急激に肥満してしまったのよ」
リリーの青い目がきらりと光った。
「ほう、それは興味深い。もっと詳しく教えてくれたまえ」
「それで、潜入の出だしはどうだ? リリー」
放課後の用務員室。リリーと大里は状況報告をしていた。彼ら以外には誰もいない。
「ばっちりさ。犬塚という気の弱そうな生徒に接触した。今後はその娘から色々と情報を仕入れるつもりさ」
「そうか、それは良かった。俺も用務員として学校に潜入し、妖怪が取り憑いていそうな職員及び生徒を探している」
「それにしても、大里。用務員の作業着が良く似合うじゃないか。妖怪退治屋から転職したらどうだい?」
「余計なお世話だ」
大里はぶっきらぼうに答えると、ポケットから煙草を取り出し火をつけた。
「リリー、俺の勘だが今度の獲物は手強い気がする。くれぐれも気をつけてな」
「何を言っているんだい。百戦錬磨の私の腕にかかれば、どんな妖怪だっていちころだよ」
リリーは発育の遅い胸を張った。
その様子を天井裏から盗み見ていた俺は、天井の戸板をそっと閉め、憑依している人間の元に帰った。