589氏その2

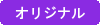
1
緑の培養液が入った巨大なガラス張りのシリンダーの中をピンク色のスライムがただよっている。
それを見ている白衣を着た研究者が二人。
一人はタバコを咥えた若い男で、もう一人は長い髪を後ろで束ねた女である。
ふわふわと浮いているスライムを見ていた男は、タバコを携帯灰皿に入れた後、
気だるそうに頭を掻いた。
「これかい?ポイントFで発見された怪生物ってのは?」
男の問いかけに女が背筋を伸ばして答えた。
「はい、田中主任。これが先日南極で発見され、調査のため当研究所に輸送された新種の生物、「G」であります」
「鈴木くん、なんだかやけに説明口調じゃないか」
「読者の方に状況を解説しなければなりませんから」
やけにメタい発言をする鈴木に田中は再度頭を掻いた。
「まあいいや。それで君がこの生物を調査を担当しているわけだが…
現在までの成果を報告してくれないか?」
「はい。実験の結果、「G」には刺激を与えると高濃度の糖分を生産することが分かりました。」
「それは素晴らしい!本部も大喜びだな。」
「はい。本部からも調査継続の指令がきております。ただ、それには少々障害がありまして…」
眉をわずかに落とした鈴木を見て、田中はほころばせた顔を歪めた。
「あー、いつもの所長の妨害か。調査費を出し惜しみしている…といったところかな?」
「その通りであります。所長曰く「本部の人間の指示は受けない。訳の分からない生物の調査には
これ以上費用をかけられない。」とのことです。」
「全く、本部の指令を無視するほどの彼女のワンマンさもどうにかならんもんかねえ。」
「どうにもならないであります。あの女はわがままで身勝手ですから。」
感情を表に出さない彼女には珍しく、鈴木は嫌悪感をまるだしにした。
(まあ、仕方ないか)
田中は心の中で一人ごちた。
所長である佐藤と鈴木の仲が悪いのは研究所の人間ならだれでも知っている。
良く言えば自由奔放、悪く言えば自分勝手な所長と規律と自律を重んじる鈴木は
磁石のN極とS極のようにことあるごとに反発している。
中間管理職である田中は癖の強い二人の板挟みになることが多い。
「分かった。調査費の追加の件については、俺から佐藤所長にかけあってみる。」
田中は三度頭を掻きながら部屋から出ていった。
2
「ダメよ、ダメ。追加の調査費なんてだせないわ。」
金髪を縦ロールにした女性が、手にしていた調査の中間報告書を無造作に机に投げ出した。
彼女こそ、研究所の所長、佐藤である。
「しかし、調査継続は本部からの指示なんです。命令違反は大問題ですよ。」
「大丈夫よ。本部長は私のパパだし。とにかく、私が嫌なものは嫌なの!」
研究所のトップの割に全く論理的でない理由でヒステリックにまくしたてる。
(よくこれで所長が務まるもんだ)
田中は吸っていたタバコを卓上の灰皿に擦りつけ、書類を手にとった。
「所長が嫌なのはよ〜く分かりました。
しかしですね、現時点でこの研究には著しい成果が出ているんです。
この研究を完成させれば研究所の責任者である所長の株もぐ〜んと上がりますよ」
「ふん!あの鈴木が担当している研究で株が上がるなんてまっぴらごめんよ。
もし成果が出たとしても本部に一番認められるのはあの女。
ならば、本部は私に換わってあいつを所長にするに決まってるわ。」
なるほど。所長が調査の継続を渋るのはその辺りが本音らしい。
優秀な鈴木に所長の座を取って換わるれるのが怖いのだ。
(ここはハッタリを効かせる必要があるな。)
田中は腕を組んでわざと大げさに言った。
「そいつは困りましたね。本部長は調査を継続させないとあなたをクビにすると言ってますが、
どうしても嫌なら仕方ありません。」
もちろん全くのデタラメである。本部長はそんなことは言っていない。
しかし、「本部長」と「クビ」という言葉に、所長は目を見開いて反応した。動揺している。
「パパがそう言ったの?」
「ええ」
部屋を出て行こうとする田中に佐藤所長が追いすがった。
「待って!分かったわ。パパの命令なら仕方がないわ。調査の継続許可をあげるわ。」
彼女はしぶしぶ許可書にサインをし、田中に渡した。
「ありがとうございます」
憮然とした所長を振り返って田中はにやりと笑い、部屋から出ていった。
田中が出て行ったあと、佐藤はいらいらと室内を歩きまわった。
「パパの指示とはいえ、研究が完成したあかつきには鈴木が所長に昇進するに決まっているわ。
せっかく、パパに頼んで所長にしてもらったのに…」
佐藤はマニキュアを塗った爪を噛んだ。
「なんとかして研究の完成を阻止する方法はないかしら」
ふと彼女の目が机の上の報告書に止まった。
「そうだ。あの女を再起不能にすればいいのよ。彼女の研究の成果を使って…ね」
佐藤は嬉しげに言うと、「G」が保管されている部屋に向かって走り出した。
3
佐藤は「G」が保管されている研究室の扉を開けた。
ぎしり…と重たい音が無人の部屋に響く。
「気持ちの悪い物体だわ…」
机の上に置かれた容器に入れられた「G」を見て、吐き捨てるようにつぶやく。
元来、彼女は不潔を極短に嫌う性格だ。
べとべとやねばねばは見たくもない。
しかし、今回はそうも言ってられない事情があった。
何せ、自分の職がかかっている(と彼女は思い込んでいる)のだ。
あの忌々しい鈴木を陥れるのなら、いくら我がままな彼女でも
多少の不具合は受け入れるだけの自制心は持ち合わせている。
道具棚を乱暴にあさり、実験器具を取り出す。
そして、ピンセットで容器から慎重に「G」をつまみだし、ペレット皿の上に乗せた。
蠢くそれを目の端で見ながら、そっとガラス瓶を「G」の下に近づける。
ピンセットで「G」の体表を刺激すると、「G」から透明な液体がピュッと吹き出し、
ガラス瓶の中に流れ込んだ。
液体の成分は鈴木の報告書にあった高濃度の糖分である。
「これをあの女のコーヒーに混ぜれば、あいつはみるみるうちに太っていくはず。
毎日少しずつ、そう、徐々にでいいのよ。1カ月も混入させれば、立派なおデブちゃん。
そうすれば、容姿が気になって研究どころじゃなくなる。自慢のおつむの働きも鈍るに違いないわ」
ぶつぶつと自分に言い聞かせるようにつぶやく彼女。
実際には肥満と頭の働きには必ずしも関係があるとはいえないのだが…佐藤はそう思い込んでいた。
思い込むことで現実から目をそむけることで彼女は生きてきたのだ。
「最低でも1Lは欲しいわね。ほら、もっと液を出しなさいよ!」
ピンセットで何度も「G」を突き刺す。
その都度、透明な粘液が体表から吹き出し、ガラス瓶に溜まっていく。
しかし…生態が未知であるとはいえ、「G」も一種の生物である以上、外部からの攻撃に対して
反撃しないはずがない。
佐藤は生物学者として基本中の基本であるその摂理を忘れていた。
突然「G]が血のような紅色に変色した。まるで彼女に警告するように。
だが、己の目的のために盲目になっていた佐藤は全く介さなかった。
「下等な生物の癖に生意気ですわよ!」
かまわずピンセットで突き刺し続ける彼女。
その時、「G]からねばねばとした1mくらいの触手が無数に伸び、彼女に巻き付いた。
「!?」
突然の事態に逃れようと身をもがく佐藤。
しかし、包み込んだ「G」は、まるでゴムのように伸縮性があり、千切れることがない。
言葉にならない悲鳴をあげている佐藤を、「G」が触手を平らに延ばし、
ゆっくりと包み込んでいく。
ほんの数十秒で佐藤の体は完全に覆われてしまった。
もう佐藤は声を発していない。口が塞がって声を発することができなかったのかもしれない。
研究室を静寂が支配する。
と。
ぶくり。
沈黙を破り、厚手のゴム風船が膨らむような音がして「G」の真っ赤な体表が膨張しはじめた。
さながら火であぶられた特大の餅のようだ。
それは近くにある机や椅子を押しのけ、天井に届くかというくらい大きくなった後。
びしり…と頂点が裂けた。
「ふぅー…ふぅー」
雌のトドのような声を上げ、中から出てきたモノ。
「G」のようにぶよぶよと太った、変わり果てた佐藤の姿だった。
白衣はびりびりに裂け、紐のように全身の肉に食い込み。
痩せていてきつめだった顔は脂肪でぱんぱんに膨れ上がり。
巨象ほどもあろうかという足を動かしながら。
急激な体の変化を気にも留めずに、彼女は「G」の亡骸から一歩を踏み出した。
「そうよ…あの女を太らせないと」
歩くたびに部屋全体がわずかに揺れる。
肉で弛んだ体を左右に揺すりながら佐藤は部屋を出ていった。
何かに操られているようにその目は虚ろだった。