肥満化ダンジョン

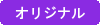
1.攫われた王女
とある王国にシルヴィアという名前のとても美しい王女様がいた。
腰まで伸びたブロンドの髪はしなやかで絹を連想させ。
整った顔は大理石の彫刻のようで。
メリハリの効いたボディは国中の男の憧れの的だった。
風呂に入る時は3人の侍女に自らの体を念入りに洗わせ、恵まれた容姿を彼女達に見せつけた。
朝の洗顔には真珠を溶かしたミルクで顔を洗い、肌の白さを際立たせた。
町を歩くときは露出の高い服を選び、男たちの視線を一身に集めた。
求婚してくる他国の王子や貴族は後を絶たなかったが、プライドの高いシルヴィア王女は全て断っていた。
いつか自分と同等の美貌を持つ男が見つかるまで結婚しないつもりだった。
「自分の容姿を鏡で良くみてみることね」
それが男を振る時の彼女の決まり文句だった。
ある夜、シルヴィアが王宮の寝室で寝ていると、その寝室に黒頭巾の男達が忍び込んだ。
男達はあっという間に彼女を抱きかかえると王宮の外へ逃げていった。
翌朝、気が付くと彼女は見知らぬ洞窟の中にいた。
「ここは…?」
かなり古い遺跡のようだった。
苔むした石の壁。
ひび割れて崩れた土器が散乱している。
壁の窪んだ場所にはところどころ松明が掲げられていて、
彼女を誘導するように擦り減った石の階段が洞窟の深部へと続いている。
振り返ると土の壁で行き止まりだった。
奥へ進む以外に道はないようだ。
「下に降りるしか選択肢はなさそうね」
しぶしぶ階下に向かって歩みを進める。
泥はねが靴にかかってとても嫌だった。
洞窟内は甘い匂いが充満していた。
焦がしたキャラメルのような香ばしい匂い。
その香りはシルヴィアの食欲を刺激した。
「そう言えば朝食はまだだったわね」
シルヴィアは早くこのトンネルから脱出し、王宮で温かい朝食を摂りたいと思った。
しばらく下っていくと開けた空間に出た。
先ほどまでの道とは違い、明るく開放的な場所だ。
天井に入った亀裂から柔らかな太陽の光が降り注ぎ広間を隅々まで照らしている。
床には赤いカーペットが敷かれており、長テーブルが中央に置かれている。
そして、そのテーブルの上には美味しそうな料理が所狭しと並んでいた。
琥珀色の野菜のスープ。
こってりしたソースがかかったウサギのステーキ。
香ばしい焼き色のパン。
具沢山のシチュー。
見るからにカップケーキ。
それらは空腹のシルヴィアを甘美な香りで誘惑していて。
シルヴィアの腹がぐぅ、と鳴った。
口内に唾液が満ちる。
「な、何を考えているのよ」と自分に言い聞かせる。
暗い洞窟に不自然なほど豪華な料理。
明らかに怪しい。
「食べるわけないんだから…」
広間の出口に向って歩き出す。
「どこの誰が作ったかも分からない料理だなんて」
再び腹が空腹を訴えて鳴った。
歩く速度が鈍る。
「でも…腹が減ってはなんとやらだし…」
足が止まり、
「でも…でも、パンの一切れくらいなら…いいわよね」
と踵を返すシルヴィア。
テーブルの前にあった木製の椅子に座る。
パンを一口齧ってみた。
「あら、美味しい…」
表面はカリカリで中はもっちりと歯ごたえがある。
ほのかに香るバターの香りが食欲をそそる。
二口、三口、続けて頬張る。
噛めば噛むほど甘味がにじみ出てくる。
恐る恐る食べ始めた料理だったが毒が入っていないことが分かると
他の料理も食べてみたい気持ちが湧いて来た。
口内に唾液がこみ上げてきた。
「こっちのスープも美味しそうね」
スプーンを手に取り琥珀色のスープを口につける。
動物の油が使われているのだろうか、こってりとしていながらもしつこい味ではなく何杯でも飲めそうだ。
カップケーキにも手を伸ばす。
狐色に焼かれたマフィンの上にたっぷりと生クリームがかけられている。
頬張ると強烈な甘味が頭の芯まで染み渡った。
「ん、美味し」
次々に口に料理を運ぶシルヴィア。
今度はステーキに手を伸ばす。
ナイフとフォークを使って上品に切り分けていく。
「んぐ、もぐ…おいふぃい。こんな美味しいの初めて」
口周りをソースで汚しながら次々に平らげていく。
少々はしたないと思われるテーブルマナーだが、この時は何故かシルヴィアの意識は
料理を食べることのみに向いていて。
よく観察すれば、料理を食べ終わった皿の上に新たな料理が出現していることに気づけたはずだった。
しかし、食事に夢中のシルヴィアは手あたり次第に出現した料理を食べ続けている。
勝手に料理が補充されること自体が異常なのだが、溢れ出る食欲が知性より勝っているのだ。
「食べても食べてもどんどん出てくるわぁ?」
食べ始めてから1時間後。
なおもシルヴィアの食欲は衰えない。
そして――食べた料理はすぐに消化され、即座に脂肪となって体中に付き始めていた。
元々豊満だった胸はボリュームを増して、大きく開いたドレスの谷間から零れ落ちそうなほど育っている。
砂時計型だったウエストラインは下ぶくれした緩やかな肉の段に変貌していて。
下腹部はぽっこりと数センチほどせりだしている。
太ももも2周りほど大きくなり、そのシルエットは柔らかな曲線で。
臀部は横に肥大して、立派な安産型になっていた。
スレンダーだった彼女の体はぽっちゃりとした体型に変貌していて、
以前とは違った豊満な色気を漂わせている。
「はぁぁ、こんなに食べていいのかしら。こんなに食べて…?」
そこで言葉を詰まらせるシルヴィア。
自らの肉体の変貌を見て正気に戻った。
「あ、わ、私は何を?!」
肥大した自分の肉体にシルヴィアは困惑した。
テーブル上に溢れんばかりに並べられていた料理の数々が贅肉となって
節制を保っていた己の体についていたからだ。
空になった皿の数を数えると数十皿はくだらないだろう。男の軍人5人分くらいの食事量だろうか。
完全に管理されたシルヴィアの食生活から考えると絶対に摂取しない量のカロリーである。
幾分丸みを帯びた頬に一筋の冷や汗が流れる。
頭の中の霧が晴れたように思考能力が戻ってきた。
「料理に魔法がかけられていたのかしら」
料理が無限に出てくる魔法と、おそらくは食べたものの食欲を増幅させる魔法?
その魔法をかけた術士が誰かは分からないがシルヴィアはまんまとその者の罠にかかってしまったのだ。
料理にがっついていた自分の痴態を思い出してしまい、シルヴィアは全身から火が出るようだった。
「この私がこんな醜態を…!」
歯ぎしりするも身に付いた脂肪が燃えてなくなるわけでなく。
魔法をかけた術士を絶対に探して出して代償を払わせてやると固く誓い、
洞窟を更に深く潜って行くシルヴィアだった。
2.新たな仲間
「フゥー…ハァ…あ、暑い」
暗いトンネルに息切れの音が響く。
その主は一歩一歩階段を下りていくシルヴィアだった。
「なんでこんなに暑いのよう」
先ほどの大広間より明らかに気温が高い。
洞窟内は湿度も高いため体感温度は30℃くらいだろうか。
おまけにたっぷりとついた脂肪が毛布の役割を果たしており、シルヴィアは全身に滝のように汗をかいていた。
ドレスには黒々とした汗染みができていて、その生地がぺたりと体に張り付いている。
おかげで丸っこい体の線が強調されている。
「も、もうダメぇ…」
その場で尻もちをついて座り込む。彼女の体重で洞窟の天井からパラパラと石片が落ちてきた。
「もう動けないわ。膝も痛いし」
増えすぎた体重のせいで膝に予想外の負担がかかっていたようである。
その時、洞窟の奥の暗がりから足音が聞こえた。
「誰…?」
身構えるシルヴィア。危害を加える敵かもしれない。
足音は次第に近づいてくる。少し重みを感じる足音だ。こちらに向かってきている。
「誰なの!?」
暗がりの向こうから近づいて来たのは長身の女性だった。
180cmはあるだろうか。
銀色の長い髪に赤い目。
多少ボリュームはあるものの均整のとれた肉体。
シルヴィアとはまた違った怜悧な美貌の持ち主である。
女は黒い服を着ている。シルヴィア達の隣にあるバルト帝国の軍服だ。
無言でシルヴィアに近寄ると、ギロリと睨んだ。
「な、何よ…!」
「やっと、仲間がいた…」
女は目の端に涙を浮かべた。
「へ?」
「このダンジョンで迷い続けて1週間。一生このままかと思っていたがよもや同じような人間がいたとは」
「ちょっと待って、わ、訳が分からないわよ。まずあなたは誰?」
「あ、ああ。取り乱してすまない。私の名前はラウラ。バルト帝国の騎士団長をしている」
ラウラは涙を拭って平静を取り戻した。取りあえず悪い人間ではなさそうである。
「私の名前はシルヴィア。あなたの隣国の王女よ」
「噂には聞いているぞ。我がバルト軍人の中でもあなたの美貌を知らない者はいない」
「それはどうも。けれど、帝国の騎士団長がどうしてこんな場所にいるの?」
「私にも分からないのだ。覆面を被った男たちに襲われて気づけばここにいた」
とラウラはそこで言葉を切り、シルヴィアの体型を少し見た。
「あなたも…食べたのか? あの料理を」
「…まあ、ね」
「そうか。あの誘惑に負けて私もこのようなだらしない体になってしまったのだ…」
「? あなたはそれほど太っていないじゃない」
「…見るか? 1週間の暴飲暴食の結果がこれだ」
ラウラは上着をたくしあげた。
そこには今のシルヴィアを優に超える太鼓腹が鎮座していた。
ラウラが息をするたびにボヨンボヨンとわずかに弾む。
ウエストは100cm近くだろうか。
「うわ、すごい」
「そんなにじっくり見ないでくれ。私にもプライドというものがある…」
ラウラは俯くと頬を赤らめた。
よくよく見るとラウラの体は体型を保っているというよりも服に無理やり贅肉を押し込んでいるという感じだ。
その証拠に服の皺ができているところには深い縦皺や横皺ができている。
おそらく弾力性のある服で強引に体型を保っているということだろう。
「これ以上は…さすがに見せられない」
「気持ちは良く分かるわ…」
「済まない。まさか自分が下半身太りするタイプだったなんて…」
「体重は?」
「…聞くな」
二人は同時にため息をついた。
「ともかく! 私は何としてもこのダンジョンから脱出し祖国に帰らなければならん。
こんな姿でくたばっては騎士の名折れだ」
「私もよ。ここから脱出して私を罠に嵌めた奴に思い知らせてあげる…!」
「なら、目的は一緒だな」
「そうね」
二人は力強く手を握った。
「「絶対に脱出してやる!」」
こうして洞窟から脱出するという目的が合致したシルヴィアとラウラだったが…
洞窟を再び進み始めてから数分後、2つに分かれた分岐路にぶち当たってしまっていた。
「右の道か左の道、どちらに進もうか?」
ラウラは腕を組んだ。
風が吹いてくる道が出口に繋がっているのが常識だが。
「どちらからも風…というか匂いが漂ってきているな」
右の道からは甘い香りが、左の道からは香ばしい匂いがする。
どちらに進むか決めあぐねていたラウラは、ふとシルヴィアの様子がおかしいのに気が付いた。
「ん? シルヴィア。腹を抑えてどうかしたか?」
「べ、別になんでもないわよ!? 甘い匂いにつられてお腹が空いて来たとかじゃないんだから!」
「…」
「ちょっとぽっちゃりしちゃったけど、さ、さすがに心まで堕落しちゃいないわ」
と言いつつもシルヴィアの腹の虫が再び鳴った。
ラウラは大きくため息をついた。
「いいか。この洞窟は私達を太らせるために様々なごちそうが仕掛けられている。
食欲に負けてトドのような姿に成り果てたいのか?」
シルヴィアは全力で左右に頭を振った。
「なら、自制の心を持つことだ。食欲なぞ気合いでいくらでも我慢することができる。
この私のようにな!」
ラウラは胸を張った。が、その腹が大きな音を立てて空腹を訴えていた。
「…」
「そ、そ、そんな目で見るな!
別に香ばしい匂いのする左の道に行きたいな〜、とか考えていたわけじゃないんだからな!」
今度はシルヴィアがため息をつく番だった。
「どちらにしても進む道を決めなきゃいけないんだし、ここは二手に分かれて行くってことにしない?」
「二手?」
「そ。どちらかが出口を見つけたら脱出して外に救援を呼べばいいでしょう?
万が一、進んだ道が行き止まりだったら引き返してもう片方の道を進めばいいじゃない」
「お、おお。そうか。頭いいな、お前」
「ラウラは左の道に進みたいみたいだし私は右の道にするわ」
「その決め方は私が香ばしい匂いにつられたみたいで大変不本意なのだが…。
仕方ない、幸運を祈るぞ」
こうして二人は二手に分かれて探索を進めることになった。