315氏による強制肥満化SS
前へ 1/3 次へ

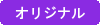
ここは、西寄りの広大な土地にある豊かな村。
この村の人間は普通とは違い寿命がとても長く、60歳で中年、といった具合である。
村というにはあまりに大きく、水車の横には小川が流れ、景観に富み、畑では小麦が金色に輝き、小高い丘には思い思いの豪邸が佇んでいる。
村には年中、ここ千年の間ほどはずっーと、笑い声と葡萄酒のにおいが溢れ返っていた。その中でも一際目を引く大豪邸、この村一の地主の家だ。
ここの娘は本当に聡明で、気立てがよく誰からも好かれていた。
髪はブロンドで少し長く、癖がついており、目はすぐ近くを流れる小川のように青く澄んでいた。
また、背もその辺の男よりは少し低いだけですっと伸びており、容姿端麗、村一番の美人である。
しかし、ここの一族は代々冒険家の気質があり、活発で好奇心が多く、村の大半からは変わり者だという風にも見られていた。
この大邸宅の中に彼女が見える。中で何か騒いでいるようだ。
「ちょっと!?なんですか・・・これは・・・!?」
家ではぷっくりとした、愛らしいとも美しいともいえる女性が大声を上げてパニックを起こしていた。
今にもその体に不釣り合いな服を破ってお腹がはみ出してきそうである。
元々は体のラインに沿ってピッタリに作られていたドレスによりぎゅうぎゅうと締め付けられていて、とても苦しそうだ。
「お嬢様、どうか落ち着いて!!」
召使たちが慌ててなだめる。
召使の一人が彼女のお腹の裂け目あたりからこの拘束具を破いた。
すると「ボルンッ」という音が聞こえてきそうなほど勢いよく、大邸宅の大広間のど真ん中に、白く柔らかそうで上等なパンのような真ん丸のお腹が、みんなの目の前に姿を現した。
「ぶふーっ!!・・・はぁ、はぁ・・・ありがとう、ございます・・・ふぅ」
よほど苦しかったのか、空気を抜いた風船のように勢いよく息を吹き出した。しかし、今なお苦しそうに呼吸をしている。
そんな彼女を心配そうに見つめる召使たちの視線を我に返った彼女が追ってみると、目の前にまん丸い丘が三つ、その一つはとりわけ大きく、激しく息をするたびに波打っている。
そしてなぜかそれだけ、いつも見ている自分の肌のように真白く美しい色をしていた。
「・・・!?///」
ようやく事態が呑み込めた彼女は顔を真っ赤にして、後ろ向きに崩れ落ちてしまった。
すると、お腹同様大きく膨らんだお尻が足や床に当たり、そのプ二ッとした感覚と、肉が潰れて少し気持ちよくなってしまった感覚とで、まだ気づかれていなかったその存在を現した。
「あっ!///」
思わずこんな声を上げてしまい、とてつもない羞恥の嵐が押し寄せてきた。
急いで立とうとはしたが力が入らず、両手を後ろにつき、重みにプルプルと二の腕を揺らしたまま、しばらく立ち上がるための体制を維持した。
顔は更に赤く染まっていった。
バランスを取り戻し、そこから一気に立ち上がろうとしたが、デン!と突き出たまん丸いお腹がつっかえて、またその重みによって阻止されてしまった。
お腹ほどではないにしろ、大きく育ってしまった二つの胸が彼女の視界を妨げていたのも一要因である。
一連の行動ですっかりへばってしまい、今は仰向けに寝っころがっている。
「ふーっ!ふぅ・・・ぶふぅ・・・」
という普段からは想像もつかないような暑苦しく情けない低音の吐息を漏らしてしまった。その音を鳴らすたびに、横になってもなお大きく突き出たお腹が上下に伸び縮みを繰り返し、彼女の顔を真っ赤に染める。
汗だくになり、かつ真っ赤に高潮している彼女は何ともエロティックである。
まあそれもこの手のものが趣味であったらの話で、まだかわいらしく、ギリギリ美しいとも言えなくはないその体つきは、一般の人が見たら良くても抱き枕にしたらやわらかそうだ、と思う程度だろう。
唖然と、あるいはその一連の行動に見とれていたのか、同情したのか、顔を真っ赤に染めていた従者たちは、はっと我に返り、わが家主の令嬢を、優しく丁寧に、そして大きな株でも引っ張るかのように力強く思いきり、力を合わせて立ち上がらせた。
今日は彼女の誕生日。村を上げて盛大なお祝いをする毎年の恒例行事である。村中から贈り物が届いたのだが、その中の一つがこの騒ぎの原因になっていたようだ。
「なんでよりによって自分の誕生日にこんな目に合わなければいけないの・・・」
少し落ち着いた涙目の彼女を召使たちが看病している。
というのも、彼女が贈り物の山に積まれていた指輪に興味を示し、指にはめてみたことが事の発端である。
指輪はいともシンプルで、何の装飾も施されてはいなかったものの、黄金一色に光り輝き、見る者を魅了するような不思議な魅力を放っていた。
それを彼女が魅入られるまま指にはめてみた途端、体がぷっくりと膨らんでしまったのが事の次第である。
まあ、ぷっくりというのはまだ柔らかい表現で、実際には彼女の見事な体のラインをことごとく崩し、服を拘束具に変え、ふーふー息苦しくなるほどには太っていた。
指にはめた指輪は、指がぷくぷくと太くなったにも関わらず、なぜかそれに合わせて大きく変形したかのように、指を絞めつけもしなかったし、すっと簡単に抜けてしまった。指から抜けると指輪ははめた時と同じサイズに戻った。
それと同時に彼女の体のサイズも元に戻ったのだからまた不思議である。
このようないきさつから、原因が夕べのドンチャン騒ぎの前夜祭によるものではなく、指輪のせいであることが判明したのである。
また当たり前の話ではあるが、はだけ(はじけ?)てしまった彼女お気に入りのハレ着であるドレスはもちろんそのままである。
しかし、本人も召使たちもほっと胸をなでおろしていた。もう二度とあんな思いをするのはごめんだ、と彼女は思い出しては赤面しそう思っていた。
なんでもこの指輪は村人からの贈り物ではなく、ここの家主である彼女の義父が誕生日のサプライズにプレゼントしようと思っていた、昔の冒険で見つけた宝物だったのだ。
それには姿を消す魔法が込められており、幾度となく彼の冒険に貢献してきたのだ。
しかし、それは男が使ったらの話で、どうやら彼女のような女性には別の能力が与えられていたようだ。
なんでも義父はもう少ししたら旅に出るらしく、もう故郷に戻ってくる予定はないのだという。
そのため、家財や資産をすべて彼女に託し、愛娘のハレの日を祝ってから出発するつもりだったそうだが、とんだ騒動になってしまったようだ。
彼は娘に平謝りし、機嫌も治ったところでつつがなく、村を挙げての盛大なパーティーが催された。
パーティーにはある老人が来ており、旧友の娘の誕生日だと聞いてすっ飛んできたのだという。
彼はみんなが見たことも聞いたこともないような技を持っており、それを今日でいう花火というような形で巧みに披露した。祭りは大盛り上がりだった。
その最中、彼女の義父はキリのいいところでふっと自宅に戻り、整えておいた旅道具を背負って、娘にも内緒で例の旅に出た。
後にそのことに気付いた彼女はとても寂しがったが、すぐに立ち直り、義父に変わり村の長としての務めを果たしていくことを誓ったのだった。
それからしばらくして、例の指輪のことも頭の片隅にしか残っていないような長い年月が過ぎたころ(といってもここの人間は寿命が長いため、外見も内面も対して変わりはないが)。
大切なものを入れる箱の中から、この世の全てを射止めるような美しくも儚い魅惑的な輝きが、辺りをうかがっていた。
まるで指輪そのものに意志があるかのように。
ある日の夜、義父の古い友でもある仲の良い老人が突然訪ねてきた。
彼女は前もって知らせてくれていればそれなりのもてなしを用意していたのに、と老人との久々の再会を喜んだ。
しかし、老人はどうも険しい顔つきをしている。
そして不意に、彼女が義父から譲り受けた指輪のことを尋ねた。
彼女は少し不思議に思いながらも、大切に保管していた指輪を箱から取出し老人に渡した。
すると、老人はあろうことかその指輪を保管していた封筒ごと指輪を炉の中に放り込んだではないか!
突然の出来事に驚いた彼女は
「なにをするんです!?」
と少し声を荒げて老人を問い詰めたが、老人は炉の中をじっと見つめるばかり。
そして、老人が不意に炉の中にしばらく放置しておいた指輪を取り出し、「熱くはない」といい彼女の手のひらに置いた。
「何か見えるか?」
と老人は聞いたが、
「いえ、何も・・・」
と彼女は答える。
老人は「取り越し苦労だったか」と内心ほっとしたが、彼女が放った一言でその考えは消えうせた。
「何か文字が見えます・・・エルフ文字みたい」
老人は彼女に文字の内容と事の次第、暗黒の王の復活の話などを彼女にすべて打ち明けた。
恐ろしくなった彼女は指輪を老人に託そうとしたが、彼は断固として拒否した。
厳密にいうと、彼はその指輪をのどから手が出るほどに欲していた。
しかし彼の理性がそれを受け取ることを拒んだのである。
老人は彼女に指輪を安全な場所、エルフ族きっての実力者の住まいである谷へと持っていくよう指示した。追手がいつ来るかわからない今、今夜にでも出発するようにと。
その時であった、庭のほうで「ガサッ」と音が聞こえた。二人の背筋に真冬の山々よりも冷たい風が走る。
老人は杖を構え、ゆっくりと窓の方へ近づいていき、狙いを定めて茂みの中を小突いた。
「イテッ!」
老人が声の主をむんずと引き上げた。
「だれかと思えば庭師のサン!盗み聞きしていたのか!」
「ご、誤解です!盗み聞きしてたなんて・・・庭の草を刈ってただけで、ほんのちょっと、暗黒の王が世界の終りとか、それだけですよ・・・」
茂みに隠れていたのは屋敷の召使い、サンであった。
こんな夜中に草を刈っていたというのはもちろん嘘で、こういう話に目がない彼は茂みの中でずっと聞き耳を立てていたのだ。
「お願いです。俺を何か変な生き物に変えちまったりしないでください・・・」
そう、この老人は少しばかり名の知れた魔法使いなのである。
とはいえ、全く知らない者もいるにはいるが、それ以外の者には高名な大賢者として崇められている。
しかし、この村では魔法使いといえば厄介ごとを運んでくるものだと思われており、村人の幾人かにも彼を毛嫌いする者がいた。
そうでなくても何をしでかすかわからない未知の存在として恐れられている傾向もあった。
彼の発言は、まさにそういった考えが凝縮されて口に出たものであった。
「嫌か?それならばおぬしの主人の共をすることじゃな」
こうして一行は旅に出た。しかし、すぐに老人とは別れた。
なんでも魔法使いの先輩にこの事態についての助言を乞いに行くのだという。
道中、なんやかんやで彼女の従兄弟であるメルーとペペンが仲間に加わり、追手の追跡を逃れながら旅を続けていた。
いま彼女たちは丘の麓に建っている、とあるおじいさんの家にいる。事の次第はこうである。
彼女たちはある森の中を横切ろうとしたが、暴れる木や幽霊による妨害を受けていた。
「だからこっちの道は嫌だといったのに!」
木の枝に抓まれブンブン振り回されているサンが、道筋の提案者である彼女のいとこたちに怒鳴る。
「近道なんだから別にいいだろ!」
いとこも負けじと怒鳴り返す。残りの三人は今にも木の幹の中に取り込まれそうだ。
このままでは弄ばれて死んでしまう。
だれもがそう思ったその時、彼女の体が突然膨らみだした。
「え?な、なに??」
「おい!お前、なんかでっかくなってないか!?」
彼女の体は、指輪もはめていないのに急にぶくぶくと太りだした。
「い、嫌ぁ!」
こういいたかったのはむしろ木の方であろう。彼女の体は瞬く間に膨らみ、閉まりかけていた木の幹に隙間を作った。
そこから従兄弟たちは逃げ出したが、彼女の方は相変わらず、先ほどよりも狭くなった幹の中に取り残されている。
膨らむのは止まったものの、幹に空いた穴に蓋をするような形ではまってしまった彼女はとても苦しそうにしている。
思わぬ大物に、木の方も幹がビシビシと嫌な音を立てていて、今にも破裂しそうだ。
むしろ彼女よりも木の方が苦しいかもしれない。
「だ、だすけてぇ・・・ふぅー、ぐっふぅ・・・」
圧迫されている体に何とか隙間を作ろうと身をよじるが、ぴっちりとはまってしまった彼女の体はどうにも動く気配がない。
突然のことに動揺した一同があたふたしていると、突然、どこからともなく軽快な歌が聞こえてきた。
するとどうだろう、木は突然おとなしくなり、真ん丸に張りつめていた彼女の体が萎んでいくではないか。
元の体に戻った彼女を、木が「ぺっ」と勢いよく吐き出した。
歌の主はこのあたりに昔から住んでいるおじいさんであった。
彼の歌には強い魔法が込められており、どんな呪いも緩和してくれるのだという。
一行は彼に手厚く保護されて、しばらく休息を取った後、一行はお礼を言い再び旅に出た。
おじいさんは一行の姿が見えなくなっても見送りの歌を歌い続けた。
その歌のおかげで再び幽霊焼きに襲われることもなく、難なく森を抜けることができた。
一体この間のあれはなんだったんだろう?
一行が森での一件を話し合っていた。
なぜ彼女が突然太りだしたのか。話題はそれでもちきりになった。
能力の話はサンが老人から聞いており、その又聞きで従兄弟たちにも周知のこととなっていた。
その疑問の答えはすぐにわかることになった。
おじいさんの見送りの歌が聞こえなくなり、しばらく歩を進めていると、再び何の前触れもなく彼女が太りだしたのである。
最初は何事かと思った一同であったが、数分もしないうちに元に戻った。
その後も、時間や程度に開きはあれど、発作的に肥満化が起こったのである。
長い年月を指輪の近くで過ごした彼女の体は徐々に蝕まれ、指輪をはめていなくても太る体になってしまっていたのだ。
それがピークに達したのがつい先日の事件の日だったというわけである。
その後も、少しぽっちゃりから歩行が困難になるレベルまで、太っては戻り、太っては戻りと、不規則で幅広い変化が見られた。
全く変化が見られなければ、数日そのまま、ということも多々あった。
その変化のたびに彼女は「わぁ!?」だとか「うごぉ!」だとか「うっぷぅ・・・」「ぶふぅ!」「ぐっ・・・」などと喘いでいた。
最初は好奇の目で見られていたが、いつしかそれが当たり前のようになっていき、ただ黙々と歩んでいた。
しかし、彼女の方は、とてもじゃないが無心で歩いてなどいられなかった。
不定期に太ったり戻ったりする体での旅に悪戦苦闘しいる様子だ。
良いときはふっくらする程度だが、悪ければ自分のデーンと突き出たお腹で前が見えないのだ。
それに加えて全身の肉が、歩くたびにゆさゆさぷるぷる揺れるため、何度かズシンと重いしりもちをついた。
一人で起き上がれないときもあった。
その時は引き上げてもらうか、それが無理な時は休憩をはさんだ。
そしてなりよりも嫌だったのが屈辱的だということである。
元来、だれもが羨む才色兼備であった彼女は、他人に醜態をさらしているというのが許せなかった。
それに、年ごろの女の子が自分がでっぷりと太るのを快く思うわけがない。
たびたび訪れるズッシリとした重みと羞恥心により、彼女は旅の終始、涙目の顔を真っ赤に染めていた。
前へ 1/3 次へ