◆nTUiVpCzdQ氏による強制肥満化SS
『念力発電』
前へ 1/4 次へ

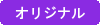
01
それは一瞬の出来事だった。
突然の地震によって建設中に破棄された骨組みから鉄骨が外れ、十数メートル下の少年に向かって落下した。
あんなものの下敷きになったら確実に死んでしまう。
――っ!
後先を考える暇などなかった。
咄嗟にセーリュは右手を突き出して意識を集中させる。
すると鉄骨は急に落下速度を遅め、少年の頭上数センチで停止した。
全身から冷汗を流しながらもセーリュは集中力が途切れないように右手を横に動かす。
鉄骨は少年を避けて地面に落ち、驚きのあまりか終始棒立ちになっていた少年は腰を抜かしてその場に座り込んだ。
セーリュは手に持った買い物袋を置いて、尻餅をついてただ唖然とする少年に駆け寄る。
「大丈夫!?」
「……」
漸く我に帰ったのか少年はセーリュの問いに顎を引く。
「う、うん」
「よかった……」
セーリュはホッと無い胸を撫で下ろした。
そして少年は自分の隣に横たわる鉄骨を見つめ、そして再び鉄骨が振ってきた骨組みを見上げる。
「お姉ちゃんって、念力が使えるの?」
そこでセーリュは自分がしてしまった事の重大さに気付く。
子供を助ける為とは言え、念力者がその力を使う事は重罪である。
仮にクレイドル・ポリスに知られたら厳重な処罰は免れない。
最悪、死刑すらありうる。
だが、幸いにもひと気の無い路地だった為、この少年以外にセーリュが力を見たものはいないはず。
セーリュは少しだけ怯えていた少年に優しくもあざとい笑顔を見せた。
「そう、だから誰にも言わないでね」
はっきりと念力を使うところを見られた以上否定するのも意味がないと感じ、セーリュはそう言った。
「うん……わかった」
「ありがと」
頷く少年の頭を撫でるセーリュ。
どのみちアウターの人間なら同じアウターの市民をクレイドルに売り渡す事などしないだろう。
「立てる?」
セーリュは少年に手を貸して立たせると、彼の服の埃を叩き落とす。
「ありがと、おねえちゃん」
少年は俯いたままそう呟くと、どこかへと駆け出していった。
「気をつけてね〜」
去っていく少年に手を振りながら、ふと妙な不安が胸を過ぎる。
――まあ、大丈夫だよね。
きっとバレはしないだろうと自分に言い聞かせ、セーリュは買い物袋を拾い上げて帰宅をする。
02
地下都市フェテュスを照らす人工太陽の光が窓から差し込み、セーリュは目を覚ました。
「うん……ううん、うわっ!」
――いてててて。
ベッドから転げ落ち、痛むお尻を摩りながら窓を開くと、外の騒音とオイルの臭いが狭い屋根裏部屋を充満する。
百数年前、大戦によって極限まで汚染された地上から逃げるように人々はこの地下都市へと移民した。
元々工業地帯として開発されていたこの地下都市はロクに資源もなく、キャパシティーを遥かに超える人口が生み出す貧困と犯罪に悩まされ続けている。
それが、セーリュの住まうアウター。
それと対を為すのがフェテュスの中心部にある巨大な壁に囲まれた地域――クレイドル。
クレイドルに住まうフェテュスの権力者たちはひたすらアウターの人間から摂取を続け、自らは何一つ苦労のない生活を送っている。
もちろんアウターの人間がクレイドルに入る事は許されておらず、クレイドル・ポリスによって日々弾圧が続けられていた。
資源も力も持たないアウターの人間は逆らう事も出来ず、ただその身を削りながら働き続けるしかない。
だが、幸いにも今日は週に一度の休日であり、工場に出向かなくていい。
つまり、今日は孤児院のお手伝いに専念出来る。
上機嫌なセーリュはハミングしながらボサボサの金髪をブラシで解かし、顔を洗って歯を磨くとパジャマを脱いで家事用のボロボロのワンピースに着替える。
「また風通しが良くなっちゃったな〜」
わき腹辺りに開いた虫食い穴に指を突っ込みながらセーリュは顔を軽く顰める。
ワンピース自体も最近背が伸びたせいか尺が足りなくなっており、太もも辺りまでしか届かなくなっている。
これではワンピースと言うより歓楽街のお姉さんたちが着るドレスに近い。
「……とは言っても新しい服作る素材なんてないし」
最後に上からエプロンをして、部屋を出る前に自分の姿を鏡で確認した。
ちょっとクセっ毛のある金髪のショートヘアーに大きく青い瞳と小さく整った鼻口。
院長のマルタを初めとして大人にはよく綺麗だと言われるが、問題は体系。
小枝のような華奢な手足に、まな板のような胸。そしてくびれとは無縁の腰周り。
身長が伸びるばかりで、肉体のボリュームは12歳頃から変わっていないような気がする。
もっとも、常に食糧不足で悩まされている状況で発育がよくなるはずもないが。
――でも、いくらなんでもこれはないよね。
「って、朝からネガティブになりすぎだって」
両頬を叩いて気合を入れると、セーリュは屋根裏部屋から降りていく。
子供たちの寝室が並ぶ二階の廊下を歩いていると、反対側から見覚えのある顔が向かってきた。
「おはよー、セーリュねえちゃん」
眠たそうに目を擦りながら六歳ほどの少年はそう言う。
「おはよ、ライくん。さっ、もうすぐ朝食だから顔洗ってきてね」
「う〜ん」
ボーっとするライの背中を優しく押すと、彼はよろつきながら洗面所へと向かっていった。
そう言えば昨日助けたあの少年はライと同じ年頃だった。彼に家族はいるのだろうか。
そんな物思いにふけながらセーリュは食堂へと降りていく。
「おはようございま〜す」
「おっ、おはよ!」
キッチンに入ると、そこでは大柄な中年の女性がすでに朝食の準備を始めていた。
彼女がこの孤児院の院長を勤めるマルタである。
「せっかくの休みだしもっと寝ててもいいんだよ」
「いいんです、マルタさん一人じゃ大変でしょ」
セーリュはカウンターに置いてある味付け用の野菜を手に取ると、戸棚からまな板を取り出して包丁で刻み始める。
「わるいね」
「マルタさんの為なら何でもオッケーです」
セーリュもまた赤ん坊の頃にここに預けられた孤児であり、16歳となった今は一人の大人として工場で働きながら孤児院の手伝いをしている。
「しかし、食べ物は高くなる一方で親のいない子は増えるばっかりだし……いつまでこうしてやってけるんだろうねえ」
不安な表情をするマルタに、セーリュは野菜を切りながら言う。
「大丈夫ですよ。私がいますし、それにアレンやロニーもそろそろ仕事が出来るようになる年頃だし」
「――そうだわね、何を心配してたんだか」
マルタは大げさに笑い、セーリュの背中を叩く。
すると急にセーリュの腹が鳴った。
「あら、随分とお腹減ってるみたいね」
「す、すいません」
凹んだお腹を押さえながら照れ笑いするセーリュ。
念力を使うと何故か決まって空腹に襲われる。おまけに昨日は夕食を食べていないので尚更だ。
「しかたないわね、ちょっとつまみ食いしちゃう?」
マルタはお玉を取ると、ストーブにある大きな鍋で煮込んでいるスープをよそった。
「ほら、おいしいわよ。いつもと同じのだけど」
香ばしい匂いのするスープが入ったを押し付けられ、セーリュは苦笑する。
「いや、そんな、大丈夫です」
「ほら、遠慮しない。アンタだってまだ育ち盛りでしょ。そんな痩せ細ってたらいい男も寄ってこないよ」
「別にそう言うのはいいですし……私はみんなと一緒に食べるんで大丈夫です」
マルタは不満そうな表情を見せるものの、すぐに満面の笑みになる。
「まったく、謙虚な子なんだから。まあいいわ、それだったら今から朝食にするから子供達を呼んできなさい」
「はい!」
セーリュは頷き、二階へと向かっていった。
賑やかな朝食が終わると、セーリュは床掃除を始めた。
一回の廊下が終わったところでチャイムが鳴り、扉へと向かっていった。
「はーい、いまいきま〜す」
セーリュは意気揚々と扉を開けるが、その瞬間全身が固まった。
「……っ」
目の前に立っていたのは青い軍服を着た二人の屈強な男性。
肩の紋章から間違いない。クレイドル・ポリスである。
急に胃がキリキリと痛み始め、心拍数がどんどん上昇していく。
すると片方の男が口を開いた。
「セーリュ・ライトだな。一緒に来てもらう」
理由も教えず、拒否も許さない。それがクレイドル・ポリスのやりかた。
だが、理由は分かっていた。どうやってか昨日念力を使った事がばれたのだ。
念力を駆使すれば何とかこの場は逃げる事が出来るかもしれないが、そうすれば連中はマルタや子供達を人質にするだけだ。
「ちょっと、どうしたの?」
慌ててマルタが駆け寄ってき、玄関に立つ二人の兵士を見つめると、何が起こっているのか気付いたかのように真っ青な顔になる。
「セーリュ、アンタもしかして……」
悲惨な表情をするマルタに振り向き、セーリュは必死に涙を堪えながら言う。
「男の子の上に鉄骨が落ちてきて……どうしても助けたくて……ごめんなさい」
「こい」
会話をぶった切るように一人の兵士がセーリュの腕を掴み、彼女を引っ張った。
当然口答えは出来ず、セーリュは抵抗せずにクレイドル・ポリスに連行される。
03
一体どれくらいの時間が経ったか分からない。
クレイドル・ポリスに連行されたセーリュは手錠と念力封じの首輪を掛けられ、薄暗く狭い牢屋に閉じ込められた。
ここがどこなのかは分からない。食べ物もロクに与えられず餓死するまでここに放置されるのか、それともそのうち処刑されるのか、もしくは拷問されるのか。
何も出来ずに時間だけが過ぎて行き、ただただ恐怖と不安の中で怯えるしかなかった。
空腹で意識が遠のき始めた時、乱暴に牢屋の扉が開いた。
「貴様の処罰が決まった」
扉を開いた兵士はそう言い、ハンドジェスチャーを見せる。
すると二人の兵士が現れ、セーリュを立たせると、彼女に目隠しをして牢屋から連れ出す。
もう生きていられるのも長くないかもしれないと言う恐怖に身を震わせながら、セーリュは恐る恐る尋ねた。
「あ、あの……私は……」
「念力者が議会の許可無しに念力を使うと言うのは重罰に値する」
「でも、私は鉄骨に潰されそうな子供を助ける為に……」
「理由など関係ない。人が地上に住めなくなったのは念力者のせいだと言う事ぐらい貴様も知っているだろう。そのような危険な力を使う事を少しでも許せばこのフェテュスまで地上の二の舞になりかねない」
――私だってなりたくて念力者になった訳じゃ……
だが、念力が使えなければあの子を助ける事ができなかったのも事実。
これがその代償と考えればあまり重くないのかもしれない。
「ともかく、本来なら銃殺刑だが、研究開発部から申し出があった。念力を使った実験をしているので女性の念力者が必要らしい」
つまり実験台になれ、と言う事であろう。
「少しでもフェテュスの発展の為に役立てる事をありがたく思うんだな」
その言葉にセーリュは少しばかりの怒りを覚えた。
何がフェテュスの発展だ、どうせクレイドルの人間が更に贅沢をする為の研究にすぎないだろうに。
04
それからセーリュは数日間に渡り様々な検査を受けさせられた。
それが終了するとセーリュは再び目隠しをさせられトラックと思わしきものでどこかへと移動させられる。
兵士に腕を捕まれてトラックから降ろされた時、そこはアウターに蔓延る騒音もオイルの臭いもしない静かな場所だった。
一体どこなのか非常に気になるが、どうやらまだ目隠しは外してもらえないらしい。
エレベータが開く音がし、セーリュは乗り込ませられる。
どうやらもう建物の中のようだ。
エレベータが停止するとまたしばらく歩かされ、そして立ち止まるように指示される。消毒液の臭いが鼻を劈き、色々な機械音が耳に入った。
「ありがとう、もう大丈夫だよ」
何者かの声が聞こえ、ついに目隠しを外されると、彼女はガラス張りの部屋の中にいた。
部屋はいたって殺風景であり、中央に病院で見かけるようなリクライニングが可能な治療イスがある他、隅にはトイレ・洗面台・シャワー、そして反対側にはベッドがあるだけだった。
部屋の外側には様々な機材やモニターがある。
おそらくここは何かの研究室で、自分の入っているガラス部屋は言わば観察対象の実験動物を入れる檻なのだろう。
「ようこそ、実験体くん」
目の前に立っていた眼鏡を掛けた白衣の青年はそう言った。
「あ……はい……」
「別に怖がらなくていいよ。僕は襲ったりしないし」
大よそ20代前半と思われるその青年は、笑顔を見せながらそう言う。
長身疾駆で顔立ちはとても整っているが、白い髪の毛は無造作に伸びており、着ていた白衣はアイロンを掛けていないのかしわくちゃでヨレヨレだった。
いかにも自分の研究にしか興味のなさそうな若い天才と言う感じである。
「僕はロイド・アークマン。君が一部となる念力発電計画の現場指揮を担当してるんだ」
「私は――」
「ああ、いいよ。別に興味ないから」
ロイドはそう言うと、懐からテープメジャーを取り出す。
優しいのだがどこか不思議な雰囲気の人だ。
「それじゃあ、服を脱いでくれるかな」
「は、はい……」
セーリュはボロボロのワンピースを脱ぎ、下着姿になる。
「あの……」
「ああ、下着は別につけてていいよ」
ロイドはセーリュの身長と体重を量り、手に持ったクリップボードに何かを書きこみ始める。
「身長160cm、体重46.3キロ。BMIは18.1、他所で行った検査の結果によると他の目立った病気や症状もなし。ちょっと痩せてる意外は健康体だね」
「あ、ありがとうございます」
「別に褒めてる訳じゃないって。ただの観測」
苦笑するロイドに思わず釣られて笑うセーリュ。
「あっ、そうですよね」
ポリスの人間とは打って変わって穏やかな物腰のロイドに、セーリュは少しばかり安心を感じた。
「それじゃあ、そこに座ってくれる?」
セーリュは支持された通りに椅子に座り、ロイドはそれをリクラインさせると彼女の両手両足を椅子についたストラップで固定した。
さっき感じた一瞬の安らぎは瞬く間に消え、再び不安が身を襲う。
いくら相手の雰囲気が優しいとは言え、自分が実験台にされようとしている事に変わりはない。
ロイドは近くのテーブルに置いてある注射器を手にとって、彼女の腕にゆっくり突き刺す。
「いたっ――」
「ごめん、後二本ね」
得体のしれない薬を注入し終えると、ロイドはセーリュの腕を軽く消毒し、次の注射をする。
「あの、これって何の薬なんですか?」
恐る恐る尋ねると、ロイドは笑顔で答えた。
「成長ホルモンとか食欲促進剤とか、色々」
「それってどう言う――」
するとロイドは空っぽになった注射器をしまい、バッグから変わった形をした金具のようなものを取り出す。
「まあ、実験体とは言え君も念力発電計画に関わる訳だし、教えてあげる」
ロイドは金具をセーリュの顔に近づける。
「アーンして」
言われた通りにすると、ロイドはセーリュの口に金具を入れ、彼女の口が閉まらなくなるよう固定する。
「へっ!? ひょっ、ひゃんへぇひゅひゃほれ!」
口が開きっぱなしのままもがくセーリュを見つめ、ロイドは言う。
「君も知ってると思うがフェテュスは電力供給に原子力発電を用いている。今まではそれで何とかなってきたけど、これからはそうにもいかないんだ」
それが一体自分が陥っている状況と何の関係があるのだろうか。
「資源の枯渇も遠くないし、おまけに最近は地震も盛んになってきててもしもメルトダウンなんてすれば地下都市の全てが駄目になる」
そしてロイドはセーリュの真上につるしてある太いホースを手に取った。
「だからそれに変わるエネルギー供給法として提案されたのが念力発電」
ホースをセーリュの喉深くまで差込むロイド。
「君も知ってるかもしれないけど、念力は念力者が摂取したカロリーを消費する事によって生まれる」
「んん〜! んんんんんん〜!!」
「だから簡単な話、念力者に沢山脂肪を蓄えさせて、それをゆっくりと念力に変換していく事で発電する」
つまり、それは……
「まあ、ここまで言えば分かると思うけど。君には念力を利用して広範囲に電力供給が出来るか実証する為に太ってもらうって事」
もがくセーリュに変わらぬ笑みを見せ、ロイドはホースの繋がれた機械のスイッチを入れる。
同時にホースからセーリュの喉へとドロドロした何かが流れ込み始めた。
やめて、と叫ぼうとしてもそれは唸り声にしかならず、ホースを流れる液体はどんどんとセーリュの胃に溜まっていく。
そして徐々にセーリュの凹んだお腹は膨らみ始め、ついには妊婦のように大きく膨れ上がった。
――くるしい……やめて……やめて!!
「んっ、このぐらいかな」
もうすぐで弾けてしまうのではないかと言う所でロイドは機械を停止し、彼女
の喉からホースを抜いて手足を固定するストラップを外す。
「ぶふっ……はあ……はあ」
限界まで膨らんだ腹部に肺を圧迫されながら必死に息をするセーリュ。
今すぐ全て吐き出したいが、おそらくそんな事はさせてくれないだろう。
「とまあ、この液体は消化が早いから三時間おきにこうやって食事タイムだから。
それ以外は自由にしてていいよ。九時になったらまた来るね」
ロイドはパンパンに張ったセーリュの腹に手を置いてそう言い、ガラス張りの部屋から出て行こうとする。
「あっ、ただし吐くのは禁止ね」
扉を潜る前にそう言い残し、ロイドは去っていく。
胃がはち切れそうな苦しみの中、セーリュは天井を見上げたまま涙を流した。
――どうして、こんな事に。
しばらくは一歩でも動いたら破裂しそうだったので、セーリュはただ椅子の上で横たわっていた。
数時間たった所でようやく歩けるようになるまでお腹が引っ込み、セーリュは椅子から起き上がる。
ふと壁に掛かった時計を見ると、九時まであと僅か五分だった。
やっと苦しみから解放されたかと思ったのに、あと五分で再びまたあの地獄を
耐え抜かなければいけない。
「……いやだ」
セーリュは必死に自分が閉じ込められているガラスの部屋から抜け出す方法を探すが、唯一の扉は厳重にロックされており、開けそうにない。
念力も首輪によって封じられていて使えないので、ロックを壊す方法もない。
ああだこうだしているうちについに時計の針が九時を示し、ロイドが二人の白衣の男性と共に研究室に入ってくる。
「それじゃあ実験体くん、約束のお時間だよ」
「やだ……やめて」
ロイドがガラスの部屋に入ってくると同時にセーリュは部屋の隅まで逃げる。
「そうやって抵抗するとこっちも力ずくになっちゃうんだけど……」
そして二人の白衣の男性がセーリュに近寄っていく。
「やだ、こないで! こないで!」
必死に抗おうとするものの、華奢なセーリュが男二人に敵うはずもなく、簡単に押さえつけられて長椅子に固定する。
「やめて! いたいの、いたいのいやなの!」
恐怖のあまり自分を抑えられず子供のように泣き叫ぶセーリュの口を強引にこ
じ開けて固定し、ホースを喉まで差し込む。
「んぐううううう! んんん!」
セーリュの唸り声は、彼女に液体を流し込む機械の音によって掻き消された。
前へ 1/4 次へ
#ディストピア