567氏その1
前へ 1/2 次へ
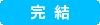
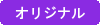
私の名前はリリアン。魔女見習いの17歳。
見習いと言ってもバカにしないでほしい。
そこらのモンスターなら1人で倒せる自信はある。
でも、今とても悩んでいることがある。それは…
「…ハァ」
「ため息なんかついてどうしたの?」
お師匠様が私に話しかける。
お師匠様は文字通り、私の魔女としての先生だ。
まだ28歳という若さながら、魔女としての実力はこの国でも1,2を争う秀才で、国家レベルで行なうような大規模なモンスター討伐にも参加を要請されるほどの人物だ。
そんなお師匠様を見て、私はまたため息をつく。
「…ハァ」
「だからどうしたの?」
「…お師匠様、また太ってません…?」
「ええ、太ったわ。それが何か?」
「いくらなんでも太りすぎですって! 今何キロあるんですか!」
「120キロくらいかしら」
「なんでそんなにあっさりしてるんですか…」
あまりに堂々と答えるお師匠様に、私は呆れるほかない。
お師匠様は実に立派な体格をしている。包み隠さず言えばデブだ。
もう何カップなのかもよくわからない、巨大なおっぱい。
そのおっぱいにも負けないくらい大きく出っ張ったおなか。
ムチムチという表現では表しきれないくらいに豊満なお尻。
同じ女として、これはちょっと正視に絶えない。
「しょうがないじゃない。魔女が太るのは自然なことなんだから」
「それはそうですけど」
そう。魔女は太る。それはどうやったって避けられないことなのだ。
魔力が強ければ強いほど、蓄積された魔力によって身体が膨らんでいく。
かくいう私も… あまり言いたくないけど、この半年の間に8キロも太ってしまった。
運動したり食事のバランスを考えたりいろいろ頑張ってはいるけど、なかなか体重を維持できない。
ちなみに、魔女としての修行をしている者にしかこの事実は教えられていない。
理由は簡単、魔女志望の女の子が減ってしまっては困るからだ。
もしも部外者にこのことを教えた場合、口にするのも恐ろしい罰が待っているのだとか。
「リリアン、いつも言ってるでしょう。女は外見だけじゃないって。実際、私は男に不自由してないわよ?」
「むう…」
お師匠様の言うとおり、お師匠様はこれでなかなか男にモテる。
ただ、魔法使いとして超一流ならそれだけでモテるのか、単にデブ専を見つけるのが上手いだけなのかはわからない。
「あと、モンスターとの戦闘では多少太っていた方が有利なのよ。私たち魔女は元々の体力が低いんだから。もちろん動けないほど太るってのは問題だけど」
「…でも」
「納得いかないみたいねえ。仕方ない、これを見なさい」
お師匠様は棚からアルバムを取り出し、その中から一枚の写真を抜いて私に手渡した。
写真には私と同年代と思われる女の子が写っていた。
どこかの海岸で撮影したのだろう、青い海をバックにビキニの水着姿でポーズを決めている。
くりっとした大きな眼。
ウェーブのかかった柔らかそうな金髪。
小麦色に焼けた肌に、健康的に引き締まった手足。
そのくせおっぱいはしっかりと膨らんでいて、谷間もくっきりできている。
いろいろ悔しいけれど、かなりの美少女と言わざるを得ない。
「あの、この子が何か?」
「私よ」
「へっ?」
「10年前の私。まだ魔女の修行も始めてない頃ね」
慌ててもう一度写真を見直す。
「…そういえば… かすかに顔に面影があるような…」
「失礼ね。太ったって目や鼻のパーツは変わらないでしょ」
「いや… その…」
確かに目の色や鼻の形そのものは今も昔もほとんど変わらない。
しかし、今のお師匠様は顔がまんまるに膨らんでしまっているために、目や鼻が小さく見えてしまう。
写真ではぱっちり開いている目も、今は脂肪に押されて細くなってしまっている。
「そ、それで、お師匠様が凄く可愛い女の子だったってのはわかりましたけど、それでどうしろと?」
「うん。つまりね」
「つまり?」
喉をゴクっと鳴らし、私はお師匠様の言葉を待つ。
「つまり… 私でもこうなるんだから、諦めなさいってこと」
「……」
私はガックリと肩を落としたのだった。
「…というわけなの」
「どこも似たようなものねえ。私のお師匠様も『魔女が太ることを気にしてどうする!』の一本槍だもの」
私立エンゲル魔法女学院、2年A組。
そこで私とリーテは愚痴をこぼしていた。
エンゲル魔法女学院とは、プロの魔女を養成する専門学校。
魔女を目指す生徒達はここで魔法の勉強や戦闘の基礎訓練を行い、無事卒業できた場合にはプロの魔女として認定されるのだ。
また、この学校で受ける授業とは別に、プロの魔女に師事して勉強している生徒もいる。
私やリーテもそのクチだが、どちらも太ることに無頓着なお師匠様を持っているという共通点から愚痴をこぼしあうことが多かった。
そのお陰と言うべきか、今では一番仲の良い友達だ。
「リーテのお師匠様もかなりの重量級だもんね」
「そうなのよ。ていうか、もうプロになった兄弟子の人たちがちょくちょく遊びに来るんだけど、それがみんなそろいもそろってデブなのよ! で、私を見ると 『あら、もっと太らなくっちゃダメよ』 みたいなことを言うわけ」
「そりゃキツいわねえ」
「なんかそんな話ばっか聞いてると、洗脳されちゃいそうでさ… そのうち私も太ることに抵抗なくなっちゃうのかなあ?」
うう、と呻きながらリーテが頭を抱え込む。
「あら。洗脳なんて随分怖いことを言ってるのね」
「へっ?」
突然話に割って入られ、私たちは声の聞こえてきた方を振り向く。
「リリアンさん、お話があるの。授業が終わったら職員室まで来てくれる?」
そこにはA組担任のセビル先生がいた。
ちなみにこの人もなかなかのデブである。
「あ、はい。何かあるんですか?」
「それはその時に説明するわ。それじゃ、あとでね」
それだけ伝えると、先生はドスドスと大きな足音を立てて教室から出て行った。
「リリアン、あんた何かやらかしたの?」
「うーん、特に心当たりはないけど…何だろう?」
突然の呼び出しに私はうんうんと頭を悩ませるのだった。
そして放課後。
私が職員室に入ると、セビル先生はお茶を用意しているところだった。
私にお茶菓子をすすめながら、先生は用件を話し出す。
「この間の実技試験で見せてもらった魔法のことなんだけど」
「あ、あれ自信作です! どうでしたか?」
「ええ、とても素晴らしい魔法だったわ。」
もしかして褒めるために呼び出されたのかも。
そんな風に思って浮かれていると、先生は少し声の調子を変えた。
「素晴らしい魔法だけどね… あれはあなたにはまだ早すぎるわ」
「はい?」
「試験の後で体がだるくなったりはしなかった?」
「えっと… そういえば」
確かにあの試験の後、しばらく体の調子がおかしかった。
疲れがなかなか抜けず、筋肉痛になったかのように体の節々に鈍い痛みがしばらく残っていたのだ。
その事を告げると、先生は納得したように頷いた。
「やっぱりね… 自分の魔力に見合った魔法を使わないと、そういうことが起こるの。魔力というのは生命力とも繋がっているから、魔力が枯渇してしまいかねないような大魔法は使ってはダメなのよ」
「そうだったんですか…」
せっかくの自信作だったけど、そういうことなら仕方がない。
あの魔法はしばらく封印するしかないようだ。
「それで、ここからが本題よ。本人の魔力に見合わない魔法では単位として認めるわけにはいかないの」
「え? それじゃ私、留年しちゃうんですか」
実技試験の単位数は他の試験よりもずっと多く、これを落とすとそれだけで進級判定に引っかかってしまうのだ。
私が青くなって詰め寄ると、先生は苦笑する。
「落ち着いて。確かに単位としては認められないけど、魔法の質が素晴らしかったのは確かよ。だから、補修としてある事項をクリアできるのであれば、単位をあげましょう」
「本当ですか! ありがとうございます! で、その補修って何をすればいいんですか?」
最悪の事態は避けられそうだと私はホッとした… のだが。
「太りなさい」
「はい?」
「太りなさい。今のあなたの体重では、魔力が上がってもそれを蓄えるだけの容量が足りないの」
「ええ? でも、これでも最近は結構太ったほうで… ていうか、魔力が上がれば自然に太るんじゃないんですか?」
「ある程度まではそうよ。でもね、あなたは今魔力の成長期に入っているの。もし魔力の伸びが体の膨張を上回ってしまったら、体が内側から弾け飛ぶことになるわ。もちろん死ぬわね」
とんでもないことをサラリと先生は言ってのける。
ある意味留年以上に最悪の展開になってきた。
「う… それはちょっと…」
「でしょう? だからあらかじめ、体のほうに余裕を持たせておくの。わかったかしら?」
「はあ… わかりました…」
流石に死ぬよりは太った方がマシだけど、それにしても他に方法はないものかと私は憂鬱な気分になる。
「あの、それでどれくらい太ればいいんでしょうか?」
「そうね。重要なのは体重よりも体積なんだけど… リリアンさんのスリーサイズは今いくつかしら?」
「…言わなきゃダメですか?」
「ダメよ」
「…上から81、66、82です…」
一般社会なら間違いなくセクハラで訴えられそうな質問だが、この場合は仕方ないのかもしれない。
恥ずかしいのをぐっと我慢して、私は先生に最重要機密事項を伝える。
「そう。それならバストとヒップは90台、ウエストは80台を目標に頑張って」
「なんかウエストだけハードル高くないですか?」
「そこが一番肉が付きやすくてやせにくいからよ。それじゃ、急に太るのも難しいでしょうし、期限は進級判定の日としましょうか。まだ2ヶ月ちょっとあるし、大丈夫よね?」
「はい…」
不承不承私は頷く。
ああ、さようなら、私の痩身…
前へ 1/2 次へ