334氏その6
前へ 1/2 次へ

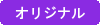
「今日も終電帰りか」
俺は大きく伸びをして、田舎の寂しい駅に降り立った。
腕時計を見ると午前1時、寒風が吹き抜けるプラットホームには人っ子一人いない。
無人の改札を通りぬけようとした時、俺はベンチに人影を発見して、ふと立ち止まった。
女の子だ。
身長180cmはあるだろう若い娘がベンチに寝転がっていた。
ハンチング帽をかぶり暗めの抹茶色のジャケットを着ており、
擦り切れた青のジーンズを履いている。
横に倒れ込むようにして眠っているその顔は、
一重の目がおとなしそうな印象だがなかなかかわいい。
「こんなところで寝ていると風邪ひくぞ」
俺は女の子の頬を手の甲で軽く叩いた。
11月、落葉樹にはすでに葉は付いていない。この地方は時々小雪が舞ったりするのだ。
「ん……」
だが女の子はもぞりと体勢を変えただけで目を覚ます気配がない。
横向きからわずかにうつぶせになり、大きなお尻がこちら側を向いた。
服の上からでは断片的にしか認識できないが、どうやら出ているところは出て
引っ込むところは引っ込んでいる――いわゆる、グラマラスな体形らしい。
俺は股間が熱くなってきたのを感じて、邪念を振り払うためにひとつ咳払いをした。
このままここに放置しておいたら不逞の輩に何をされるか分からないし――
第一、一社会人として不親切だろう。
「交番で保護してもらおう」
俺は女の子の腕を肩に回し、彼女の体を起こした。
上背があるせいでずっしりとした重量が肩にかかった。
日頃、営業で鍛えている若い肉体でもさすがに堪える。
重みで震える足で改札口を出た時、一筋の風が構内に吹き込んで来た。
女の子の帽子が風にさらわれる。
「あっ、ちょっと……」
女の子をかつぎながら帽子が飛ばされていった方向を振り返った時。
女の子の栗色の髪の間からちょこんと2本の角が生えているのが見えた。
「!?」
なんだこれ。どういうことなんだ!?
静かに女の子を床に寝かせ、頬をつねる俺。
冬の寒気が痛みとともに身にしみたが、目の前の光景は変わらない。
気持ちよさそうに眠る彼女の頭には、小さな三角形の角が生えたままだ。
警察には連れて行ってはダメだ。
どうしてか俺はそんなことを考えた。
今振り返るとこの予感は、後に俺が体験する奇想天外な物語へ続くきっかけになったわけだが
――当時の俺はそんなこと思いもせずに女の子の寝顔を見ていることしかできなかった。
我に返った俺は、その後、女の子を支えつつやっとこさ自分のアパートの部屋に帰りついた。
金属製の扉を開け、1DKの我が家に入る。
シンクでコップに水を注ぎ、女の子の桃色の頬に数滴垂らす。
「んあ……?」
眠たそうな声を上げ、女の子の目が開いた。
彼女はきょときょとと辺りを見回したが、目の前に俺の顔を見つけて不安げに眉根を寄せた。
「あ……ここは……?」
「気分はどうだい? あんた、冬のプラットホームで寝ていたんだぜ。
あのままだと風邪を引くところだった」
「え? そ、それはご迷惑をおかけしました」
女の子はぺこりと頭を下げた。白い角が一緒にお辞儀をする。
「助けていただいてありがとうございます。私は牛坂といいます。
お名前を伺ってもいいですか?」
「俺の名前は須々木。ここは俺の家だ。それより聞きたいことがあるんだが――
あんたの頭に生えているその角はなんだ?」
俺は牛坂さんの角を指差すと、女の子は自分の頭に手を遣った。
帽子を被っていないことに気付いたのか、顔を赤らめた。
「ば、ばれてしまいましたか……」
「あんた――何者だい?」
「そ、それは……」
彼女はしばらく逡巡していたが、こちらをしっかりと見ると口を開いた。
「私はミノタウロス――神話に出てくる牛の亜人です」
俺は昔本で読んだミノタウロスの挿絵を思い浮かべた。
人間の体に牛の顔を持つ化け物だったような……
「でも、俺の持っているイメージと大分違うんだけど」
「それはですね、人間の思い違いです。私の故郷は絶海の孤島にある小さな町で
大勢のモンスターや妖怪が住んでいるんですけど、時々漂流した人間が流れ着くんです。
そうした人間達が私達の姿を見て、運よく人間の世界に帰って来た時に伝播したイメージに
尾ひれがついたものが、今あなたが持っているミノタウロスやその他モンスターの姿なんですよ」
「へえ。ということは実際の姿は牛坂さんみたいな――」
「――人間の体に角と尻尾がついた格好です」
そう言うと、彼女のズボンからふさふさの牛の尻尾が覗き、左右に揺れた。
どうやら臀部で彼女の体と繋がっているらしい。
ミノタウロスか――以前の俺ならモンスターや妖怪がいるという話は信じなかったろうが、
実物を見せられてしまった後では信じざるを得ない。
「あんたが何者なのかは分かった。しかし、どうしてミノタウロスが人間の町で倒れてたんだ?」
「それは話せば長くなるのですが……私達モンスターは人間達と共存するための試練として、
18歳になると1年間人間の町を周って自活する実地研修が課せられているんです。
私もそれに参加していたのですが……この町で下車した時に財布を無くしたのに気付いて。
ベンチで途方に暮れていたら疲れてついつい寝てしまったんです」
「それなら、あんたの両親に連絡をとってお金を送ってもらわなくちゃいけないな」
「でも実習中は両親に頼ってはいけない規則になっているんです。
あらゆる事態に対する適応能力を養うのが実習の目的ですから」
「ちなみに実習はあとどのくらい続くんだい?」
「6か月です。その期間、自分でバイトして生活費を稼ぎます」
「ただ、問題は住む場所なんですよね。身元が怪しい私は部屋を借りるのも一苦労で……」
「それなら――よければこの部屋に間借りしない?」
袖振りあうも多少の縁である。
「いいんですか!? ありがとうございます!」
こうして俺と牛坂さんの奇妙な同居生活が始まった。
翌日の朝。
牛坂さんと同じリビングで寝るわけにもいかず、キッチンで毛布を引いて寝ていた俺は
異臭を感じて目を覚ました。
「おはようございます」
目の前に牛坂さんのジーンズの大きなお尻が見えた。
「何してるんだい?」
「ただで居候も悪いと思いまして――朝ごはんをつくっています」
「何を作っているんだ? やたら臭うんだが……」
「はい、ヨモギとセイタカアワダチソウのソテーです!
ミノタウロス界ではごちそうなんですよ」
牛坂さんは嬉しそうにフライパンの中身を見せた。
中には深緑色のよくわからないかたまりが悪臭を放っていた。
「あのな……人間はそんなもの食べられないんだよ」
俺は戸棚の中からカップラーメンを2つ取り出し、お湯を注いだ。
牛坂さんが興味深けにその様子を見ていた。
「よし、3分経ったな。これ、食べろ」
差し出されたカップラーメンにおそるおそる手をつける牛坂さん。
「……なにこれ、おいしいです」
「そうだろ。これは人間の食べ物でカップラーメンっていうんだ」
「お湯を入れるだけでこんなおいしいものが食べられるなんて……人間って侮れないですね」
そういうと、彼女は一気に麺をすすりあげ、スープを飲み干した。
「けぷぅ――とてもおいしかったです。あのー、おかわりはないですか」
ずうずうしいなと思いつつ、残りのカップラーメンを出した。
彼女はたちまちそれらを全て平らげ、あまつさえ3杯目も胃袋におさめた。
牛飲馬食とはこのことか。
食い物のことになるとおしとやかな彼女も少し厚かましくなるようだ。
彼女の食いっぷりをみながら、食費がかかることを覚悟した俺だった。
前へ 1/2 次へ