334氏その7
前へ 1/3 次へ
#,THE IDOLM@STER,アイマス,アイドルマスター,三村かな子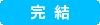

私は憤っていた。所属する芸能事務所のプロデューサーにである。
「あの、かな子先輩……怒ってます――よね?」
目の前に座っていた後輩がおずおずと私を見た。どうやら眉をしかめていたようだ。
「ううん、正直なところ、プロデューサーさんに対して嫌悪感を持つよ。
その話が本当なら、だけど」
今、私は事務所の休憩室で後輩の相談にのっている。
彼女が語るところによれば、事務所のプロデューサーさん――彼は事務所に所属する
アイドル全員のマネジメントを担当しているのだが――に黒い噂が流れているらしい。
その噂によると、彼は成績が芳しくないアイドルを止めさせ風俗等の汚れ仕事に
強制的に斡旋している、ということ。
腕を組んで考え込んでいると、彼女はすがりつくように目を潤ませた。
痛い気な演技を得意にしているだけあって、同性の私でも心を動かされそうになる。
「でも、実際に私の同期生が急に事務所をやめているんです。
その子はとても真面目な子だったんですけど、このところ売り上げが伸びてなくて。
辞める理由を聞いても寂しそうに笑うだけで……でも、私はその後盗み見てしまったんです。
強面の男たちと一緒にプロデューサーの車で連れ去られる彼女を!」
それだけだと、どうにも判断しようがない。情報があまりにも限られすぎている。
それに、デビュー当時から色々お世話になっているプロデューサーさんを
疑いたくないというのも本心だ。
「ですから、かな子先輩にはその噂の真偽を確かめるのに協力して頂きたいんです。」
「確かめるって――どうするつもりなのかな? プロデューサーさんに直接問い詰めるとでも?」
「はい!」
「……」
はい、って――どれだけ直球な子だろうか。
後ろめたいことを尋ねられて素直に「そうです」と答える人間がそうそういるはずがない
――特に業界を渡り歩いてきたであろう、海千山千のプロデューサーさんは。
私は少し思案した。相手はしたたかな凄腕である。やわい手段では解決できそうにない。
証言だけではなく、物的証拠が欲しい。
「それよりも、斡旋の噂が本当なら書類かなんかがあるはずだよ。それを入手しよう」
「でもどうやって?」
首をかしげる彼女に私は怪しくほほ笑んだ。
というわけで、私はプロデューサーさんの部屋に忍び込んだのだった。
無論、斡旋関係の書類がないか確かめるためである。
毒を食らわば皿まで。芸能界にいる内に我ながら黒くなったな、と
ファイルに閉じられた書類の束を繰りながら思う。
ちなみに後輩は部屋の外で見張り番。プロデューサーさんに見つかっては大変だからね。
それにしても大量の書類である。
所属アイドルの個人データ・日誌・財務書類その他その他……
戸棚に並べられた書類をかき分けていくと、奥に丸い銀のボタンを見つけた。
これは怪しい。
スパイ映画でよくある秘密の金庫かもしれない。
私は好奇心に駆られ、ボタンを強く押した。
次の瞬間足元に穴が開き、私の体は暗闇に吸い込まれていった。
管理室で打ち合わせをしていると、壁に取り付けられたランプが赤く光り、ブザーが鳴った。
「誰かが部屋に忍び込んだみたいだな。トラップにかかったサインが鳴ってますぜ、
プロデューサーさん」
八田が鋭い目をさらに細ませながらランプを振り返った。
俺は契約書をまとめながら目の前のいかつい男に言った。
「おおかたウチの事務所の誰かだろう。好奇心が強い三村あたりじゃないか」
そばに置いていたタブレット型端末で『檻』の様子を見ると、やはり、
かな子が石の床に横たわっていた。
気を失っているようだ。
「へっへっへ、それは大変だな。もしあんたがやっていることがばれたら、
業界にいられなくなるぜ」
相変わらず下衆な笑い方をする男だ。
この男はどうしても好きになれないが、こいつの協力なしに俺の事務所は
やっていけないのも事実だ。
感情を押し殺し、冷徹に対応する。
「そうだな。悪いが三村には秘密を悟られた以上、アイドルを引退してもらって
第二の人生を歩んでもらうとするか」
「これまで送ってきたやつらのように――ですかい?」
これまで俺が『商品』として送ってきたアイドル崩れ達。
八田の店に送られた後はどんなことをさせられているのか知らないが
――知りたくもないが、八田がどこかの組の構成員だということを考えれば
彼女達の末路を想像することは難しくはない。
「こないだ送った子、あの子も上玉でしたな。店でも良く働いてくれてますぜ。
3年もすれば立派な――」
その先は聞きたくない。あの子も真面目で良い子だった。
「おしゃべりは終わりだ。早速、彼女の様子を見てくる」
「ちょっと待ってくれ」
管理室を出て行こうとする俺を、八田の濁った声が呼び止める。
「今度、俺は新しい店を出そうと思っているんだ。ついては、『檻』に落ちてきた子に
ふさわしいプロデュースを施してほしい。これが店の概要だ」
そう言って八田は俺にA4大の書類を一枚手渡した。
ざっくりと流し読みする。読み進んでいくに従って眉間に皺が寄っていくのが分かった。
「なかなか――個性的な店じゃないか。三村をこの店に合うようにプロデュースしろ、と?」
「そうだ。落ちてきた子はかなりの美人だし――それにこの仕事が上手くいけば通常の10倍、
料金を弾むぜ。あんたが弱小事務所の経営で背負ってきた借金も全額返済できる」
俺はしばし考えた。
かな子は売り出し中の期待のホープであり、個人的にかわいがってきたアイドルの一人。
思春期の少女にこの運命は可哀そう過ぎる。
「何を迷っている? どうせ『檻』に落っこちてきた時点で、あんたのやっていることは
彼女にはばれたも同然なんだよ」
八田のその一言が俺の背中を押した。芸能界でマネジメント業をしてきて早10年、
こんなことで悩む神経をしていたらとっくの昔に精神を病んでいる。
俺は心の奥に蓋をして、八田を振り向いた。
「分かった。契約を飲もう。ただし、約束の金はちゃんと払えよ」
そう言い残すと、にやけた笑みを浮かべる八田を残し、『檻』へ向かった。
「あいたたた……」
痛む頭をさすりながら私は目覚めた。
周囲はぼんやりと明るい。何か柔らかいものの上に落ちたらしい。
古びたクッションのようだ。私が充分乗れるくらいの大きさで――
なんだか獣のような臭いがする。
クッションから降りて、地面に立つ。
無機物のひんやりとした感触がニーソックスを通して足下に伝わる。
石を敷き詰めて作られた床だった。高校の教室くらいの広さである。
起き上がって上を見る。落ちてきた穴からわずかな光がもれ、部屋をかすかに照らしている。
周りの壁も石造りで――それも、ずいぶん年季が入っていて、
ところどころに茶色の苔が生えている。
ただ、私の正面の壁だけは違っていた。
向こうが暗くて輪郭がよく分からないが、鉄格子―刑務所でおなじみの鉄の柵が
はめ込まれたアレ――だった。いや、実際に刑務所に行ったことはないのだけれど。
どうやら私はいる場所は、世間一般で言うところの牢屋と呼ばれる場所らしい。
プロデューサーさんの部屋から落とされてここに閉じ込められてしまったようだ。
というか、なんでこんなものがあるんだ、ウチの事務所は。
いぶかしんでいると、スイッチが入る音がして鉄格子の向こうに明かりがついた。
光と影の縞模様が石の床に投射される。
まぶしさに目を細めて、牢屋の外を見ると聞き覚えのある落ちついた声がした。
「大丈夫か? かな子」
鉄格子からこちらを見ていたのは――プロデューサーさん。
声の調子は柔らかかったが、表情は固い。
私は鉄格子に駆け寄り、彼の顔をしっかりと見つめながら言った。
「どういうことなんです、これ!? やっぱりプロデューサーさんの黒い噂って本当――」
「それ以上は言わないでくれ。かな子にはこれから辛い思いをしてもらわなくちゃいけない。
けれど、これはウチの事務所のアイドル全員のためなんだ」
きっぱりとした口調だった。その目は覚悟を決めた目だった。
「え……」
どういうこと?何をされるの?
困惑する私をよそに、プロデューサーさんは鉄格子の下にあった小さな差し入れ口から、
イチゴのショートケーキを一皿牢屋の床に置いた。
「頑張れよ」
後ろを振り向かずに歩き去っていくプロデューサーさん。
ケーキを食べてこれから起こることに備えろ、ということだろうか。
私はフォークでショートケーキをすくい取り、頬張った。
まろやかな甘みが口一杯に広がる。ケーキは私の何よりの大好物だ。
ケーキの差し入れは、この異常な状況に対するプロデューサーさんなりの謝罪なのかもしれない。
生来が楽観的な気性の私は、すぐにここから出してもらえるだろうと考え、
クッションに横たわった。
「ふぁ〜あ……」
緊張で疲れていたのだろう。横になると、とろりとした睡魔が襲ってきた。
そのまま眠りの世界に引きずり込まれた。
前へ 1/3 次へ