アメリカ留学
前へ 1/4 次へ
#読者参加型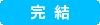
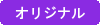
プロローグ
「見ろよあの女」
電車に乗っていると、金髪の男が私の方を見て、連れらしき男に耳打ちをした。
「スッゲーデブw」
耳打ちされた男も私を見るなり口を歪めて笑った。
「ゲッ、マジかよ!?あんなピザ女見た事ねえ」
胸の奥がちくりと痛む。
「どんな生活したらあんな体形になれるんだろな?」
彼らの嘲笑に耐え切れず、顔を背け寝たふりをした。
つぅ、と涙を頬を伝う。
やめて…やめてよ…
それ以上私の心をくじかないで…
1年ぶりの日本なのに、あの人に会わせる顔がないよ…
1
1年前、私は高校の援助でアメリカに語学留学した。
学業成績が優秀な生徒だけが選ばれる、我が校が誇るプログラムだ。
プログラムの受講生に選ばれたことを知ると、クラスの皆は送迎会を開いてくれた。
「おめでとう!榊なら選ばれて当たり前だな。この間の模試も1番の成績だったから。」
同級生の賛辞に顔が自然と赤くなる。
「ありがとう。そんなに褒められると恥ずかしいよ。」
「学校でも一人しか選ばれないプログラムに私のクラスから受講生が出て、先生も鼻が高いぞ。」
担任の先生が大きな手で私の肩を叩く。
「痛たた、痛いですって!」
「すまん、すまん」
教室がどっと笑いに包まれた。
送迎会が終わって教室から出るとあの人がいた。
「榊、アメリカに行くんだってな。」
「あ、大沼君…。明日、朝一番の飛行機で出発するんだ。」
「そう…」
大沼君は少し寂しそうだ。
私はあわてて言葉を継いだ。
「で、でも向こうに行っても大沼君の事、忘れないよ。約束する!」
「本当か?」
「うん!」
その言葉を聞き、肩の力が抜けたようだった。
そして、少し顔をそらしながら私に言った。
「あのさ、もし良かったら俺の家でお前のアメリカ行きを祝して食事でもしない?
今日は親もいないしさ…。」
その誘いの意味を何となく感じながら、私はこくんと頷いた。
2
「ふぅ、ここがアメリカかあ」
長時間のフライトを経て、私はロサンゼルスの空港に降り立った。
ガヤガヤとたくさんの人でにぎわっている。私は急に心細くなった。
「えっ…と、ホストファミリーが迎えに来ているはずだから探さないと。」
きょろきょろと周りを見渡し、歩き始めたその時。
「Hey, pretty girl!」
大きな声で呼びとめられた。
声がした方を見ると、恰幅の良い青年がのしのしと歩いてきた。
「May I ask your name?」
「あ、ま、まいねーむ いず さかき…」
「Oh!ペラペラペラ…」
「あ、あの、その…」
返事をしようとするが、青年の話す早さが速いのでついていけない。
ごにょごにょと訳のわからない単語が飛び出るだけだった。
その様子を見て青年はさわやかにほほ笑んだ。
「ごめん、ごめん!ちょっとからかってみただけなんだ!」
流暢な日本語である。
「榊 綾香さんだね。僕はロジャー。キミのホストファミリーさ。」
目じりが少し下がったなかなか愛嬌のある顔。
「よ、よろしくお願いします。ロジャーさん。」
ぺこりとお辞儀する。
「長旅で疲れてるだろ?早速、家で歓迎パーティーをしよう。」
大股で歩く彼の横を、私はキャリーバッグを引きながらついていった。
ロジャーさんが運転する車に乗って、私はホストファミリーであるブラウン家に着いた。
「Welcome! YAMATONADESHIKO!」
ドアから降りると、でっぷりと太った中年の男女が玄関に立っていた。
「紹介するよ、僕の両親のロビンとキャサリン」
「Nice to meet you!」
夫妻はグローブのような手で握手を求めてきた。
「な、ないす とぅ みーちゅ…」
パワフルな夫妻に圧倒されながら、なんとか返事をした。
「さあ、挨拶が済んだところで早速ウェルカムパーティーだ!」
近所の人たちも集まって、ブラウン家の庭でバーベキューが行われた。
「どんどん食べてね!」
そう言って、ロジャーさんは私の皿に肉を持ってくれた。
300gもありそうなステーキが何枚も積み重ねられている。
「あ、ありがとう」
親切を無碍にするわけにもいかず、私はもそもそとステーキを食べ始めたが、
1枚を食べ終わる頃にはお腹がいっぱいになっていた。
一方、ロジャーさんや他の人達は大きなステーキを何枚もと平らげていく。
あっけにとられてその様子を見ていると、口の周りをバーベキューソースでべたべたにした
ロジャーさんが話しかけた。
「遠慮せずにもっと食べていいからね」
私は苦笑いを浮かべ、進まない手で配られたステーキを食べることを再開した。
これからのアメリカでの食生活になじめるか不安に感じながら。
3
アメリカでは全ての食べ物が大きかった。
現地の学校の給食は主にハンバーガーとフライドポテトのような炭水化物が中心だったのだが、
それら全てが日本の2倍はあろうかという大きさだった。
ブラウン家での夕食も大盛りのパスタや巨大なステーキ(大味!)、
食後はアイスクリームやケーキ(大甘!)というものだった。
(毎日こんな食事なら太っちゃうよ…。でも、残すのももったいないしな…)
アメリカ人向けの料理のように辟易しながら、私はなんとか完食するように努めた。
不思議なもので、しばらく経つと、以前は満腹になっていたアメリカの料理も
軽く食べきることができるようになっていった。
また、大味なジャンクフードも結構イケるかも?と思うようになった。
こうして、私自身、慣れとは恐ろしいなあと思いながら、アメリカでの生活に馴染んでいった。
4
アメリカに来て3カ月が経過した。
私とロジャーさんはカフェで食事をしている。
「いやあ、榊さんが来てからもう3カ月か。月日が経つのは早いものだね。」
両手に余る大きさのハンバーガーを食べながらロジャーさんが言った。
「そうですね、ついこの間のような気がします。」
私もテーブルの上に置いてあった4個目のハンバーガーに手を伸ばした。
「それにしても、榊さんは本当によく食べるようになったなあ。
ウェルカムパーティーの後は吐きそうになっていたのに。」
「あはは、アメリカンサイズの料理を食べ続けているうちに
胃袋が大きくなったのかもしれないですね。」
ハンバーガーの最後の一口をほおばりと、私はベルトを緩めた。
ズボンに余裕が出来て、むちむちとしてきたウエストがふっくらと広がる。
その様子をちらりと見たロジャーさん。
「食欲が旺盛なのはいいれけど、最近ちょっとお腹周りが大きくなってきたんじゃない?」
にやりとほほ笑む。
気になっていたことを指摘され、私は少し俯いた。
「あの、分かっちゃいました?」
上目づかいで彼を見る。
丸みを帯びたお腹を撫でた。恥ずかしい…。
「ははは。その程度なら目立たないよ。
もっと太った人はいくらでもいるさ。」
なるほど、室内を見渡すと客の大半は100kgを超えてそうな肥満体の人ばかりだ。
確かにこの中では、ちょいむち程度の私は痩せている部類になるだろう。
「だ、大丈夫ですか…ね?」
「大丈夫、大丈夫!むしろ僕はちょっと太目の方が好みだな。」
ロジャーさんの真っすぐな瞳に、思わず目をそらしてしまう。
「もう…そんなこと、やめてくださいよ。」
「それより、服を買うのに付き合ってくれませんか?日本から持ってきた服がきつくなってきて…」
胸の奥に疼きを感じながら、私は話題を変えるために言った。
「いいよ、近くに良い服屋を知っているから行こうか。
XXLまでサイズを取りそろえているからね。」
5
その服屋には5回行くことになった。
もちろん、私の体形が大きくなるにつれて、より大きな服が必要になったからだ。
アメリカに来て半年が経つころには、私の体重は90kgを超えてしまっていた。
ある時、ロジャーさんと並んで帰宅すると、庭に水をまいていたブラウン夫妻が
私達に何か喋りかけた。
「何?なんて言ったんですか?」
「あー、『並んで歩いていると、ふくよかなおそろいのカップルだね』って…」
「え、それって…」
「あ、気にしないで。家の親、鈍感なところがあるから。」
彼が話し終える前に、私は玄関に入って階段を駆けあがり自室に駆け込んだ。
姿見の前に立つ。
むっちりとしたハムのような二の腕。
マシュマロがくっついたような胸。
妊婦のように突き出たお腹。たぷたぷとした脇腹。
大きなクッションがひっついたようなお尻。
気がつくと、周りのアメリカ人達と比べても遜色しない立派な体格になっていた。
「あわわ…これは本格的にあぶないよぉ…ダイエットしなきゃ」
姿見の前で色々なポーズをとっていると、扉の外でロジャーさんの声がした。
「おーい、大丈夫?入ってもいいかい?」
「だ、大丈夫です!」
贅肉をつかむのを止め、あわてて返事をする。
扉が開いてロジャーさんが顔をのぞかせた。
「さっきはごめんな。家の親、鈍感なところがあるから…」
「い、いいんです。太ったこっちが悪いんですから」
もたもたとズボンをたくしあげる私。
ロジャーさんは話しを続ける。
「本当にすまなかった。何かお詫び出来ることがあれば言ってくれ。」
「あ…」
私は少し躊躇した後、こう続けた。
「じゃ、じゃあ、だ、だ、ダイエットを手伝ってくれませんか?」
前へ 1/4 次へ