太っちょマリアの大冒険
前へ 1/2 次へ
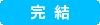
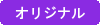
ある町に一人の女性が住んでいた。町といっても、わたしたちが住んでいるような騒音が鳴り響いて、深呼吸のできないくさい空気の町ではない。ただ巨人よりもはるかに大きな建物がいくつか建っているところは同じだ(特に街の中心や教会、貴族の住居など)。居心地は申し分なく、日当りはよくて夏には近隣の林から涼やかな香りが流れ込んでくる。ここは人間たちがたくさん暮らす、国一番の大きな街(人間以外にもたくさんいる)。市場には物があふれて、働くことや遊ぶこと、何もしないことなど、何をするにもうってつけだ。街道には人や物をたくさん積んだ、荷車・馬車などがひっきりなしに往来している。しかし昔はもっと栄えていたものだ。
それというのも、この国は度々大変な事件に見舞われてきたからだ。もう覚えている者が一人もいない、大昔の神々と悪神との戦いでは大陸を丸ごと消し飛ばされ、住民は移住を余儀なくされた。その後も退治された悪神の残党との小競り合いや種族同士の対立、疫病、飢饉など、様々なことが起きた国だった。
この町は戦争中に起きた疫病により、一時は滅びかけたものをここまで再生させて今に至る。しかしそんな悲しい話も過去のこと。人々は平和な日々を謳歌していた。
既に述べたように、この国ではたくさんの事件が起こった。当然ながら、それにまつわる伝説や英雄、変わった物語も数多く誕生していったのだ。その物語の中からひとつを抜粋して、ここに記したいと思う。それがこのような町に住むある女性にまつわる物語だ。
彼女の名前はマリア。今でこそ町に住んでいるが根っからの野生児で、森の奥の木の上に作った小屋で両親と暮らしていた。いわゆる「森の人」と呼ばれる人たちで、狩猟や軽業などが得意だった。昼間は狩りや採集を楽しみ夜になると木に登って、下で群がるオオカミをからかって遊んでいた。枝から枝へとまるでバネのように軽やかに、木々の間を飛び回った。その際、彼女の腰まで伸びたクセのある黒髪が、月明かりに照らされて森の暗がりでもよく輝いた。
森での生活を満喫していた彼女だったが幼くして両親を寿命で亡くし、身寄りのない彼女は町にいる遠い親戚に引き取られた。初めは町の生活に慣れず、家を抜け出しては近くの林まで出かけて夜遅くまで遊び、泥まみれで帰ってきたものだった。
そんな彼女も町での誕生日を5回ほど経験する頃にはすっかり落ち着いて、投げ輪やボーリング、なぞなぞ遊び、読書など町から出なくてもできる遊びをするようになった。特に読書にはすっかりはまったようで、一番少ないときでも項数の少ない本なら日に5冊は読んでいた。実は彼女の冒険心は縮んだわけではなく、本の中に広がる広い世界に心を躍らせていたのだ。機会があれば本の中のようなどこか知らない所へ行ってみたい、そう考えていた。
それから少しも経たないうちに、町を大飢饉が襲った。その年は特に寒く、雪解けの時期がだいぶ過ぎても霜が降りるほどだった。周辺国のなかで特に深刻なのが一番人口の多い、彼女のいる町だ。町の統領はすぐさま豊穣の国である辺境のカルカッタ国へと使者をだし、知恵か食料を要求した。しかし何度使者を送り出しても一人も帰っては来なかった。
危機感を覚えた町の自治組織は有志で旅団を募り、カルカッタへと派遣した。その中には傭兵、行商人、町民の代表である使者、そしてマリアの姿があった(おじとおばに反対されたが、行商人の荷物に隠れてついてきた)。
「こんなチャンスを逃したら、私はずっと冒険に出られないかもしれない。」
マリアは焦りと抑えきれない好奇心から、出発間際で祝福を受けている旅団の荷馬車にたまらず飛び乗ったのだ。このことを彼女は後からしこたま後悔することになる。
幾日か過ぎ、一行はカルカッタの国境、カルカッタ野を過ぎてカルカ谷へと差し掛かっていた。まったくマリアの忍びの技ときたら大したもので、ここ数日間バレもしなければ飢えることも全くなかった。数年のブランクはあるものの、森で生活していた彼女にとっては疲れきった見張りをかわして音もなく食糧をくすねるなど、鼻しか利かないオオカミを相手にするより簡単だった。
寒くて殺風景な街道とは違い、谷は暖かく木々が生い茂り、いろんな色のいい香りがする果実がたくさん実っていた。しかし何かがおかしかった。それはみんながうすうす感じていたことだ。目的の町に近づくにつれて植物なり、動物なり、道端の石なりの角が取れて丸々とし出したのだ。空気を入れて膨らんだというより、水の飲みすぎでむくんだといった方が的確な形をしていた。
カルカッタの中心部へ着いた一行が目にしたのは異様な光景だった。人やら家やら、とにかく何もかもがコロコロしていて、完全な丸ではなく少し垂れ下がって何やら鈍重そうにブヨブヨとうごめいていた。中には転がっているもの、ドアに挟まっているもの、体が重すぎて立ち上がれないもの、とにかくひどいありさまだった。しかし見たところ男性らしき人の姿は一人も認められなかった。
一行が呆気にとられていると、か細い声とともに糸のように細く板のように薄い、おそらく人間の男性とみられるものが町の入り口で出迎えた。聞くところによると彼はカルカ谷の町長で、町がこのようになったいきさつを語ってくれた。
「今年はひどい飢饉になると聞いていて、町民はおびえていたんです。この谷は安全だと説明しましたが聞き入れる者はなく、この豊穣の国にさらに豊穣になるようまじないをかけました。その結果、いきすぎた豊かさは暴走して、恰幅が良いことが自慢だったカルカッタ男の体からは栄養が抜け、その栄養がすべて周りの人や物にまとわりついてしまったんです。あんなに美しく整った体をしていた女たちもこの通り。」
町長は体を安定させようと必死にブヨブヨ動き回るカルカッタ女たちの方を向いてため息をついた。
「このまじないはカルカッタ中に及んでいます。食糧は有り余っているし是非支援したいところですが、男も女もこのざまじゃあどうしようもない。せめてこれを持って行ってください。これは大地にめぐみをもたらすまじないがかけられた水です。どんなやせた土地でも果物が生えて、その種をさらに別の場所にまくのです。そうすれば飢饉はたちどころに解決できるでしょう。」
そういって町長は、濃く澄んだ色をした緑の液体が入ったビンを一行に渡した。
「あなたたちにも既に異変が起きているはずです。今更手遅れかもしれんが、早くこの国から逃げ出した方がいい。」
そこまでいうと重しがなくなった町長は、そよ風に吹かれてひらひらと飛んで行ってしまった。
一行は慌てて自分の体を確認した。村長の話通り、この国に入る前と比べるとガリガリに痩せていることが分かった。
マリアも顔を青くして、狭く感じてきていた荷馬車の中で、体のあちこちを触ってみた。いつも皆が寝静まった夜にしか行動しなかったし、馬車の中は薄暗いため、今まで気づきもしなかったが、乙女の淡い望みは柔らかい触感とともに掻き消えた。
シュッと整っていた頬は、両手で押すとホワッとやわらかく、まるで赤ん坊のよう。この時点で目に少し涙が浮かんだ。
その頬を押している手も腕も、木の上で生活していた頃が嘘のように真ん丸になり、健康的な筋肉の上に脂肪が乗ってしまっている。
木から木へ軽快に移動できて自慢だった彼女の足も見るからに鈍そうで、さながら大きな木の幹で作った棍棒のように太く膨れ上がっていた。
胸は元が人並だったものが、衣服かなにかで支えていないと垂れ下がってしまうほどの重さになり、息をするたびにつっぱったりたるんだりする。
不安と驚きと息苦しさとで、自然と呼吸は荒々しくなる。
腰回りにかけての膨張は著しく、自慢のふとももから続くキュッとしまっていたお尻はほどよく張りを備えて、衣服の下からでもドンと突き出している。座っていると、さながら背中から腰に掛けて、突き出た尻が床で潰れて土手を形成しているようにも見える。
お腹の方は、近頃動いてないせいだと自分をだましていたが、これは自分でも気づいてしまっていたほど、でっぷりと前に突き出ている。下腹部に潰れたへそがついている以外は完全な反球体となり、もはや衣服でも隠しきれていない。盗み食いをするしか楽しみがなかったため、ドカ食いをしたこともあった。これはただの食べすぎで、脂肪が詰まっているわけではないと思い込んでしたのだ。
「う、うそよ・・・こんなのありえ・・・ぅぇっ」
自分の唯一残していた女らしさが数日の間にこうも変貌してしまったことに戸惑いを隠せなかった。顔を真っ赤にして涙ぐみながら、両手でお腹やらお尻やらをつまんだり揉んだりしながら、いまだこれが自分の体の一部だと納得できずにいた。
一行は馬の頭をもと来た道に戻して、あわてて馬車を走らせた。そしてあんまり慌てていたため、荷馬車に積んだ大事な便が途中で転げ落ちていることに、マリア以外はだれ一人気付かなかった。
突然急発進したため、荷馬車の中でドテッとよろめき仰向けに倒れてしまった。マリアは重たい体を何とかおこし、恥ずかしさと悲しさで緩んだ口元を無理やり「へ」の字にくいしばって、疾走する荷馬車から飛び降りた。お腹の脂肪のおかけでボヨンと体が弾み、大した怪我もなく瓶を回収することができた。しかし荷馬車はマリアをおいて元の町へと帰ってしまった。馬車で数日かかった距離をこれから歩いて行かねばならない。それもこのだんだん重たくなる体を背負って。そう考えただけでマリアは頭が真っ白になった。
「・・・ぷぅ・・・お腹・・・痛い」
しばらく地面にへたり込んでいたマリアだったが、ふいにおじとおばや町の友達のことを思い出した。よそ者である自分を温かく受け入れてくれた町の人々を、これ以上困ったことにするわけにいかない。
「町のみんなのところへ早く戻らなくちゃ。きっとみんな苦しんでるに違いないわ」
こう考えるとマリアは一念発起し、荷馬車から降りた時のような勇気を再び奮起した。いつもよりズシッと重たくなった体を振り子のように揺らしながら、力強く町へと進みだした。もちろん手にはしっかりと魔法のビンを握りしめて。
ここ数日で彼女の胃袋の中身は馬車で頂戴した糧食から、そこらに転がっている木の実へと様変わりした。本当は味気ない木の実よりも木の枝になっている甘い香りのする果実が食べたかったのだが、それは叶わずにいた。マリアは一度木に登り実をもぎ取ろうと試したが、丸まった腕と脚では幹にうまく引っかからなかった。さらに木にひっつこうとすると、腕が幹に届く前にお腹がつかえてしまうのだ。それを無理やり押しつぶして木にしがみつくものだから息をするのも苦しくて、とても木登りどころのさわぎではなく結局は木の実で我慢せざるを得なかった。
森を颯爽と駆け抜けていた頃の彼女はどこへ行ったやら、一番そう思っていたのは彼女自身らしい。森で生活していた頃、近所のこどもたちが木に初めて登るときに指導をしたことがあったが、今ではその時のこどもたちにすら指導されてしまいそうだ、と彼女は思い始めた。思い通りに動かない体と木に登ることすらできないこととで、悔しさや情けないという気持ちが顔中にあふれ出た。
しばらく進むとそんなマリアでも登れそうな木があった。枝の一本が低く長く突き出ていて、幹は足を掛けられる程度に反れていた。この木なら枝に手をかけて幹を上り、果実のあるところまで行けそうだ。さっそく登って行ったマリアだが上に行くにつれて木の枝が細くなっていき、次第に何本かの枝から掴むたびにミシッ、ペキッ、という音が出始めた。果実にとどくまで手のひらひとつ分もないというところで、体を支えていた枝がバキッと折れてしまい彼女の左手に握られたまま、一緒に落っこちてしまった。
「ぶふぅ!ぐ、ぐるぢい・・・ふっ、ふっ、い・・・息が」
枝はかわいそうにそのままドサッと地面に落ちてしまったが、彼女自身は他の枝に引っかかり何とか無事だった。正確にいうと引っかかったというより「はまった」といった方が正しい状態だ。
マリアがはまったのは二股に分かれている同じ木の枝で、ちょうどその間に腰から下がスッポリとはまってしまった。たっぷり太ったお腹が双方の枝に支えられてビンの蓋のような役割を果たしている。落下の勢いで枝にたたきつけられた張りのあるお腹は、腰から下の重みでひっぱられて、へそから二つに折りたたまれている。マリアは本の中で異国の農法「ダンダンバタケ」というのを読んだことがあったが、彼女のお腹が今まさに段々になっていることは、あんまりにも苦しくかつてなく焦っていたため気づくことはなかった。
マリアがはまってから数秒もしないうちに、とんでもないしなりの強さに負けて、その枝もメギッと鈍い音を立てて木にくっついている部分から丸ごと一本折れてしまった。幸い枝があったのはそれほど高い位置ではなかったため、マリアもはまったまま地面にドシーンと尻餅をついた。体中の余分な脂肪が波打って彼女の見ている森の風景も一瞬歪んだ。視界が歪んだのは落下の衝撃のせいだけではなく、振動により遅れてに落ちてきた果実が頭にコツッと当ったためでもあった。念願の果実を手に入れたマリアは今までの苦労を忘れそうになったが、木の枝に体がはまったまま抜けないことに気付くと、先ほどまでの嫌な思いがまた戻ってきた。
「なんで抜けないのよ?くっ!ふぬぬぬぬ・・・!つ、痛い痛い!んんっ!!」
体を右へ左へ何度か大きく揺さぶり、やっとのことで枝を体からはなすことができた。息も絶え絶えで頭からはかっかと湯気が立ち、もうこれ以上は動けないといった様子で草の上にドサッと横になった。こんなに必死に動き回ったのは森に住んでいた時、誤って木から落ちてオオカミに追い回されて以来だった。昔の動きやすい体に戻りたいと思うと同時に、おじさんとおばさんが待つ家のあたたかい暖炉の前でゆっくりしたい、そう思っていた。既にあの町はマリアにとって第二の故郷になっていた。そんな我が家を懐かしみながら、その日はもうこれ以上動かず疲れきってぐっすりと眠りについた。
マリアが木に登るのはこりごりだと思い始めてからまた数日が過ぎた。体は日に日に重くなっていくように感じられた。それもそのはず、まじないの効き目は中心の町から始まり、国の外側へいくにつれてより強くなるからだ。
もともとこのまじないは広域の土地を豊かにする呪文であるため、外縁部に近づくにつれてその効果は強くなる。そしてまじないは波紋のように広がっていく。中心が一番早く影響を受けるが、効果が一番如実に表れるのは外側なのだ。町に近づくにつれて、ものやら動物やらが丸くなっていった景色から一行は勘違いをしていた。一行は中心部へ向かい進んでいたため効果が表れた景色を見ることなく、勘違いしたまま通り過ぎてしまったのだ。きっと今頃は国境の生き物やら草地やらが大変な有様になっているだろう。
町があった谷から抜けて久しく、それからずっと森を進んできたがそれもようやく終わりそうだ。森を抜けると切り立った崖が下にのぞいており、その崖をはさんで向こう側にもまたすぐ森が続いていた。ずいぶん下では川がゴウゴウと音をたてて流れていて、流れが突き出た岩にぶつかり一層大きな音を出していた。
しかしその轟音も、川の近くにいれば大きく聞こえるが、なにしろ大変な高さの崖の間を流れていたため、マリアにはただ勢いのよい川が遠くで流れている、としか思われなかった。
崖の間には一本の橋がかけてある。いや、「あった」といった方が正しいだろう。なにせ谷の町へ行くときにはかかっていた橋が真ん中でパックリと割れて、こちらと向こう側の崖にブランと力なく垂れ下がっているのだ。実は例の旅団一行が慌てて馬車を走らせ、無理な橋の渡り方をしたため、もとから古びていた橋に引導を渡してしまったのだ。谷の人々の生活を支えていた老橋はついにその役目を終えた。
「できれば私を向こう側に渡らせてから隠居してほしかった」
前より幾分低くなった声で、マリアはぶつぶつと文句を言った。
ここから向こうへ渡るとなると、また何キロも下流の方へ下って行かなければならない。そうなるとこの体もどうなるのかわかったものじゃない。下手をすると町で見た女性のように歩行も困難になってしまうかもしれない。そう考えただけで彼女はぞっと身震いをした。何より、もし本当にそんなことになればだれがこの飢饉を解決するというのか。そう考えた途端にマリアの体は力がみなぎり、全身があつくなった。もちろんあつくなったというのは心が高ぶっただけでなく、全身に着いた脂肪で体熱が逃げにくくなったのも一要因である。
マリアはここで初めて念のために持ってきた携行道具袋の中を物色し、そこから長めの縄を取出した。これがあればあんなに苦労をしなくても果実がとれたかもしれない、と思うと自然と眉が下がり苦い顔になった。
長縄でうまい具合に輪っかを作り、投げ輪遊びで鍛えた腕を生かして向こう側の木の枝に目がけてヒュッと投げつけ、縄は見事に枝に引っかかった。投げる時に縄を揺らして勢いをつけた際、以前より幾分丸くなった尻やら胸やらがフルフルと揺れたが、お腹だけは重すぎてもはやフルッともせずその場に鎮座していた。
もう一本縄を用意し同じように向こう側の少し低い枝に引っ掛けると、こちら側でも手ごろな枝を見つけて同じように二本の縄をくくりつけ、一本に両手で掴まりもう一本に足を置くようにして縄を伝り始めた。
ちょうど中間までは順調に進んでいたが、だんだん縄へ負荷がかかり、とうとう足をおいていた下の方の縄が切れてしまった。その数秒の後、なんとか両手だけで縄をつかみ必死に持ちこたえていたマリアにも限界が訪れようとしていた。マリアの手がもう少しも力が入らなくなるという寸前で、最後の縄もこと切れた。縄はそれをつかんだまま甲高く恐怖の叫び声をあげている彼女を、向こう側の崖にたたきつけん勢いで迫っていったが、運よく(すぐに運など全然よくなかったと思うことになる)崖にいくつかあいていた小さな穴の一つにストンと入り込むことができた。
前へ 1/2 次へ