英雄サーシャと不思議な薬
前へ 1/5 次へ
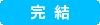
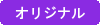
剣を模した木の棒きれが音をたてて空を切る。その甲高い音は幾度も起こらないうちに鳴らなくなった。しんと静まり返る中で次に響いた音は、かすれ気味に聞こえる「参りました」だった。
その声を発した男の喉元には、木で作られた剣が今にも首を貫かんとする勢いでに突きつけられていた。周りにいた者たちは口々に感嘆の声を上げた。しかし、大声で騒ぎたるものなどは一人もいなかった。あまりの気迫と技の素早さに気後れしたためであった。
ここは騎士が技を磨くための修練場。騎士たちはこの場所で日夜一人前の騎士となるべく修行に取り組む。騎士の中には武芸を得手としない比較的華奢な騎士文官もいるが、基本的には全身に金属鎧を着込み、剣を振るうための筋力が必要とされる。そのため、この修練所にいる騎士たちのほとんども筋骨たくましい者たちが多い。
その中で特に目立つ縦にも横にも小さな人物。そのシルエットは鎧を着込んでいてもわかるほどほっそりとしていて、なよっとした、そこはかとない女々しさを放っていた。しかし、その華奢な体躯から繰り出される剣技には一手の無駄もなく、かつ並ぶ者がないほどの素早さで見る者の目をくぎ付けにした。
彼女の名はサーシャ。女として生まれながら騎士として育てられた。生まれた子の適性に応じて育て方を変えるのが、彼女の国の習わしであり女が騎士になるというのも珍しい事ではなかった。しかし年を重ねるにつれて男と女の力の差は歴然としたものになってゆく。女騎士というのは一種の建前であり、形式な者でしかなく実践に投入されるといったことはなかった。
そんな女騎士の常識を塗り替えたのが他ならぬサーシャであった。彼女は貴族の娘として産まれた。本来であれば武家の者でもない貴族階級の娘は、よほど武の才能がない限り行儀作法を学ばせるために他家へと修行に出させるのが一般的だ。幼少の頃からサーシャの活発さは群を抜いていた。貴婦人としての教育を施されそれらを難なく淡々とこなしながらも、サーシャが兄のように慕っている十歳も離れた従卒たちと、野山へよく遊びに出掛けたものだ。
他家に修行へ出させる年齢になった時、両親は悩みに悩んだ。武家の出でもないこの子を騎士として育てて本当に良いのだろうかと。そんな中、その後のサーシャの運命を決定づける出来事が起きた。人の世界にたびたび侵攻を仕掛けてきていた奇形の者どもを打ち破りし英雄が、流浪の旅でたまたまサーシャの一族が治める領内を訪れたのである。サーシャの両親は、これは啓示だと考えてその英雄騎士に娘を預けることにした。
はじめは渋い顔をして崩さなかった騎士だったが、華奢なサーシャの体に収まりきらないほどの活発さが気に入ったのか、後に快諾し彼女を養女として育てることとなった。英雄とうたわれた者の下で修業に励んだサーシャはめきめきとその頭角を現し、二十歳を過ぎた頃には精神的にもその強さも、既に世界で指折りの戦士として成長していた。
腕白で頑固ながらも騎士としての常識はしっかりと身についている。もとよりきれいな金色をしていた髪は更に艶やかなものとなり、首が隠れるほどまで伸ばしている。戦いの邪魔にならない程度に女らしさを残していたいという彼女なりの努力が垣間見える。彼女の小さな体から繰り出される磨かれぬいた技の数々と雷光のごとき素早さは、武の心得がある無しに関わらず、広く知られるところであった。小さいといっても筋肉が自慢の一般騎士に比べたらの話であり、そこらの年頃の若い男性よりはよっぽど立派な体付きをしていた。年を重ねるにつれて大きく成長していく胸部や腰回りは、少々邪魔だと感じているようであった。ともかく、サーシャは騎士としても貴婦人としても申し分ない一人前に成長していた。
サーシャは今、名目上は人質として扱われ城内でもてなしを受けていた。人質といっても彼女の命をどうこうするわけではない。徳を積んだ騎士の命は尊いものであり、むやみやたらに奪われて然るべきものではないのだ。というのは建前で、騎士はいわゆる金貨袋。身代金により身柄が受け渡されるため、捕えた敵方の騎士は大事に扱わなければならない。また、戦場や決闘以外で理不尽な傷を与えることはとても不名誉なこととされており、騎士に対する拷問の類なども諸国会議の取り決めで厳しく禁止されていた。身代金が支払われるまでの間、騎士は軟禁状態であり監視付きではあるが領内での享楽や散策なども認められていた。
そんな事情を抜きにしても、サーシャは客人として目いっぱいのもてなしを受けていた。先ほどの模擬試合は城の血気盛んな従卒たちが、高名なサーシャにぜひ稽古をつけてほしいといい、お付きの騎士の身の回りの仕事をいつもよりさらに手早く済ませて必死にせがんできたため、もてなしの礼もかねて指導していたのである。
そもそもサーシャほどの武芸に長けた人物がなぜ人質として捕えられているのか。ことの発端は経済危機にある。サーシャが今世話になっているこの国は、魔物どもとの戦線に一番近かった。あの異形どもを打ち破るのに全ての財力をなげうったのだ。他国も相当に加勢したが魔物の勢いは凄まじく、奴らを打ち破りはしたものの最前線であるこの国の疲弊ぶりは悲惨なものだった。連合王国もかの戦いの後で、支援する余力は残っていなかった。このままでは国が傾く。面倒な手続きを抜きにして、即急に支援する必要があったのである。
そこに救いの手を差し伸べたのがバルゴ・サルコスことサルコス家であった。サルコス家の当主であり大戦の英雄ことバルゴの下には各国から膨大な恩賞が贈られた。小領主でありながら、連合国の中で一番の物持ちとなった。サルコス家は先祖代々民に尽くすことを家訓としており、精強ながらも所領を拡大させるという野心は持ち合わせていなかった。もとより富に関心がなかったバルゴはこのおびただしい恩賞を国の復興に使ってもらおうと考えた。しかし、なんにしても手続きが面倒だった。自身の所有物とはいえ、元はもらい物。バルゴの働きに報いるために連合国から与えられたものである。決戦の舞台となったサイゼン国にもこれ以上は出せないというほどの物資や支援金が贈られたが、それでもやはり足りなかった。
人の世がここまで繁栄してきたのも一見面倒とさえ思えるこの法があったからであり、いくら英雄といえど面倒な決まり事を全て無視しての勝手がゆるされる物ではなかった。ましてや長きにわたった戦乱が終わりを迎え混迷している最中、これから復興を目指す国々には足並みをそろえた連携が不可欠であった。
そこでバルゴは考えた。
「古くからの騎士の習わしに従い、人質の身代金と称してサイゼン国を支援しよう。」
一見ばかばかしい事のようにも思えるが、この非常化においてはこの上なく最善の策であった。今、諸国連合は微妙な均衡の下に成り立っており、法の乱れが結束の乱れに、引いては国の乱れにつながることをバルゴは重々承知していた。
早速だれを人質として送り出すか会議が開かれた。そこでバンゴの養女でありバンゴに次ぐ大戦の功労者であるサーシャ・サルコスが真っ先に志願した。
「そなたがサイゼン国へとおもむけば、魔物の残党や野盗の牽制にもなるだろう。」
会議に出席していた騎士の一人がそう発言すると、それに呼応するように皆が口々に賛成の声を上げ、サイゼン国の救済という大役はサーシャに任せられることとなった。
そうしてサイゼンへとやってきたサーシャは、存外平和な日々を謳歌していた。古くより魔の国との国境にあったせいかサイゼン国の民の結束は固く、野党などは発生せず、みな力を合わせて国の復興に尽力していた。魔物の方はすっかり成りを潜めたのか、国境に近づいても影も形も見当たらなかった。
このときサイゼン国に魔物たちがいなかった理由は最後の抵抗の準備をしていたからだった。サルコス家の治める領土はサイゼン程でないにせよ、魔の国に限りなく近い国であった。魔物たちは戦や悪巧みの度に幾度となくバルゴに邪魔をされ、たいそう腹を立てていた。絶大な力を誇る首領がバルゴによって倒された折に軍勢は四散したが、首領の近衛兵団が軍をまとめ上げ、再度、バルゴの治めるサルコス領へと攻勢を仕掛けてきたのである。
すぐに届けられるはずであった身代金は、このゴタゴタが片付くまで送り届けることが不可能となった。その知らせを聞いたサーシャはサルコス領に戻ろうとしたが、バルゴからの使者がやってきた。
「こちらはすぐに片付くためサイゼン国で待機せよ、との仰せにございます。」
サーシャは心底安心した。魔の者とはいえ既に一度士気が崩れて戦い傷つき、復讐にかられた集団だ。近衛兵とはいえその数もだいぶ減った。もはやバルゴの敵ではない。そう思った。実際、この最後の小競り合いはサーシャの思ったところと同じになり、サルコス勢は時間こそかかったものの快勝した。大戦が鮮烈すぎたため印象は薄いが、この小競り合いでのバルゴと近衛兵団残党との戦いは歴史上でも稀な名勝負として、戦マニアの騎士や村人たちにより後世まで語り継がれることとなる。
サーシャは身代金も支払われず暇を持て余すこととなった。ともあれ彼女は国を挙げてのもてなしを受けた。鷹狩りに出かけたり、剣の稽古をつけたり、仲良くなった世話役の侍女を言いくるめてお忍びで出かけ、客人だからという理由で禁止されていた城下での復興活動を手伝ったりしていた。
それなりに充実した日々を送り、適度に運動も行っていたサーシャであったが、ひとつだけ気になることがあった。食事の多さである。決して不服という意味ではない。むしろこの貧困化において多すぎるほどの量である。サイゼン国としてはこれがサーシャに対する感謝や敬愛の表れなのだろう。英雄であり救世主、そして良き盟友であるサルコス家のサーシャ殿だ。彼女自身もひとかどの勇者でありサイゼン国は何度も窮地を救われた。バルゴ・サルコスが手塩にかけて育てた愛娘でもあるのだ。精一杯もてなさないわけにはいかない。サイゼン王もサーシャもこの接待がやりすぎであることには気づいていた。しかしこれは世界の習わしなのである。
むかし、前代未聞の大飢饉が起こり、「食べ物は食べれるときに、残さず食べる」という習慣が生まれ、その文化が育まれていった。すでに古くさい習慣であるため、サイゼン王は形式的にと、出せる限りの食糧を用意したのである。もちろんすべてサーシャにささげるつもりであり、余りをつまみ食いしようなどとは考えてもいない。しかしサーシャが一人で食べきれる量だとは鼻から思っていなかった。実は王が用意したものよりも少しばかり多かった。復興の手伝いをしてもらった国の人々が、城勤めの者を通してサーシャに食料を分けに来ていたのである。お金も建材も砦の建設などで使い切り何もなかったが、食糧だけは国一番といえるほど豊富にあった。サイゼン国が長年、魔物の進行を食い止められた理由も、この国が大食糧庫であったことが挙げられる。
そこは格式を重んじるサルコス家のサーシャ嬢。騎士としての徳を叩き込まれた彼女には、出された食べ物を残すという選択肢はなかった。多すぎると心の中では思っても、食べて、食べて、食べまくった。それはもう腹がはちきれんばかりに。もともと小食の彼女にはこたえた。朝の稽古やカリなどで体を動かしている分にはまだよかったが、晩餐になると毎日のように暴飲暴食の繰り返し。一緒に卓を囲むサイゼン王と彼のごく近しい騎士たち、給仕たちはそのようなサーシャの様子を心配そうに見つめていた。
「無理をせんでもいいのですぞ。お体を悪くしては元も子もない。」
「そういうわけにはまいりませぬ・・・何一つとってもこの非常化においては貴重なもの。いただいたものを残しては民に申し訳が立ちません。なによりサイゼン国の顔に泥を塗ることになってしまいまグップ・・・」
今日の献立は山で採れる美味な花の実。摘み取るときには乾燥してしなびているのだが、香りが豊潤で茹でると水気がまし、食欲をそそる香りもさらに強くなる。淡白な食感も人気があり、サイゼン国では主食や酒のお供としても広く親しまれている。
しかし、食べた際にガスが発生しやすく、すぐ腹にたまる。さすがにこらえきれなかったのか、まだ童心を残しつつも清廉であるサーシャの口から、信じられないほどドスの利いた低音が大きく広間に響いた。音の主は恥ずかしいやら苦しいやらで何が何だか分からなくなり、片手で赤くなった顔を隠し、もう片方の手で膨れた腹をさすり、その腹を突き出すように背もたれに寄りかかっている。
すかさず話のうまい文官騎士が話題を切り替えたが、結局その日は晩餐が終わるまでサーシャの顔から赤みが抜けることはなかった。
前へ 1/5 次へ